現場歴の長い生活支援員は、仕事でどんなものを持ち歩いているんだろう? そんな風に思うこと、ありませんか?
今日は、新人の生活支援員さんに向けて、現場歴15年の私が日々身につけている「ウエストポーチの中身」をご紹介したいと思います。
ご利用者さんの介助や外部との対応をスムーズにしてくれる“私の7つ道具”。
ただ紹介するだけではなく、それぞれ「なぜそれを持っているのか?」という理由も添えて書いていきます。
「これ、あると便利かも」と思ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。
【📌現場歴15年、このブログを書いている私のプロフィールはこちら】
私の7つ道具とは?
① ウエストポーチ(本体)
まずはウエストポーチそのものが、最初の道具です!
なぜこれなの?
- 両手が自由に使えるから
→移乗介助や、急な動作にも対応しやすいです。 - 利用者さんの興味を引きづらいから
→ボディバッグのように紐が目立つと、気になる方もいるので避けています。 - 引っかかりにくいから
→車いすの背もたれや、備品に引っかかると危険。腰回りに収まるポーチは安全面でも◎。
私の職場には、ボディバッグやサコッシュの紐が見えると、思い切り引っ張ってしまうご利用者さんがいます。ご利用者さんの障害特性に合わせた道具選びも大事です。
② メモ帳とボールペン
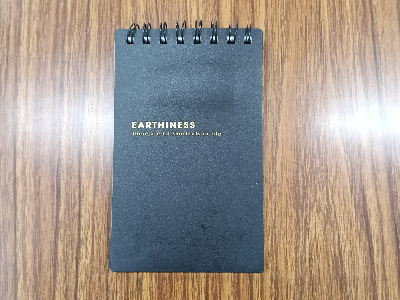
なぜこれなの?
- 備忘録・伝言・記録メモなど、使い道多数
- A7サイズのリングノートを使っていて、必要なページをちぎって渡せるのがポイント。
現場では、ご利用者さんの状況を共有する機会が多いもの。でも、声に出して「〇〇さんが△△です」と伝えるわけにはいかないこともあります。
そんなとき、メモに書いて見せることで、対象のご利用者さんを不安にさせることなく対応することができます。
③ 名刺入れ&名刺
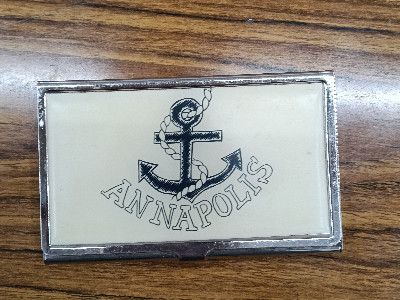
なぜこれなの?
- 来客対応や外出時のトラブルに役立つ
- 急な訪問者に対応したり、外出先で職場情報を伝えたい時に重宝します。
ぶっちゃけ、新人さんのうちは名刺交換をする機会も少ないかもしれませんが、職場情報を伝えるという意味で持っておくと重宝しますよ。
④ 小銭入れ(100円玉5〜6枚)

なぜこれなの?
- ちょっとした買い物や急な支払いに便利
- 財布を持ち歩くと動きにくいし、落とすリスクもあるので、小銭入れだけ携帯。
特に、ウォーキングの引率で外に出たとき、自販機で飲み物が買えるので重宝しています。
活動に目的を設定し、歩くことに苦手意識があるご利用者さんの、やる気をサポートする方法についてはこちらの記事をご覧ください👇️
⑤ ミントタブレット
なぜこれなの?
- 眠気覚ましとして持ち歩いています。
- 特に送迎や自家用車の運転前にリフレッシュ!眠気は事故の元です。
私の職場では、片道1時間以上運行する号車もあるので、眠気覚ましが欠かせません。
⑥ スマートウォッチ

なぜこれなの?
- 時間&連絡の確認
昔は「手を洗う頻度が高い」「介助中に引っかかるのが嫌」という理由で、着用にはやや消極的でした。でも今は、着信に気付きやすい、時間の確認が楽、という理由で着用するようになりました。
⑦ 携帯電話(私用)
なぜこれなの?
- 連絡用
- タイマー機能を、自分自身のタスク管理やご利用者さんのリマインダーとして活用
時計を読むことが苦手なご利用者さんに、「タイマーが鳴ったらおしまいです」と伝えたり、「〇〇時に特別便の出発」といった、自分自身の仕事を忘れないようにするために使っています。
タスク管理に関するアプリについて書いた記事もありますので、よろしければ覗いてみてください👇️
おわりに
以上が、私が日々身につけている「7つ道具」です。
どれも特別なアイテムではなく、よく使うものを最低限持ち歩くことで、現場での安心とスムーズな支援につながっています。
新人さんにとっては、支援の内容だけでなく「どう動くか」「どんな道具を使うか」も大事。あれもこれもと詰め込みすぎず、取り出しやすさを重視するのがポイントです。
絶対的な正解はありませんので、いろいろ試して自分の肌に合うアイテムを見つけてみてください。
【新人さんのためのスタートブック(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
新人さんや実習生の受け入れを担当した際には、「わからない人の視点でアドバイスをしてくれるのが助かる」と高評価を頂いています。
スキルアップだけでなく、セルフケアにも関心があり、同じ現場で働く仲間が、少しでも長くこの仕事を続けられるようにという思いを込めてブログを運営しています。


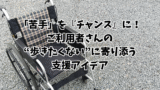
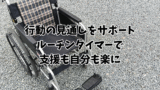
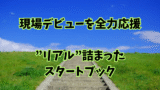


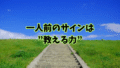
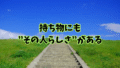
コメント