私が勤めている生活介護事業所では、10名ほどのご利用者さんが車いすを利用しています。
生活支援の現場で、車椅子介助の際に大切なことのひとつが「坂道の対応」です。特に、
「急な坂道では、進行方向と反対を向いて下りる」
これは教科書にも出てくる程の基本動作ですが、ふと疑問が湧きました。
どれくらいの坂道で「後ろを向く」判断をすればいいの?
その疑問を確かめるため、実際に坂道を作り、勾配ごとの感覚を“体験”してみました。この記事では、支援員の皆さんが日々の支援で迷いやすい「どこからが危険か」の判断スキルを身につけるためのヒントをまとめました。
【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】
実験の概要|自作の坂道で勾配を体験!
.png)
自宅にあった木材を使って、長さ2mほどの坂道を作成。そこに手動式の介助型車椅子を使用し、「勾配1%ずつ」坂道をつけながら体感してみました。
車いすの種類に関して知りたい方のために、私が参考にしているページをご用意しました👇️
-1.png)
✅ 勾配とは?
100m進んで1m上がる=勾配1%
→ 今回は「2m進んで2cm上がる」で1%ずつ再現

使用した材木の厚み(2cm、4cm)を活かして、段階的に角度を増やしていきます。
※勾配の計算には「TOM’s Web Site」様の勾配計算ツールを利用しています
※ヘルメット・膝パッド装着で安全に配慮して実施しています。ご自身で実験される場合は、安全面に十分配慮し、複数名で実施するなど安全対策をお願いします。
-2.png)
実験①|勾配 0〜3%:「ゆるやかな傾斜」
| 勾配 | 使用者としての感覚 | 介助者の判断 |
|---|---|---|
| 0% | 完全に平坦 | 特に意識なし |
| 1% | 「言われれば…?」程度 | 坂とは気づかない |
| 2% | 見た目は傾斜と分かるが、怖さなし | 後ろ向きの必要性は感じない |
| 3% | わずかに動き出す感じあり | 後ろ向きにするかは微妙な判断 |
💡 このあたりまでは「急」と感じないが、ご利用者さん視点ではすでに“動き出す不安”が出てくる場面も。
実験②|勾配 4〜6%:「不安を感じはじめる傾斜」

| 勾配 | 使用者としての感覚 | 介助者の判断 |
|---|---|---|
| 4% | ブレーキをかけていても“滑りそう”な不安 | 状況によっては後ろ向き介助を検討 |
| 5% | 明らかに“下る”感覚。板の上では滑ることも | 後ろ向きが安心 |
| 6% | 坂に乗ること自体に怖さあり | “このまま下るのは危険”と判断できるレベル |
🧠 「そろそろ反対を向いた方がいいかも」という感覚は、4%あたりからはっきりしてきます。
実験③|勾配 7〜10%:「急な坂」と明確に感じる傾斜

| 勾配 | 使用者としての感覚 | 介助者の判断 |
|---|---|---|
| 7% | ハンドリムを持っていないと怖い | 車椅子が勝手に進む可能性あり |
| 8% | いるだけで不安。制動力が足りない | 可能なら単独介助は避けたい |
| 9% | 完全に“滑り落ちる”危険を感じる | 実際に支えるのも大変 |
| 10% | 実用的ではない。事故リスクを強く感じる | できれば通らないのが理想 |
⚠️ このレベルになると、もはや「急」ではなく「危険」と言える傾斜。
道路の勾配については、「最大12%」と規定されているので、今回の実験よりも急な坂道があるということですが、車いすで上り下りするのは現実的ではありません。
道路の勾配については、こちらの資料を参考にしました👇️
👉️坂が多い地域特性に応じた道路基準の緩和により、住民に使いやすくコストを抑えた道路を整備(内閣府ホームページ)
考察|「急な坂道を判断する」というスキル

実験を通して私が感じたのは、以下のポイントです。
- “勾配4%”から「不安」が生まれる
- 6%以降は「後ろ向きでないと危険」と感じる
- 使用者目線の方が、見た目以上に怖さを感じる
🚩【支援の目安】
「どちらかが少しでも不安を感じたら、迷わず反対を向いて下りる」
この判断が、安全への最短ルートかもしれません。もし、ご利用者さんと意思疎通が取りにくい場合は、自分が思っているよりも少し早めに後ろを向く判断をするのが良いのではないでしょうか。
まとめ|“感覚”で支援の精度を高めるために
今回は、「急な坂道とはどれくらいか?」をテーマに、坂道を自作して車椅子で体験した記録をご紹介しました。
- 4%前後から恐怖感が出てくる
- 勾配を“数字と感覚”で結びつけることができた
- 安全確保のためには、坂を感じたら「早めに後ろ向きになる」のがベスト
あくまで個人の体験ですが、支援員として「体感しておく」ことは、いざという時の判断力につながります。この記事が、どこかの支援現場で役立つヒントになれば嬉しいです。
車いすやスロープなど、福祉用具の選び方について知りたい人はこちらの資料が参考になるかもしれません👇️
👉️介護保険における福祉用具の選定の判断基準|改訂案(厚生労働省:PDF)
【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️






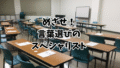
コメント