私が、介護福祉士やケアマネージャーの試験勉強をしていたときのことです。参考書を使って勉強し、習熟度をチェックするために過去問を解き、試験対策をしていました。
受験票を確認し、前日に持ち物もチェックしたはずなのに、なぜか試験当日「準備万端!すべてが上手くいった」とはならなかったんです。
今回は、そんな私の経験を元に、「当日のベストコンディション」を整えるための、前日にしておくべき準備の工夫をご紹介します。
【📌ケアマネや介護福祉士の資格を持ち、現役の生活支援員である私のプロフィールはこちら】
☑当日の朝ごはんを決めておく
試験ってとにかく頭を使いますよね。だから、家を出るまではできるだけエネルギーを温存しておきたい。でも、私は朝から「朝ごはんは何を食べよう」と迷ってしまったんです。
前日に朝ごはんを決めておけば、悩まずに済むだけでなく、準備や片づけにかかる時間もわかるので、時間的に焦ることもなくなります。
これは、いわゆる「脳の決断疲れ」への対策。朝食のテンプレ化はセルフケアにも繋がりますので、よろしければこちらの記事をご覧ください👇️
👉️心を強くする思考力の鍛え方「決断疲れ」の対処法(関東百貨店健康保険組合)
☑ブドウ糖で集中力をサポート
試験にはベストコンディションで臨みたい。そんな時に欠かせないのが「脳のエネルギー源」です。甘いものを食べると気持ちがリラックスできるので、まさに一石二鳥。
私は、試験会場入りする前や、休憩時間に食べれるように、ブドウ糖タブレットを用意していきました。特に、介護福祉士の試験は午前午後に分かれていたので、休憩時間の甘いものに助けられました。
介護福祉士の試験の時に、大袋のまま持っていき、取り出す時にガサガサ音がしてしまったので、ケアマネの試験の時には、ポーチに小分けにして、ポケットにも2〜3個入れていました。
☑腕時計はアナログがおすすめ!
試験の時間管理に重要な腕時計。デジタル式でもOKなんですが、私はアナログ式を強くオススメします。
理由は「スマートウォッチと間違われにくいから」。試験管がパッと見て「腕時計である」とわかるアナログ式のほうが、試験に全神経を集中させることができます。
私は普段腕時計をしないので、「気づいたら電池が切れていた」という心配がない、ソーラー式の腕時計を愛用しています。
☑スキマ勉強用に「ポケットブック」
試験会場までの移動時間や、会場入りしてから試験が始まるまで、介護福祉士の試験の場合は午後の試験が始まるまで、など、試験当日は思った以上にスキマ時間があるなと感じました。
そんな時に活躍したのが、ポケットに入るサイズの参考書です。場所を選ばずにサッと取り出せて、試験が始まったらカバンにサッとしまえばOK。
スマホのほうが、サッと取り出してすぐに勉強できそうなイメージがありますが、電波状況に左右されることや、勉強以外にも使えて誘惑が大きいので私には不向きでした。
まとめ:「当日の持ち物」だけが準備物ではない
私自身、いくつかの資格試験を受けてきた中で、当日にどれだけ落ち着いて試験に臨めるかは、勉強量だけでなく「前日の準備」にも左右されることを痛感しています。
特に、仕事と勉強の両立を目指す場合、朝食の工夫や集中力を支えるエネルギー補給、スキマ時間を有効にする参考書選びなどで、どれだけ当日のパフォーマンスを高めるかがカギを握ります。
通信講座やオンライン教材で学んだ知識も、試験本番で力を発揮できなければ宝の持ち腐れ。
勉強法と同じくらい、準備とコンディション作りに意識を向けることで、努力を最大限に活かせるはずです。
私の経験が、これから資格試験に挑戦するあなたの参考になれば嬉しいです。
【資格試験勉強と研修対策の工夫|私の実践ノート】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員で、小学校第1種教員免許や、介護福祉士の資格を持っています。
ABA(応用行動分析学)をベースにした”環境を整える支援”で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自信があります。
実はココだけの話、座学はちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線での体験談」をぜひご覧下さい。


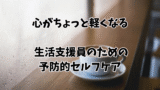





コメント