生活支援員の仕事って、「人のケアをする仕事」
気をつかいすぎて、気づけば自分のことは後回し…。
日中の支援でやさしさをフル稼働したあと、
今度は会議や記録で脳みそまでぐったり。
どうにか家に帰ってきてご飯は食べた。何かしたいけど、何もしたくない——。
そんな時は「ちゃんとしたケア」より「ちょっとしたケア」がおすすめ。
今回は、私が「心が限界になる前にしている」
お金も手間もかけずにできる、“ちょっとひと息”セルフケア術を3つ紹介します。
【📌仕事と暮らしのベストバランスを大事にしている私のプロフィールはこちら】
1.レンチン蒸しタオルで、目と気持ちをあたためる

頭がパンパンで、これ以上何の情報も入ってこない…。
そんな夜は、視界ごと休ませてあげるのがいちばんだと思っています。
やり方は簡単。
濡らして軽く絞ったタオルを、電子レンジで30秒〜1分温めて、
そっと目の上に置いて、深呼吸。
目を温めることで、眼精疲労が回復するだけでなく、副交感神経が優位になってリラックス効果が期待できるそうです👇️
👉️目を温めて自律神経を整える!?(いりなか眼科クリニック)
これは私だけの、ココだけの話ですが、目を閉じて、ゆっくり息を吐きながら
「んだぁあああ〜〜〜〜……」って声に出してます
これで、ご利用者さんへの気づかれや、会議のモヤモヤなどが体から出ていく気がするんですよね(笑)
人には聞かせられないけど、この“んだぁあああ〜〜〜”が、私にはけっこう効くんです。
あとは、目に乗せたタオルが覚めるまでの数分間、ただぼーっとするだけ。
それだけで、フラットな自分に戻れる感覚があります。
2.“専用の部屋着”に着替えて、心に合図を送る

セルフケアって、自分に安心をあげる時間だと思っています。
そこで私は「この服に着替えたら、リラックスできる」って思える一着を用意しています。
ヨレヨレでも、安物でもいいんです。
着替えた瞬間、心の中でスイッチが「オフ」になるように、
自分にとっての“終業モード”をつくってあげる感じです。
”〇〇したら△△”と脳が覚えることを、アンカリングと言うそうですよ。
あとは、好きな姿勢でぼんやりするだけ。
蒸しタオルの「んだぁあああ〜」と組み合わせることもありますよ(笑)
3.大好物のシュークリームを、お皿に乗せて食べる

私が考える「ちょっとしたセルフケア」に必要なのは、普段の生活にほんの少しの工夫をすること。
普段コンビニで買っているいつものシュークリームも、工夫次第でセルフケアのアイテムとして使えます。会議や研修で疲れた私の脳を救うのは、やっぱり甘いものです(笑)
いつもなら、袋を開けてかぶりつくところを、あえてお気に入りのお皿に乗せてから食べます。
この一手間が、実は自分を労る工夫。「いつもより、自分を大切にしている感じ」を目に見える形にしてあげることで、ほっと気持ちが安らぐんです。
これは、心理学の「非日常性がもたらす効果」に心の動きが似ています。
👉️非日常性がもたらす効果(Creative Intelligence)
おわりに|“ちゃんとしたケア”より、“ちょっとしたケア”を
セルフケアと聞くと、本格的なヨガとか瞑想とか、
「ちゃんとやらなきゃ」って思われがちだけど、
ほんとはもっと自由で、もっとゆるくていい。
がんばる生活支援員だからこそ、
自分を最優先にする時間を、自分にプレゼントしてほしいなって思います。
何かしたいけど何もしたくない日。
それは、心からの「小さなSOS」かもしれません。
厚生労働省のこちらの記事でも、自分自身の小さなSOSに気づくことの大切さについて書かれています👇️
誰かのケアに一生懸命なあなたが、
誰かのケアばかりにならないように、そんな願いを込めて書きました。
【生活支援員のためのセルフケア】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
生活介護事業所で15年働く、現役の生活支援員です。小学校第1種教員免許や、介護福祉士、ケアマネージャーの資格を持っています。
でも実は、常に第一線で働いてきたわけではありません。調子を崩して、専門家の力を借りながら立て直した時期もあります。
その経験から、「セルフケアって大事だな」と実感するようになりました。
このカテゴリでは、あの時の経験が誰かの役に立てればという願いを込めて、“体をいたわる支援のしかた”や、“ちょっとした整え方”を、私なりの言葉でまとめています。

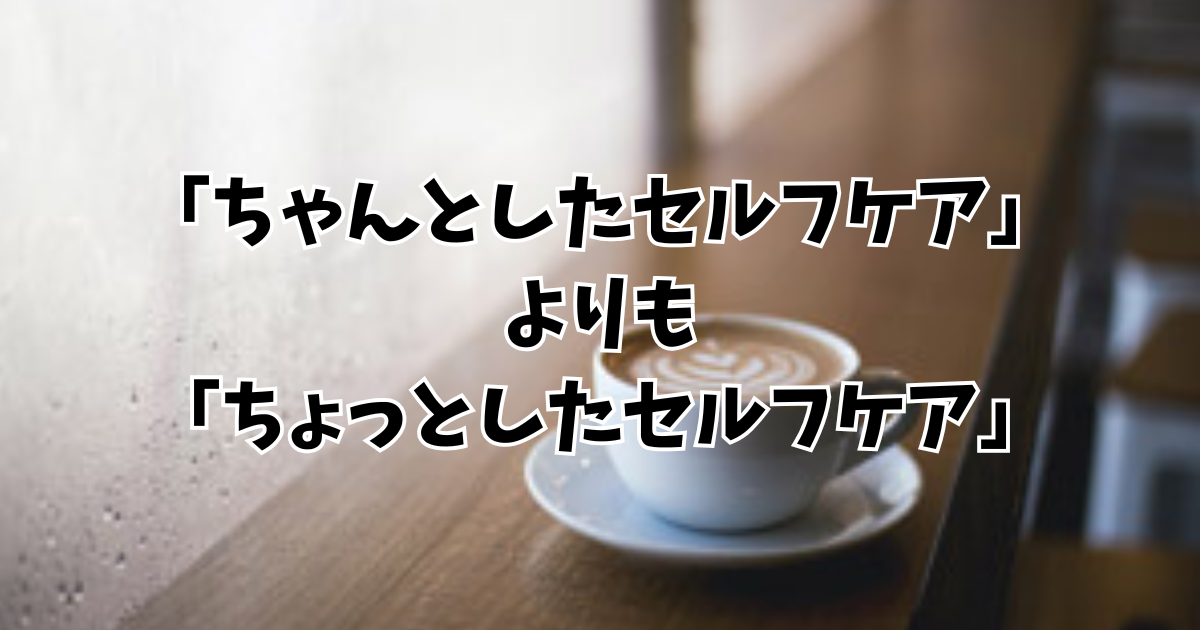
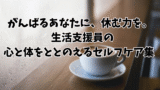


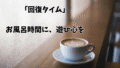
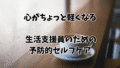
コメント