生活支援の現場に入って15年。新人さんの研修を任されることも多くなりました。
その中で、特によく聞くのが「ご利用者さんの名前が覚えられない」という悩みです。
でも実は、名前を覚えるだけでは、支援の質は上がりません。支援の信頼を左右する、もう一つの大事な視点──それが“物との一致”です。
【📌現場歴15年。この記事を書いている私のプロフィールはこちら】
「顔と名前」よりも、「顔と物」を一致させてほしい理由
私が新人さんの研修に入るとき、必ず伝えていることがあります。
「顔と名前」だけでなく、「顔と持ち物」を一致させてください。
なぜなら、ご利用者さんの中には、持ち物に強い思い入れがある方や、逆にまったく関心がなく、生活支援員が全ての管理を行う必要がある方もいるからです。
たとえば──
リュック、水筒、財布、薬のケース、ハンカチ、着替え…それぞれが「その人のものであること」が、支援の中ではとても重要になります。
“物の取り違え”は、時に信頼を損なうだけでなく、支援員側に責任が問われる事態にもなり得るんです。
【体験談】Aさんの財布を、Bさんのカバンに入れてしまった
これは私が支援員になって数年目の頃の話です。
ご利用者さん数名と映画に行ったときのこと。チケットの代金を一時的に立て替え、施設に戻ってからそれぞれのお財布から集金させてもらう段取りでした。
利用者さんのお財布を預かり集金していたときのこと。慣れた作業の中で私は、Aさんの財布を、うっかりBさんのカバンに入れてしまったんです。
AさんもBさんも、ご自分の荷物に関心がないため、私がお金の出し入れをすべて行っていました。
その時は全く気づかず、帰宅後、Aさんのご家族さんから「財布が入っていない」と連絡があり、ミスが発覚。
結果的には、Bさんのご家族さんから、「本人のものではない財布が入っていた」と連絡があり、大きなトラブルにはなりませんでした。
けれどもし、中身が減っていたら?
万が一、財布が見つからなかったら……?
考えれば考えるほど、ぞっとしました。補償問題や信頼関係の崩壊にもつながりかねない重大なミスだったと、今でも忘れられません。
「物」との一致が、支援の安全と信頼を守る
それ以来私は、名前と顔だけでなく、「このリュックは誰のものか」「この水筒は誰が使っているか」をしっかり頭に入れるようにしています。
そして、新人さんにも「ご利用者さんが持ち物を新調されたタイミングで、ミスが起こりやすいですよ」とアドバイスできるようになりました。
ご本人さんが自分の荷物を自分で管理できる方なら、持ち物の取り違えは非常にデリケートな問題になりますし、ご自身で管理が難しい方なら、私たちの確認ミスが直接ご本人の安全に影響することもあります。
名前も、物も、その人らしさの一部
もちろん、名前を覚えることが不要だとは思っていません。
名前を覚えることは、新人さんにとって大切な第一歩。だからこそ、大手サイトのアドバイスが役に立つ場面もたくさんあります。
でも、実際に現場に出ると、名前と顔だけでは支えきれない瞬間があるのも事実なんです。
私は、物と人をつなげる“もう一歩深い理解”が、支援の安心をつくると信じています。
そんな現場での気づきを、少しずつ伝えていけたらと思います。
私自身の経験として、冬場に3名のご利用者さんが、全く同じ色のユニクロのダウンを着て来所し、現場が混乱したことがあります。
「ご利用者さんが同じ上着を来ていて、誰のものかわからなくなる」というこの状況。言い換えれば「誰のものかをしっかり判別できれば混乱しない」ということです。
ものの見方を変える”リフレーミング”についても、私の体験談をまとめていますので、興味がある人は覗いてみてください👇️
まとめ:名前を覚えることは「入り口」、でもその先が大事
支援の安心は、「名前を呼べる」だけではなく、「その人の大切なものを守れる」ことから生まれます。
新人の頃は、焦ってすべてを一気に覚えようとしがちですが、まずは「Aさんの水筒はこれ」「このリュックはBさんのもの」という情報と一緒に覚えていくと、自然と名前にもつながっていきます。
顔と名前、顔と物、そのどちらも少しずつ。
支援の現場は、そうやって“その人らしさ”を覚えていく時間なんだと思います。
【新人さんのためのスタートブック(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
新人さんや実習生の受け入れを担当した際には、「わからない人の視点でアドバイスをしてくれるのが助かる」と高評価を頂いています。
スキルアップだけでなく、セルフケアにも関心があり、同じ現場で働く仲間が、少しでも長くこの仕事を続けられるようにという思いを込めてブログを運営しています。

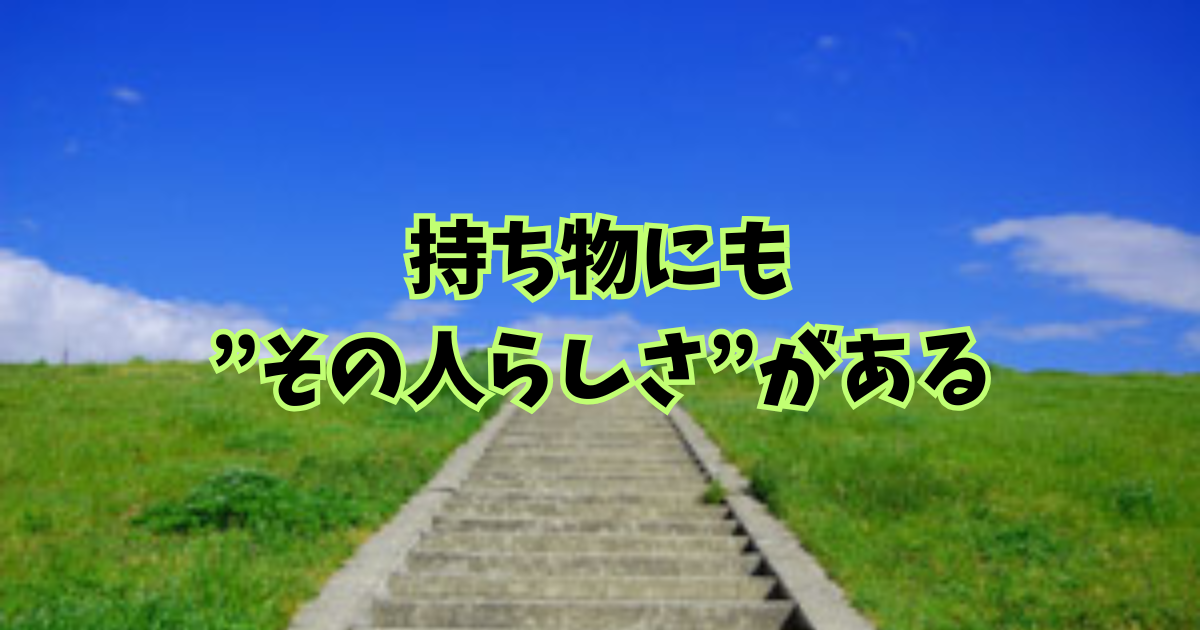
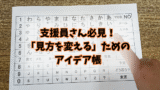
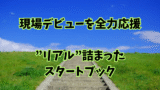


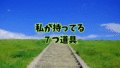
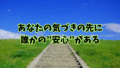
コメント