「慣れた動きほどミスが出る」——送迎業務はまさにその典型。
いつものコースをいつもの手順で、乗り降りの操作もいつも通り。この”いつも通り”に潜むのが、一歩間違えば重大なアクシデントに繋がりかねない「ヒヤリ」です。
だからこそ、私は“手と声”を使う「指差し確認」を導入しています。
ポイントは、しっかり指を指して声に出すこと。これだけで集中のスイッチが入り、最初から最後まで「送迎モード」でいることができます。
今回は、現場歴15年の私が実施している安全対策をご紹介します。
【📌現役生活支援員、ほぼ毎日送迎車両を運転している私のプロフィールはこちら】
なぜ「指差し確認」が大事なのか
指差し確認は難しい言葉で「指差喚呼(しさかんこ)」と言います。
厚生労働省が出しているこちらの記事でも、ヒューマンエラーを減らしたり、集中力を高める効果が期待できるとして、指差喚呼の大切さについて詳しく書かれています👇️
私が特に大事にしているのが「意識がはっきりすること」です。今自分が何をしているのかがはっきりするため、うっかりが減ると考えています。
特に、運転中は「横断歩道に歩行者がいないか」、リフト作業中は「車いす固定のスイッチをオンにしたか」に関して指差し確認をしています。
私がチェックしている”3つのポイント”
①車いすの乗降時
- ブレーキよし(解除/固定ともに)
- シートベルトよし
- (ドアを閉めたあと)ドアよし
送迎時にヒヤリとした経験を元に、目線の配り方やリフト操作の時の立ち位置も工夫しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください👇️
②運転中
- (横断歩道で)歩行者なし
- (発車時)前方よし
- (カーブミラー確認時)よし
生活介護事業所の送迎は、主に平日の朝と夕方に行っています。送迎ルートと通学路が重なっている箇所がいくつかあるので、そこを通る時は特に気をつけています。
③送迎終了時(自分が運転手の時)
- (全員降車を確認して)全員降車よし
- (忘れ物などを確認して)忘れ物なし
自分一人で送迎する場合、特に気をつけています。
夏場の忘れ物で特に気をつけているのは「ペットボトル」。停車中の車内に放置された飲み物を、帰りの送迎時にご利用者さんが飲んでしまうケースが考えられるからです。
私の「うっかり」防止エピソード
車外にご利用者さんの靴⁉️
生活動作のほとんどに介助が必要なAさん。Aさんの乗車後、Bさんのお迎えに行きました。Bさんが乗車後、「ドアよし」と声に出そうとしたら、車外にAさんの靴が落ちていました。
走行中に、Aさんの靴が脱げてしまい、Bさんが乗車するためにドアを開けた時、落ちてしまったものと思われます。
もし、ドアが閉まるのを確認していなかったら、施設に戻って「Aさんが履いていたはずの靴がない」と大騒ぎになっていたかもしれません。
シートベルトのかけ忘れに気づいた
私(運転手)と介助員さんの2名で送迎。車いすを利用しているCさんを”いつも通り”に、リフトで乗車中、「シートベルトよし」と声を出そうとした時、かけ忘れに気づきました。
私達の職場では、運転手と介助員の仕事が明確に分かれているわけではありません。どちらが悪いというわけではなく、お互いの”いつも通り”に潜むうっかりに気づくことができました。
声を出すのが恥ずかしい時は?

職場での決まりがあるわけではなく、あくまでも「自分自身の安全対策」として行うなら、声に出さなくても大丈夫です。
大切なのは、”いつも通り”からくるうっかりをいかに防ぐか。あなた自身が一番しっくり来る方法を見つけてみてください。
ご家族さんにも伝わる安全意識
実はあるご利用者さんのお母さんから、「なぜ指差し確認をしているのか」と質問されたことがあります。理由を説明したところ「電車の運転士さんみたいですね」と言われました。
安全を意識した行動は、ご利用者さんだけでなくご家族さんにもきちんと伝わっているんだなと感じたエピソードです。送迎時は、ご家族さんとお話する機会も多いので、優しい言い換えなどに興味がある人はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
どれだけ安全対策を実施していても、予想外のアクシデントは起こります。大切なのはミスをゼロにしようと思って緊張することではなく、”いつも通り”の中にあるうっかりをできるだけ減らすこと。
私の実施している安全対策が、あなたの参考になれば幸いです。
【生活支援員のための送迎ガイド】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


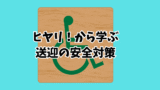

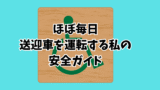


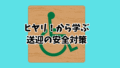
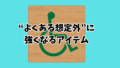
コメント