生活介護事業所では、日中活動の一環として「ウォーキング」を取り入れているところが多いのではないでしょうか。
- 体力づくり
- 気分転換
- 健康管理
と、目的はさまざま。でも、全てのご利用者さんが楽しく歩けるわけではありません。
今回は、生活支援員歴15年の私が実際の現場で見てきた「ウォーキングが苦手な理由」と「4つの対策アイデア」をご紹介します。
【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】
生活介護でウォーキングを行うときの3つの注意点

1.「やめ時」がわからず、歩き続けてしまう
障害特性によっては、歩き始めたら止められなくなってしまうご利用者さんも。疲れを感じていなくても、足や膝に負担がかかっていることもあります。
➡ 支援者の判断で「区切り」を作ってあげる工夫が必要です。
行動をアナウンスしてくれる無料アプリ「ルーチンタイマー」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
2.「歩くこと」がルールのように強く刷り込まれてしまう
ウォーキングと次の活動が強く結びついてしまい、「歩かないと次に進めない」という状態になるケースも。特にASDがあり、行動パターンに強い思い入れがあるご利用者さんに、よく見られる状態です。
➡ 季節や体調に応じて柔軟に変えられるよう、代替活動の準備や、見通しを伝える工夫を
ASDについて詳しく確認したい人は、こちらの記事がわかりやすくておすすめです👇️
👉️大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴は?その特性・行動などを紹介(スマイルクリニック イムス東京)
3.痛みに気づきにくいご利用者さんもいる
感覚に鈍麻がある方は、靴擦れや関節の痛みに気づきにくい場合もあります。
➡ 支援者がこまめにチェックする習慣をつけましょう。
感覚過敏・感覚鈍麻に関して、詳しくはこちらの記事を参考にしてみて下さい👇️
👉️感覚過敏・感覚鈍麻とは|それぞれの特徴と発達障害との関連性、対処法を紹介(大人の発達障害ナビ)
「ウォーキングが苦手」と感じる4つの理由とその対策
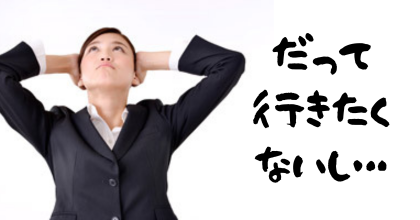
1.歩く目的がわからない
「なぜ歩くのか」が見えづらいと、行動に結びつきにくいご利用者さんもいます。
こんな工夫で対策!
- 歩いた先で「自販機でお茶を買う」など楽しみを用意する
- 「公園の写真を撮ってくる」などの役割を設定する
2.気持ちの切り替えが難しい
気持ちの切り替えが苦手なご利用者さんにとっては、いきなり「歩こう」と言われても難しいもの。
こんな工夫で対策!
- 専用シューズや服で“気持ちの切り替えスイッチ”をつくる
- 「この音楽を聞いたら歩く」といったルーティンを取り入れる
- 朝イチや昼食後など、区切りの良い時間帯に設定する
3.毎回同じコースで飽きてしまう
変化がないと退屈に感じるタイプのご利用者さんもいます。
こんな工夫で対策!
- コースをくじ引きで決めるなど、ゲーム感覚を加える
- 一緒に歩くメンバーを入れ替える
- 時間帯を変えてみる
4.「歩かされている」と感じるのが苦手
運動そのものに苦手意識がある場合、「歩かなければならない」こと自体がプレッシャーになります。
こんな工夫で対策!
- ショッピングモールなどで「結果的に歩いていた」状況をつくる
- ゴミ拾いや写真撮影など“目的のある歩行”を取り入れる
まとめ:歩けたらラッキーくらいの感覚で
ご利用者さんがウォーキングに苦手意識を持つのには、ちゃんと理由があります。
- ご本人さんの特性を知る
- 目的や意味を工夫する
- 「歩けなくてもOK」という選択肢を用意する
これだけで、支援の幅はぐっと広がります。
私の実践例
対象:Aさん
状況:Aさんは、体調管理の面でウォーキングの導入が望ましいが、運動全般に消極的。ある日「4つ葉のクローバー探しが得意」と話してくれた。
実践:ウォーキングではなく、4つ葉のクローバー探しという名目で、近所の公園まで行くことにした。プログラム名も「幸せハンター」と名付け、Aさんのやる気を引き出せるように工夫
結果:2025年6月現在、週3回程度、公園まで700メートルほどの距離を往復することができている。Aさんから「時間ありますか?」と声をかけてくれるようになった
最後に:悩む支援員さんへ、伝えたいこと
「なんで歩いてくれないの?」
「自分の声かけが下手なのかな?」
そんなふうに考えてしまう生活支援員さんへ。
少しの工夫で、ご利用者さんの表情が変わることもあります。
うまくいかなかった日は、「今日はムリな日だったんだな」でOK。
「今日歩けなかった」は、見方を変えれば「歩けないという気持ちに寄り添うことができた」ということ。こういったリフレーミングの考え方のヒントも置いておきます。
日々のウォーキングにちょっとしたアレンジを加えて、「季節のイベント」にするアイデアもご用意しています。興味のある人はぜひ読んでみて下さい。
【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


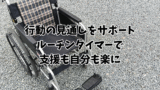
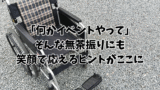
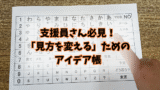





コメント