介護福祉士の試験勉強で、もっともポピュラーな勉強法の1つが「過去問に取り組むこと」ではないでしょうか。
私も、参考書と過去問を揃えて勉強を始めました。でも、途中で「この方法で過去問を解いていたらよくないのかもしれない」と気付いた瞬間があったんです。今思えば、過去問の落とし穴にはまっていたんです。
今回は、現役の生活支援員として働く私が体験した、過去問の落とし穴と、後輩にもアドバイスしている対策方法をご紹介します。
効果を保証するものではありませんが、アナタの資格取得の応援になれば嬉しいです。
【📌ケアマネや介護福祉士の資格を持ち、現役の生活支援員である私のプロフィールはこちら】
過去問の勉強は大切
決して、過去問での勉強が不要だと考えているわけではありません。むしろ、有効な勉強方法だと感じているからこそ、その取り組み方が大切だと感じています。
私自身、参考書で用語を確認し、その分野の過去問を繰り返しとくという方法で勉強を進めていました。
こちらのサイトでも、過去問を使った勉強の意義やメリットについて書かれています。出題傾向なども紹介されているので、深堀りしたい人におすすめの記事です👇️
👉️【2026年版】介護福祉士過去問を徹底解説|無料過去問題集もご紹介(湘南国際アカデミー)
落とし穴|問題と答えを丸暗記してしまった
私は「知識を定着させよう」という意識が強く、同じ問題を繰り返し解いていました。
その結果、問題そのものを暗記してしまい、「この問題の答えは、1」「この問題の答えは、4」というふうに、その問題に対応する答えを記号で覚えてしまったんです。
これこそが私がはまった落とし穴。全く同じ問題が出ない限り対応ができない勉強方法になってしまいました。
この事を、介護福祉士試験に挑戦する後輩に伝えたところ、「自分も問題と答えをセットで覚えていたかもしれません」と、気づきのきっかけになることができました。
対策①ランダム出題のサイトを利用する
私が最初にした対策は、「問題を暗記してしまう方法を防ぐこと」です。同じ問題を繰り返し解くのではなく、幅広い年代の過去問を出題してくれるサイトを利用しました。
私自身が受験したのが10年以上前の話なので、当時どのサイトを利用したかはっきりと覚えていませんが、「今受験するとしたら」という視点でおすすめなのはこちらのサイト。
ダウンロードや登録不要で、すぐに解き始めることができ、年度を絞った出題や、完全ランダムの出題も可能です。スマホでも操作しやすかったですよ👇️
対策②繰り返しは参考書で
知識の定着に関しては、問題と答えがセットになっていない「参考書を繰り返し確認する」ことで対策しました。
過去問を解き、間違っていたら解説を読み、わからない部分は参考書で確認し、知識の定着を図る流れが、自分の中でしっくりくる勉強法です。
対策③1回しか解かない問題を用意しておく
私は、過去問で勉強することのメリットに、「試験の雰囲気が掴めること」があると思っています。
そのために、前年度の問題は最後の最後まで解かないようにし、試験直前の最後の力試しとして活用しました。試験時間なども正確に再現することで、自分なりにイメージを掴むことができました。
試験前日の準備についてチェックしたい人は、こちらの記事がお役に立てるかもしれません👇️
息抜き(=セルフケア)も大切に
社会人として、仕事をしながら勉強するのは大変です。私も0歳児を育てながら、ケアマネ試験に挑戦した経緯があるので、息抜きの大切さを伝えたいです。
特に勉強が佳境に差し掛かると、僅かな時間も勉強に当てたくなるかもしれません。そんな時にオススメしたいのが、私が実践している「朝食テンプレ化」。脳のメモリ節約になるので、仕事と勉強の両立のお役に立てるかもしれません
まとめ|過去問にプラスして“合格の習慣”を
- 過去問で出題傾向を知ること
- 参考書で基礎を固めること
- 模擬試験やランダム出題で応用力をつけること
私は、実際に介護福祉士権に挑戦した経験から、この3つをバランスよく取り入れることが大切だと実感しています。
また、社会人や子育て中の方にとっては「学習習慣をどう作るか」も合否に影響すると考えています。通信講座やオンライン学習サービスをうまく使うと、独学ではカバーしにくい弱点を効率よく補えるかもしれません。
過去問を味方にしながら、“あなたに合った学び方”を見つけることが、合格への近道です。
【資格試験勉強と研修対策の工夫|私の実践ノート】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員で、小学校第1種教員免許や、介護福祉士の資格を持っています。
ABA(応用行動分析学)をベースにした”環境を整える支援”で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自信があります。
実はココだけの話、座学はちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線での体験談」をぜひご覧下さい。




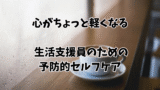





コメント