今日は、「クリンネス」と「クレンリネス」の違い【福祉施設の現場から】というテーマで、生活支援員としての掃除の考え方を書いてみます。
実は私、掃除はあまり得意ではありません。
でも、これまでの職場で「なぜ掃除が大切なのか」を教わってきたおかげで、少しずつ“気持ちがラクになる考え方”を見つけました。
【📌現場歴15年!掃除は”働きやすさにつながる”と思っている私のプロフィールはコチラ】
掃除に追われる毎日。でも、ほんとはそれでいい
生活介護事業所では、日中活動、記録、送迎…やることが山ほどあります。「掃除まで手が回らない」「片付けてもすぐ散らかってしまうはず」——そう感じるのは自然なこと。
でも大事なのは、**“完璧にやること”より、“支援につながる意識を持つこと”**です。
そんな“現場のリアル”を、支援員目線でまとめた記事もあります。伝え方のヒントやデスクワークのコツなど、幅広いテーマで書いていますので、興味がある人は覗いてみて下さい👇
「クリンネス」と「クレンリネス」の違いとは
生活介護事業所の掃除。その心を軽くするヒントになるのが、「クリンネス」と「クレンリネス」という2つの言葉の違いを知ることです。
クリンネスとは
掃除という行動そのもの。
職員目線で言えば、「汚れた場所をきれいにする」こと。
私の勤めている生活介護事業所には、「掃除を手伝いたい」と声をかけてくれるご利用者さんがいます。
机を拭いたり、椅子を片付けるなどがクリンネスです。
クレンリネスとは
きれいな状態を保つこと。
ご利用者さん目線で言えば、「気持ちいい」「快適」と感じられる状態。
生活介護事業所で意識したいポイント
① 掃除=支援の一部
通路に物がないことで、車椅子移動がスムーズになり、転倒リスクも減ります。
つまり、「安全な環境をつくる」という支援の一部なんです。
② きれいを“保つ”ために、無理をしない
一度に全部やろうとしなくてOK。
“気づいたときに一カ所だけ整える”でも、それは立派なクリンネスです。
③ チームで「気持ちいい」を共有する
掃除をする人がいるから、みんなが気持ちよく使える。
「ありがとう」の一言が、クレンリネス(きれいな状態を保つ文化)を育てます。
現場でよくある「できないとき」こそ大事
掃除の途中で呼ばれたり、ご利用者さんの対応で中断することも多いですよね。
それでも大丈夫。
できなかったことより、気づけたことを大切に。
お互いを責めるのではなく、「今は難しいよね」「あとでやろうか」と声を掛け合う。
それも立派なクレンリネスです。
まとめ:完璧じゃなくていい。意識が変われば、掃除はラクになる
「クリンネス」と「クレンリネス」の違いを知ることで、掃除は「やらなきゃ」から「支援の一部」へと変わります。
生活介護の現場では、“できる範囲で整える”ことが、支援員の優しさ。それぞれの”できる範囲”が積み重なれば、大きな力になります。
今日も無理せず、いつもの場所に物を片付けるところから始めてみましょう。
そして私が、がんばりすぎない自分を守るために実践している、「お風呂術」もチェックしてみてください。
【生活支援員のための掃除テクニック】のカテゴリは現在準備中です。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利掃除はご利用者さんのためだけではなく、私達自身の働きやすさにもつながると考え、様々な掃除のアイデアを実践しています。
現場の業務と同じくらい大切なのが、自分自身をいたわるセルフケア。”目指せ福祉マスター”では、仕事と暮らしのベストバランスを応援しています。

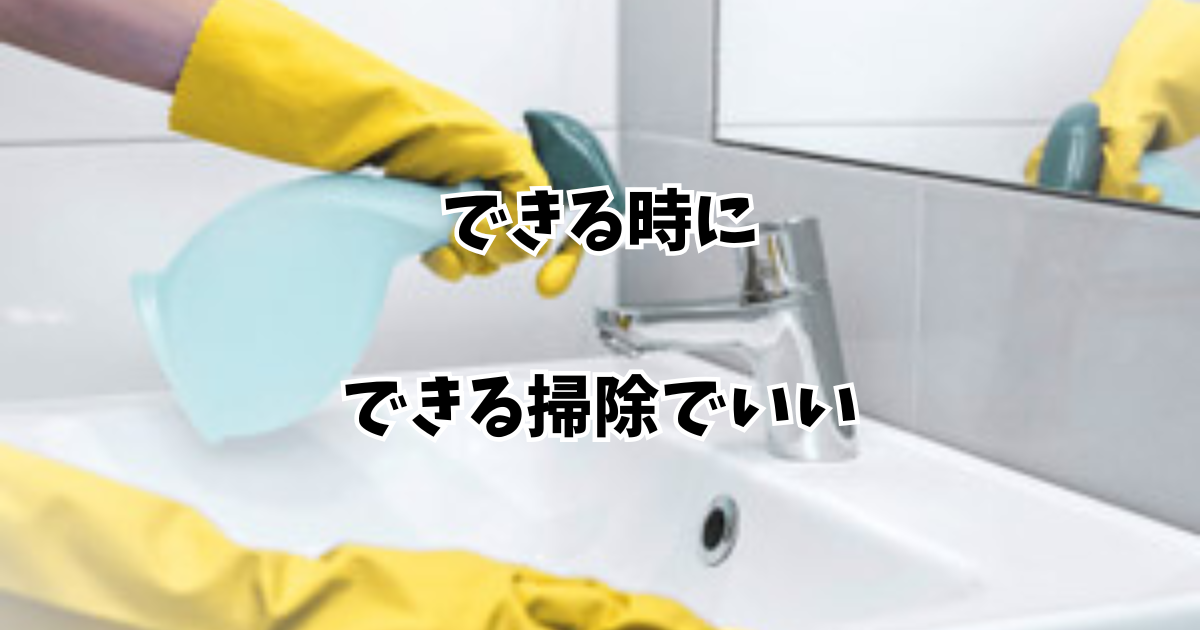

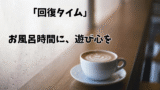

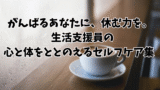
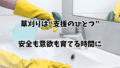

コメント