生活介護事業所では、ご利用者さん一人ひとりのニーズに合わせた支援が日々行われています。
中でも、スケジュール管理や行動面のサポートは、ご本人だけでなくご家族からも高い要望が寄せられる分野ではないでしょうか。
私自身、ご利用者さんのこんな様子を何度も目の当たりにしてきました。
- 活動の途中で離席してしまう
- 次の活動にスムーズに移ることができない
- スキマ時間ができると、落ち着きがなくなってしまう
これは、見通しが持てないことによる不安や混乱かもしれません。この、見通しに関するニーズに応える可能性を秘めているのが、今回ご紹介するアプリ「ルーチンタイマー」です。
【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】
ルーチンタイマーとは?
「ルーチン」とは、決まった動作を繰り返すこと。
「ルーチンタイマー」は、その動作や時間を設定しておくことで、一つずつ順番にアナウンスしてくれるアプリです。
ご利用者さんの支援ツールとしてだけでなく、私自身も複数のご利用者さんに時間差で声を掛ける時など、「覚えておかないと忘れてしまう」という業務をする時に使うことがあります。
ここからは、実際に使ってみて感じたおすすめポイントをご紹介します。
私がルーチンタイマーを知ったのは、SNSプラットフォーム「note」で読んだこちらの記事がきっかけです👇️
👉️ルーチンタイマーはADHDさんの課題解決のために生まれたアプリだった
ルーチンタイマーのここがすごい!
直感的に操作できるシンプル設計

アプリを開くと、
- 上部に「?」と「郵便箱」マーク
- 右下にオレンジ色の「+」マーク
この「+」マークから簡単に行動と時間を設定でき、ルーチン登録が完了します。
文字情報が少ないため、迷わず直感的に操作できるのが魅力です。
視覚ではなく“聴覚”に訴えてくれる
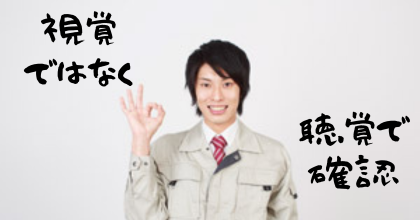
ルーチンを再生すると、
「今から○分間、●●を始めてください」と音声で案内してくれます。
携帯の画面をいちいち確認する必要がないので、次の行動にスムーズに移りやすくなります。
複数のルーチンを登録できる
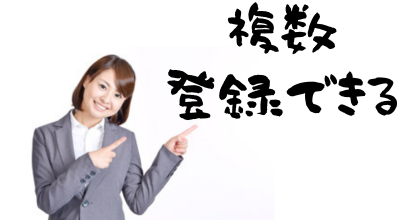
例)
- 朝の支度
- 帰宅後の流れ
- 就寝前の準備
このように場面ごとに複数登録できるので、ご利用者さんの支援にも、自分のタスク管理にも応用しやすいです。
再生中でも微調整が可能
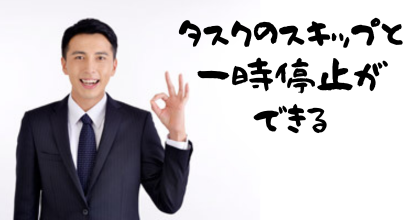
予定より早く終わったり、不要な動作がある場合でも、一時停止・スキップができるため、
柔軟な対応が可能です。いちいち登録し直す手間がないのは大きなメリット!
ルーチンタイマーのデメリットは?
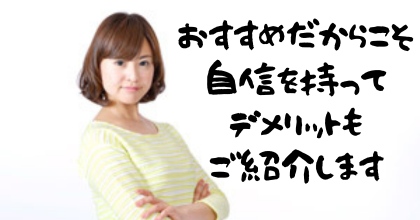
もちろん、完璧なアプリではありません。
以下のような注意点もあります。
- 端末を近くに置いておく必要がある
- 最初は入力作業に慣れが必要
- 集中しすぎるとアナウンスを聞き逃す可能性がある
とはいえ、2024年4月時点では無料でダウンロード可能なので、試してみる価値は十分にあると感じます!

ルーチンタイマーを使った1日の流れ(例)
ルーチンタイマーの設定の例を、こちらのスケジュールでやってみます。
- 9:00 来所
- 10:00 ウォーキング(45分)
- 12:00 昼食(60分)
- 13:00 絵を描く(60分)
- 15:00 帰宅
①来所してから、「荷物をロッカーにしまう」「予定表を確認する」という手順が必要な場合は、それぞれタスクと時間を設定する
②ウォーキングや昼食など、活動の5分前に「ウォーキングの準備」「昼食の準備」といったタスクを設定しておくことで、活動の切り替えを狙うことができる
③絵を描くことに集中しすぎて時間を忘れてしまう場合は、「絵を描く片付けの時間」あるいは「気持ちの切り替え」といったタスクを、5分くらい前に設定し、やめ時をサポートする
ご利用者さんが、何に不安を感じ、どの部分に見通しのサポートが必要かによって、設定するタスクの数や時間は変わります。また、支援者がデバイスを操作するケースも考えられますので、焦らずにベストを探していきましょう。
特にASDがあり、ルーチンが崩れることに強い不安があるご利用者さんにとっては、導入そのものを丁寧に検討していく必要があります。
ASDに関して詳しく知りたい人は、こちらの記事がとても参考になります👇️
👉️大人のASD(自閉症スペクトラム症)とは?特徴や診断、支援先もご紹介(社会保険労務士法人ゆうき事務所)
まとめ|ルーチンタイマーで支援も自分もラクに!
今回ご紹介した「ルーチンタイマー」は、
- 直感的に操作できる
- スケジュール管理・習慣化に役立つ
- 支援員自身のタスク管理にも使える
という魅力があり、支援ツールにも自己管理にも幅広く活用できるアプリです。
「今なんの時間」かがわかることで、不安が軽減できるご利用者さんの場合、ルーチンタイマーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
また、ご家族やご本人自身にも使ってもらえるとさらに効果が広がるかもしれません!

見通しを持つサポートができたら、イベントに参加できる可能性が広がります。もし、ご利用者さんから「なにかイベントをやってほしい」と言われた時のために、イベントのアイデアをストックしておくのはいかがでしょうか。
【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


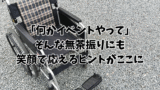





コメント