生活介護の現場で、「ご本人さんやご家族さんには、できるだけ専門用語を使わずに説明する」。
それを大切にしている支援員さん、多いのではないでしょうか。
でも、いざ言い換えようとすると──
「言葉を選ぶのに時間がかかる」
「説明がまわりくどくなって、かえって伝わりづらくなってしまう」
そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
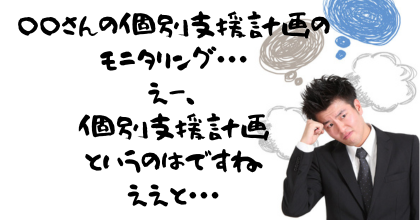
この記事では、専門用語をかみ砕いて説明するためのコツや、実践的なステップ、実際にご利用者さんの反応がどう変わったかをご紹介します。
そしてもうひとつ、「伝え方」について考えるときに知っておきたいのが、リフレーミングとポジティブシンキングの違いです。興味のある方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。
【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】
専門用語って、どこからが“専門”?
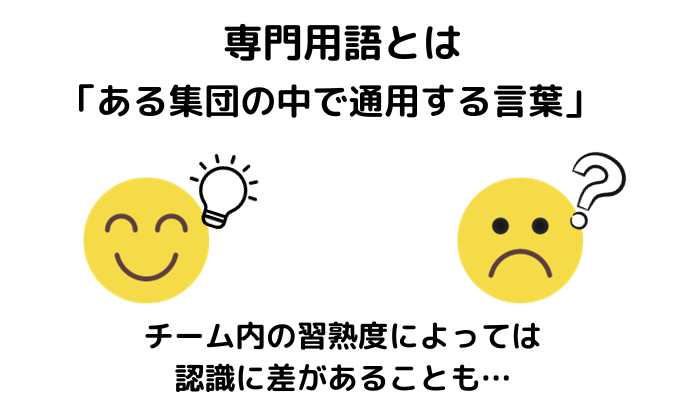
福祉の世界には、「個別支援計画」や「支援手順書」のような書類名のほか、
「ADL(エーディーエル)」「QOL(キューオーエル)」のような略語、
さらには「PT・OT」など職種を示すものまで、さまざまな“専門用語”があふれています。
加えて、「今日はフリーです(=送迎業務なし)」など、職場内だけで通じる言葉も、広い意味では専門用語と言えるかもしれません。
同じ職場でも、ベテランと新人では“共通語”の範囲に違いがあります。
だからこそ、言い換えの力が必要なんです。
なぜ、専門用語は使われるのか?
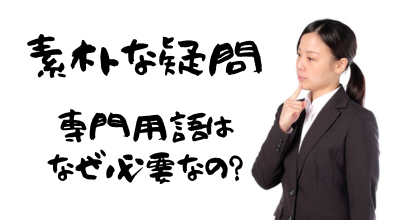
専門用語がなかったら、説明はどうなるでしょう。
たとえば「レスパイトケア」という専門用語がなければ──
「一時的に介護から離れて、心身のリフレッシュができる支援を…」と、長くなってしまいます。
専門用語には、「共通理解によって話がスムーズになる」という強みがあります。
だからこそ、”使いどころ”と“伝えどころ”の見極めが大切になります。
障害者福祉の専門用語が詳しく知りたい方は、こちらのサイトがとても便利ですよ👇️
私の実践:「伝わるコツ」3つのヒント
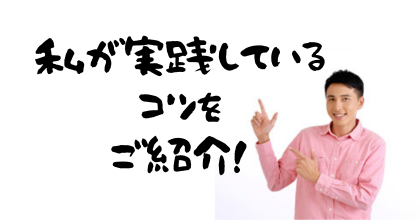
① 相手に寄り添う“前置き言葉”を使ってみる
「ちょっと難しい言葉ですが、“○○”はご存じですか?」
このひと言があるだけで、相手に確認しながら話を進めることができます。
知らなくてもOK、知っていたら自信になる──どちらでも安心して聞ける空気を作れます。
新人研修や実習生の受け入れなどでも活用できる、支援員にとっての“頼れる言葉”です。
② 言い換え練習は2段階で
一気にうまく言い換えようとせず、2段階で練習しています。
ステップ1:日常の言葉を、もっと簡単な言葉に言い換える。
例:「終わりです」→「おしまいです」
それだけで伝わりやすくなるケースもあります。
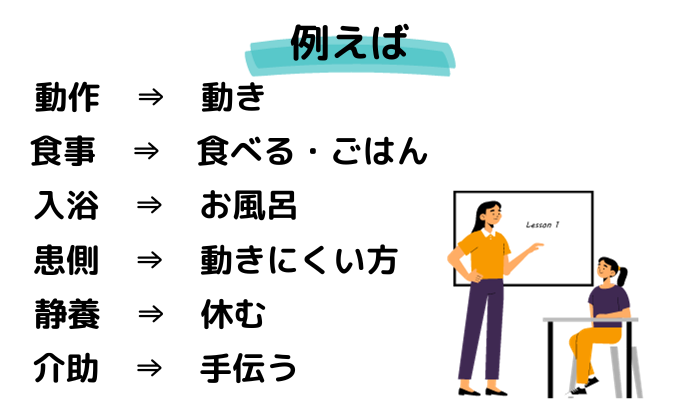
ステップ2:少し難しくても別の言葉に置き換えてみる。
100%正確じゃなくてもOK。言葉のバリエーションが増えることで、応用力が育ちます。
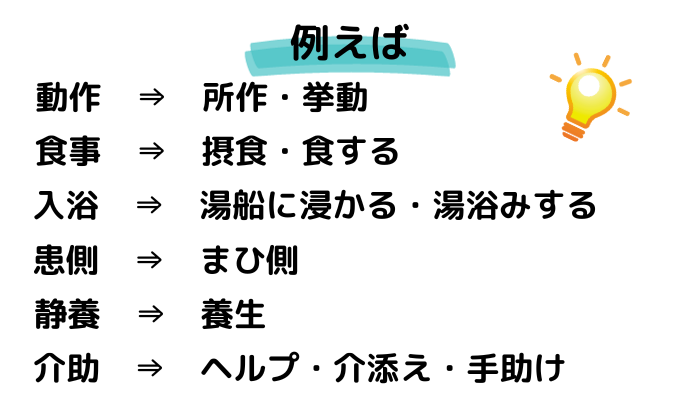
③ 思いきって”かみ砕いてみる”
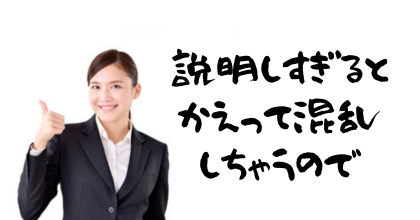
「ADL=日常生活動作」これでは少し専門的。
さらに、「着替え、食事、トイレなど、自分でできること」と言い換えることもできます。
でも、もっとシンプルにするなら──
「自分でできること、どれくらいありますか?」
と、日常の感覚に近づけて伝えるのもひとつです。
削りすぎが不安な場合は、「もっと詳しく説明することもできます」と添えることで、相手が選べるようになります。
実践例:反応がこう変わった
相手に合わせた言い換えで、ご本人さんにどんな反応があったか、2つの事例をご紹介します。
①落ち着いて話を聞いてくれるようになったAさん
Aさんは、軽度の知的発達障害があります。「大人として見られたい」という意識が強く、支援者の言葉の難易度に合わせて話そうとします。
そんなAさんに、運動プログラムの導入を勧めることになりました。
言い換え前:「1回20分、ウォーキングをしませんか?」
⇒「ウォーキング」が本人にとって馴染みがなく、また、時間の理解が苦手だったため、混乱してしまった。
言い換え後、「公園をぐるっと1周、お散歩しませんか?」
⇒本人の馴染みのある言葉で、時間ではなく行動で言い換えたことで、スムーズに定着した。
②笑顔が増えたBさん
Bさんは、重度の知的発達障害があります。60歳を超えていて、最近の出来事よりも子どもの頃のことをよく覚えています。
自分のものが見えなくなると、極端に不安になってしまうBさんの、上着を預かってハンガーにかけておくことになりました。
言い換え前:「上着をハンガーにかけるので、渡して下さい」
⇒上着を脱ぐことは大丈夫でしたが、渡してくれませんでした
言い換え後:「上着を衣紋掛けにかけるので、渡して下さい」
⇒本人の知っている言葉(お母さんが使っている言葉)で言い換えたことで、行動の見通しを持つことができた。
おわりに
「わかりやすく説明したいのに、言葉に詰まってしまう」
その悩みの背景には、支援員さんのやさしさと責任感があります。
だからこそ、日々の支援の中で「本音を話してもらえない…」と感じている支援者さんの悩みがよくわかります。
でもそれは、あなたの“伝え方”が悪いわけじゃなくて、「伝わりやすい環境」が整っていないだけかもしれません。
そして、会話のきっかけに迷ったときは、初対面でも笑顔がこぼれる“おもしろクイズ”という小さな工夫もありますよ。下のリンクに、会話のヒントを置いておきます。
【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。
ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。
ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

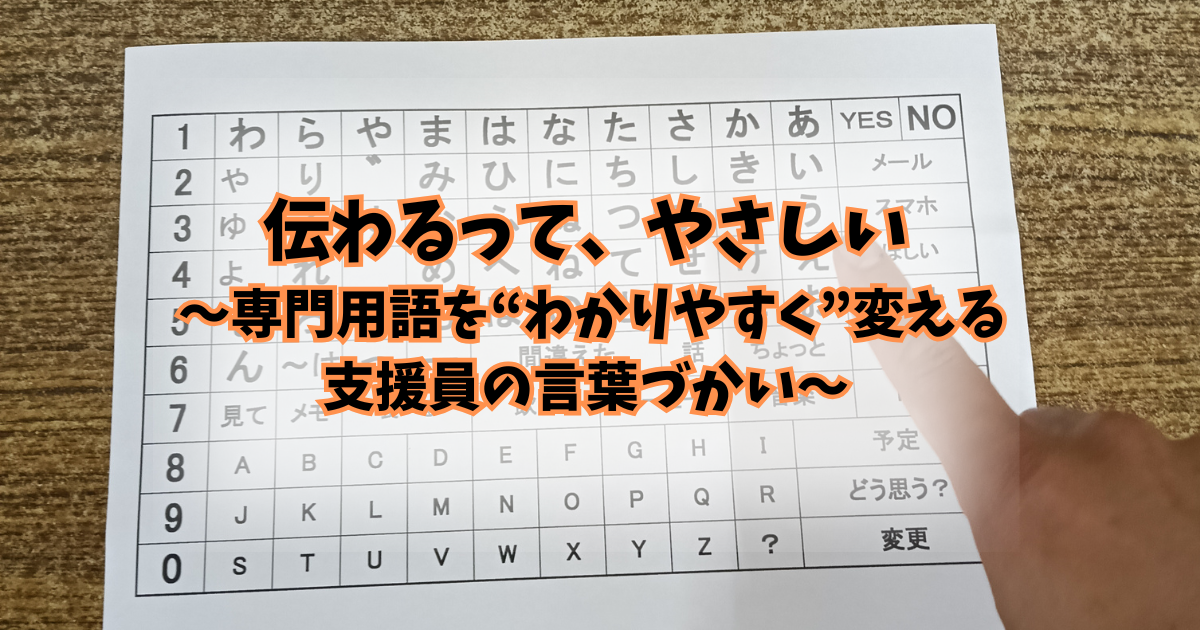
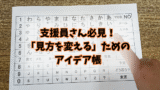
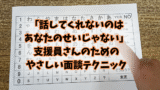
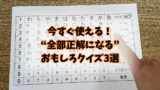
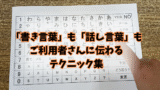


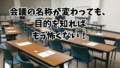
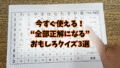
コメント