こちらの記事はSNS「note」の『別館・めざせ福祉マスター』に掲載した3つの記事を再編集して掲載しています。
「生活介護事業所で働いてみたい」と思っているそこのアナタ! 今回は、生活介護事業所で15年間勤務している私が、生活介護事業所の「あるある」をご紹介します。
この記事では、生活介護事業所の『送迎』『車椅子の介助』『仕事中』の「あるある」をご紹介します。障害のある人と関わる仕事に興味がある人に、障害者福祉を身近に感じてもらえるような、思わず頷いてしまうかもしれないあるあるネタを集めました。
この記事は
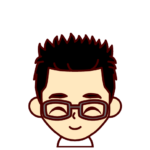
・生活介護事業所で働いてみたい人
・会話のきっかけを探している生活支援員さん
・「私だけじゃなかった!」と共感したい人
におすすめです。
⇒【関連記事】『生活介護事業所の『食事介助』『トイレ介助』『着替えの介助』の「あるある」をたくさん言いたい!』
送迎あるある
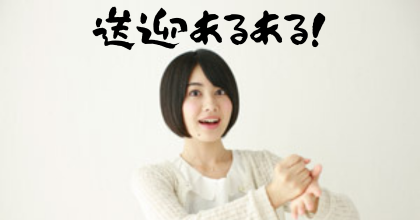
まず最初は、生活介護事業所の「送迎あるある」です。
ハイエースの運転上手くなりがち
最初は「こんな大きな車運転できるの?」と思っていても、いつの間にか乗れるようになっています。
同じ車なのに、ドアが閉まらない事がある
車椅子に乗ったまま乗車可能な福祉車両を運転される方なら、わかっていただけるでしょうか。
乗る位置も、車椅子のサイズも変わっていない、毎日同じ段取りで車椅子を固定してるはずなのに、なぜかドアが閉められないことがあるんです。
同じ場所ですれ違う他の施設のドライバーさんに、妙な親近感を覚えがち
きっと相手も同じことを考えていると思います。
「あ、○○デイサービスの車だ」ってなります(笑)。
送迎コース上のトイレの場所が頭に入っている
長時間運転するルートだと特にそうなんですが、急にトイレに行きたくなったときのために、
利用できるトイレの位置が頭に入っています。
…え? 私だけですか?
福祉車両っぽい車を見ると、施設名を確認してしまいがち
白いハイエースや軽バンなど、福祉車両っぽい車を見かけると、すれ違う時やカーブした時に、チラっと車体の文字を確認してしまいます。
車両ごとに車いすの固定方法が微妙に違って混乱しがち
車椅子を固定するための方法は、車によって違いがあります。
・後部のフックで固定するタイプ
・前部のウインチで固定するタイプ
・前後から引っ張るタイプ
などなど
久しぶりに運転する車の担当になった時に、
「あれ? この車ってどうやって操作するんだったっけ?」ってなりがちです。
雨の日の玄関、混雑する
発車時間や到着時間が重なると、みんなが少しでも雨に濡れないようにという配慮が重なって、混雑しがちになります。
車椅子の介助あるある
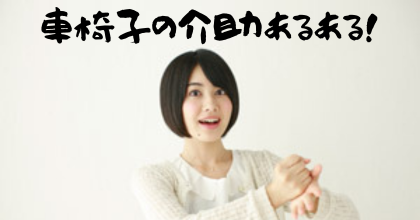
続いては、「車椅子の介助あるある」です。私が勤めている生活介護事業所では、車椅子を利用しているご利用者さんもいるので、ほぼ毎日車椅子の介助があります。
「この幅は通れそう/通れない」という感覚が身につきがち
一般的な車いすの幅は約60センチ、電動車いすの幅が約70センチです。
利用する人に合わせてカスタムしたものは、それよりも幅が広くなることがあります。
私の場合、特に練習したわけではないのに、机と柱の間を通ったり、壁と椅子の間を通るときなど、「あ、この幅は通れるな」という感覚が身につきました。
電動車いすを巧みに操る利用者さんに尊敬のまなざし送りがち
「この空間で転回は無理だろう」と思っている自分の感覚をよそに、時に細かく時に大胆に車いすを操って方向転換するご利用者さんに、
「すごい…」
と尊敬のまなざしを送ってしまいます。
タイヤの空気入れのバルブが「米式」だった場合、戸惑ってしまいがち
細かすぎて伝わらないかもしれませんが、日常的に複数のタイプの車いすを介助する経験がある人や、自転車好きな人なら共感して頂けるでしょうか?
ほとんどの車イスのタイヤは、自転車と同じようなバルブ(英式)なんですが、まれに「米式」のバルブに出会うことがあります。
電動車いすだから、手動車いすだからというわけではないので、車椅子のタイヤの空気を入れようとしたとき、「こっちのタイプだったか~」ってなることがあります。
仕事中のあるある
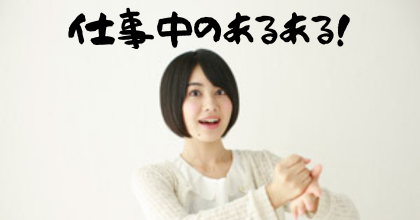
最後は「仕事中のあるある」をご紹介します。
レクリエーションで自分のほうが真剣になりがち
クイズの回答のサポートや、生涯学習講座に参加するご利用者さんの見守りなど、ご利用者さんと一緒に参加した活動で、いつのまにか支援者自身が回答者になったり、自分が疑問に思ったことを質問していることがあります。
一緒に楽しむことはすごく大事です。ご利用者さんも職員さんも、いつも楽しんで活動しています。もちろんご利用者さんのサポートも忘れていませんよ(笑)
ごく稀に「びっくりするほど仕事がない瞬間」がある
「介護の仕事」と聞くと、常に動き回っているイメージを持たれている方も少なくないと思います。
実際に、動き回っていることも多いしです、動きが止まっていても、周囲の様子には常に気を配っています。神経を使っているという意味では、業務中フル稼働です。
ですが、本当にごく稀に、「びっくりするほど仕事がない瞬間」があります。
トイレ介助に呼ばれることもなく、見守り支援が必要なポジションにはすでに人がいる、担当するフロア全体を見回しても、ご利用者さんが落ち着いて過ごしている。
そうかと思うと、「今までの静けさは何だったのかしら」と思うほど、一気に呼ばれたりします。
翌日のイベントの準備をしたい時に限って、戻る時間が遅い送迎車の担当になりがち
直接ご利用者さんに関わる介護以外にも、会議の資料作成やイベントの準備といった仕事が思った以上にあります。
「できるだけ早くまとめておきたい資料がある」
「明日のイベントの段取りを打ち合わせたい」
など、時間に追われた仕事を抱えていたり、送迎が終わってからある程度まとまった時間がほしい時に限って、一番遠いルートを回る送迎車の担当になりがちです。
持ち主を見つけ出す能力を持ったベテラン職員さんがいる
寒暖差の激しい季節には、誰のものかわからない上着などが大部屋の机にぽつんと置かれていることがあります。
こういう時に、かなりの高確率で持ち主を即座に見つけ出す能力を持ったベテラン職員さんがいます。
「これは○○さんが着ていそう」
「そういえば、さっき○○さんがここに座っていた」
「この匂いは…〇〇さんかもしれない!」
など、ベテラン職員さんが数名集まって持ち主不明の上着について意見を交わしている様子は、さながら推理ドラマを見ているようです。
まとめ
今回は、「生活介護事業所のあるある」をテーマに、3つのジャンルのあるあるをご紹介しました。
全て私の経験に基づくものです。「そうそう!」と共感できたものや、「それはあるあるじゃないよ〜」と思われたもの、いろいろあったと思います。
同じ生活介護事業所でも、施設によって雰囲気は様々ですが、少しでも障害者福祉の世界に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
SNS「note」で運営している『別館・めざせ福祉マスター』もぜひご覧下さい。

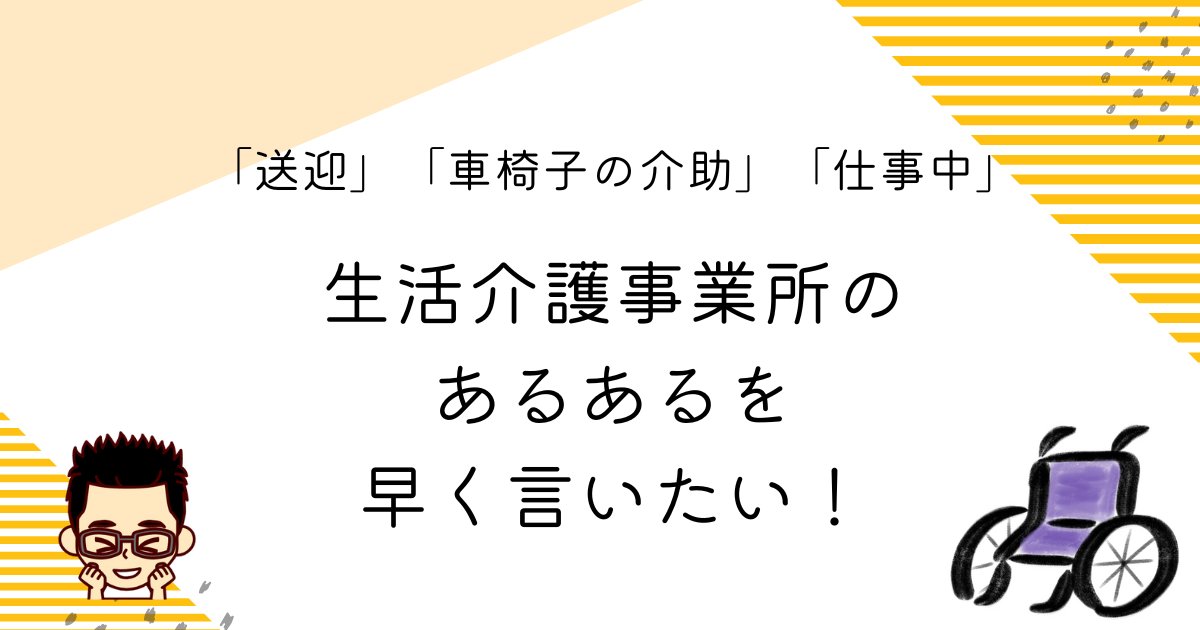
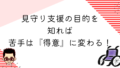

コメント