この記事は、私がSNS「note」で運営している『別館・めざせ!福祉マスター』で、前後編にわけて掲載していた記事を1つにまとめ、再編集しています。
生活介護事業所で働く皆さん。今日は「見守り支援」についてわかりやすく解説します。改めて聞かれると「見守り支援」の目的や方法について、よくわからないと悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。
- 何となく「そこにいるだけ」になってしまう
- すぐに支援介入してしまう
- 今まで目的や方法などについて考えたことがなかった
この記事では、現場歴15年の私が、ワンランク上のサービスが出来る生活支援員になるための、「見守り支援のコツ」を3ステップでわかりやすく説明します。
この記事は
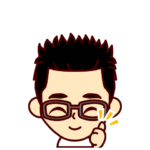
・見守り支援の目的や方法を知りたい中堅職員さん
・新人研修を担当することになった職員さん
・見守り支援の苦手意識をなくしたい生活支援員さん
におすすめです。
ステップ①「見守り支援」を知る
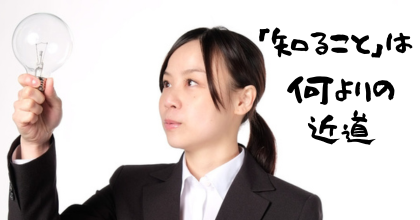
見守り支援の「苦手」を『得意』に変える最初のステップは、見守り支援について知ることです。
生活介護事業所見守り支援とは、ご利用者さんのそばについて、さりげなく様子を見て、突発的な出来事に素早く対応するという介助の方法です。
最初から直接手伝うのではなく、ご利用者さんの言葉や仕草を観察することが中心になります。見守り支援は次のような人に効果的です。
- 誰かが近くにいてくれることで、「今何をして、次に何をするか」を思い出すことができる人
- 1人でいる(と感じる)時に、急な行動が起こりやすくなる人
- 動作そのものは自分でできるけれど、安全面などで配慮が必要な人
距離は一定ではない
いくら「支援」と名がついていても、真横でじっと見つめられていたらストレスがかかります。これでは「見守り」ではなく「監視」になってしまいますね。
かといって、気配を完全に消してしまうと、突発的な行動が起きやすくなってしまうケースがあります。つまり、誰かがそこにいることはわかっているけど、そこまで気にならない距離を見極めていくことが大切です。
ご利用者さんのその日の調子によっても、見守り支援に必要な距離感は変わってきますので、微調整を繰り返しながら試行錯誤を続けていきます。
まずは見守り支援に必要な距離はそれぞれ違う、という部分をおさえ、具体的な距離感についてはステップ2で確認していきましょう。
ステップ②「見守る目的」をはっきりさせる
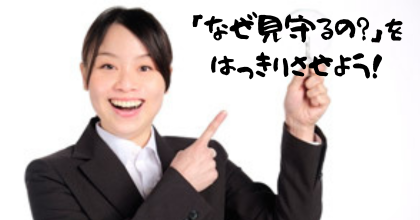
「見守り支援」をする時のポイントは、なぜ見守るのかをはっきりさせることです。ここがブレてしまうと、何の目的もないままとりあえずそばにいる、必要な距離感が取れないことでご利用者さんへのケアが間に合わない、という状況に陥ってしまいます。
ここで想定するのは次の3つのケースです
急な事態に備える
1つ目は、ご利用者さんの突発的な行動に対し、ご本人や周囲への危険を予防する意味で見守りをするケースです。
ご利用者さんの障害特性によっては、気になるものに向かって一直線に走り出してしまったり、自分で自分を叩こうとしてしまったり、近くにいる人を傷つけようとしてしまう事があります。
また、年齢が若いご利用者さんの場合、力が強く、一度走り出してしまうと追いつけなくなることも考えられます。
距離感をつかむ時に考えたいのは、
- ご利用者さんの瞬発力
- 自分の瞬発力
- 建物の構造
などです。1名がご利用者さんのそばにつき、もう1人が部屋の出入り口付近で待機するなど、複数名での対応が必要になる場合もあります。
空間単位で違和感に気づく
2つ目は、1対1ではなく、ご利用者さんの過ごす空間全体を見守るケースです。
自分で自分の気持ちを伝えることが極めて苦手なご利用者さんもいます。また、「休みたくない」という思いから、不調を隠してしまうケースも考えられます。
空間全体を見守ることで、「〇〇さんの元気がなさそう」「いつもよりふらつきが目立つ」といった違和感にいち早く気づくことができる可能性がぐっと高まります。
距離感をつかむ時に考えたいのは、
- 突発的な飛び出しをケアする必要があるか
- 「空間を見守る人」と「対応する人」で意思疎通が取れるか
- 動きながら見守るか、定位置で見守るか
などです。どちらかというと、「一歩引いて全体を見渡す」ようなイメージで行う見守り支援の方法です。
ご利用者さんの「やる気」を引き出す
3つ目は、ご利用者さんの「やる気」を引き出すために見守るケースです。
感じ方は人それぞれですが、「人の目がある」というのは緊張する反面、やる気や安心感につながる要素でもあります。
歩行訓練を例にして考えてみましょう。見守り支援があることで、「歩けるところを見てもらおう」「万が一バランスを崩しても、すぐに助けてくれるから安心して歩ける」と感じてもらえるかもしれません。
その結果、1人で歩くときよりも歩行距離が伸びたり、姿勢が安定するなど、ご利用者さんにとってプラスの効果が期待できます。
ステップ③複数の「見守りの型」を用意する
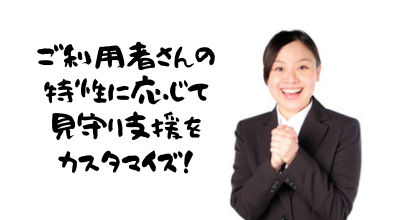
最後に、見守り支援の工夫を3つご紹介します。自分にとっての得意・不得意がわかれば、支援の軸ができるだけでなく、苦手な部分を人に手伝ってもらうなど、チーム全体での支援の幅が広がることに繋がります。
座る位置を変える
後方に位置を取ると支援が上手くいかない場合は、座る位置を横並びに変えるだけでうまくいくことがあります。
あえて視界に入るようにすることで、1人でいる(と感じる)時に、急な行動が起こりやすくなるというご利用者さんに対処しやすくなります。
私の場合、次でご紹介する「何かをしている人」になる方法と併用し、ご利用者さんと同じテーブルで横並びに座るパターンが多いです。
「何かをしている人」になって見守る
何もせずにそこにいられることが苦手と感じるご利用者さんには、あえて「何かをしている人」になって見守り支援をしています。
私の場合、バインダーにコピーの裏紙などを挟んだものを用意しておき、ペンを片手に「書類を書いている人」になることが多いです。
「私も近くで作業させてもらいます」みたいな感じで、さらっと支援に入るのがポイントです。
複数で交代しながら見守る
常時の見守り支援が必要な場合は、複数で交代しながら見守り支援をする方法が有効です。支援者が交代することで視点が変わり、1人では気付けなかった違和感を共有できるといったメリットがあります。
交代するタイミングや、各支援者の得意とする距離感などを事前に共有しておくことで、1人ではできない支援が可能になります。
まとめ
今回は、見守り支援の「苦手」を『得意』に変える。というテーマで、見守り支援上手になるための3つのステップをご紹介しました。
- 「見守り支援」について知ることから始める
- 見守りの距離感に絶対的な形は存在しない
- 「なぜ見守るのか」をはっきりさせることで、ブレない支援の軸を作る
特に働き始めて間もない職員さんにとっては、「ご利用者さんのために」という気持ちが先行して、本来は1人でできる動作まで手伝おうとしてしまうことがあります。
また、見守り支援の大切さが共有されていないと、「働いていない」という間違った評価をされてしまうことも考えられます。
見守り支援は、立派な対人援助スキルの1つです。SNS「note」の『別館・めざせ!福祉マスター』も、ぜひご覧下さい。

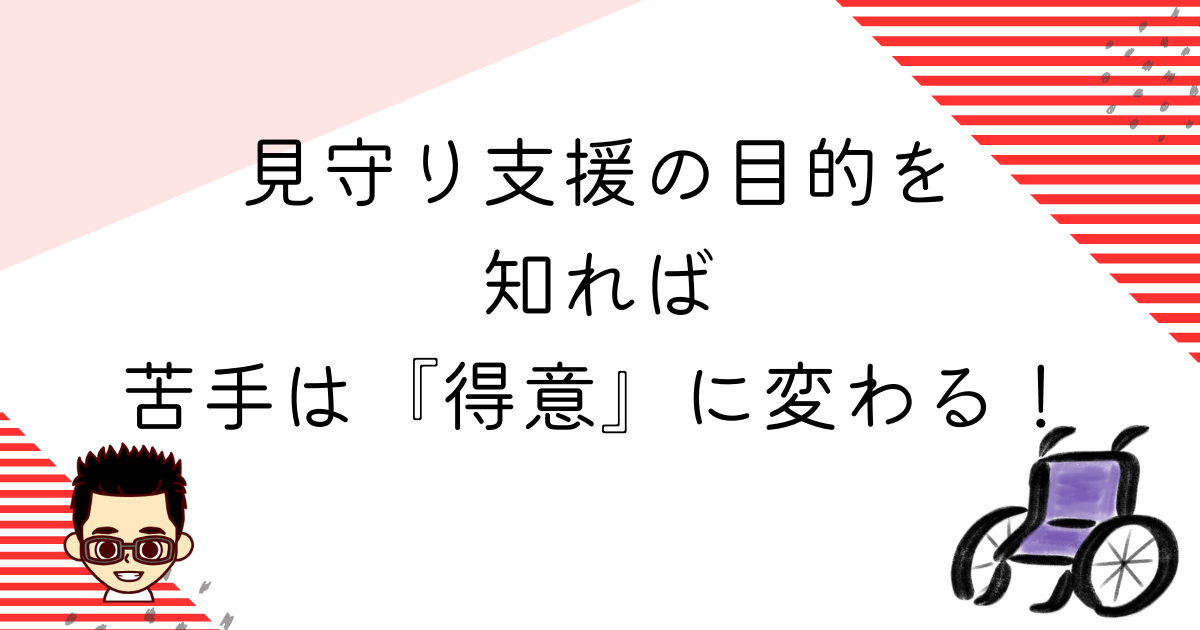


コメント