生活介護事業所の送迎は「ご利用者さんの無事」だけではなく、乗務員である私たち生活支援員も安心して乗車できることが大事ですよね。
雨に降られたとき、急な気分不良があったとき、ちょっとした汚れやにおいが出たとき——焦りが出るのは、たいてい“すぐ使える物”が手元にない瞬間ではないでしょうか。
そこでこの記事では、生活支援陰暦15年の私が、送迎車に常備している5つのアイテムを、具体的な使用シーン付きで紹介します。
小さな備えが、ご利用者さんの安心はもちろん、私達生活支援員の心の余裕も守ってくれます。
【📌現役生活支援員、ほぼ毎日送迎車両を運転している私のプロフィールはこちら】
① カッパ(ポンチョタイプ)
具体的に使うシーン
- にわか雨の乗降
ご利用者さん宅の到着直前に強い通り雨。車いすを利用しているご利用者さんの場合、介助員が傘をさしながら車いすを押すことはできません。
サッと被ってさっと使える。ご利用者さん用と介助員用、2つあると便利です。
② ぞうきん
具体的に使うシーン
- 車いすの泥拭き
車いすの形状によっては、アームレスト(肘置き)の下に、泥よけが付いていないタイプのものがあります。
そのままではご利用者さんの服が汚れてしまうかもしれない。そんな時に使っています。
- 靴底を拭く
ご自分で乗り降りされるご利用者さんにとって、足元が濡れているのは危険。床においたぞうきんを踏んでもらうことで、転倒リスクを少しでも軽減するようにしています。
雨の日、車から降りた瞬間に足をすべらせてしまったご利用者さんがいました。その時の経験を活かし、導入しました。
③ポリエチレンの手袋
具体的に使うシーン
- 嘔吐などで、床や座席が汚れてしまった時の緊急対応
送迎時の緊急対応で最も大変だなと感じるのが、嘔吐などの処置です。咄嗟に「なんとかしなければ」と素手で触ってしまうのはNG。
2次汚染を予防する意味で、交換用に2〜3双あると安心です。
④ビニール袋(不透明)
具体的に使うシーン
- エチケット袋として
私の職場には、雷がなると恐怖感で嘔吐してしまうご利用者さんがいるため、ほぼ必須アイテムです。
- 汚れ物の一時隔離
不透明の袋を使うことで、ご利用者さんのプライバシーへの配慮と心理的な負担軽減になります。
- 座席の簡易防水シートとして
障害特性によっては、「どうしてもこの座席に座らなければならない」と考えてしまうタイプのご利用者さんがいます。
どうしても席の移動が難しい場合は、ビニール袋を座席に敷いて対応しています。本来であれば席を移動することが望ましいのですが、それができない時が大変だなと感じます。
⑤おしぼり(不織布)
具体的に使うシーン
- 拭き取り
ティッシュよりも水に強いので、対応できる場所が多いのが強みです。個包装タイプを、業務スーパーなどでまとめ買いすれば、コストカットと予備の用意が同時にできます。
置き場所の工夫

これらのアイテムの置き場所は、「運転手と介助員、どちらが使うか」を基準に考えるのがおすすめです。
さらに、「〇〇さんにはビニール袋をよく使う」など、ご利用者さんごとの利用シーンを考えて配置を工夫するのも効果的。
たとえば「突発的な体調不良が起きやすい=準備をしておけば安心できる」とリフレーミングして考えると、ただの備えもその人の強みを支える工夫になります。
まとめ
ちょっとした工夫で、雨・汚れ・体調不良・衛生管理といった送迎の“よくある想定外”に強くなれます。
そして何より、ちょっとした工夫があれば、本来なら“対応不能な想定外”になりそうな出来事も、“よくある想定外”に変えていけます。
ご利用者さんの顔ぶれを思い浮かべながら、あなたの現場に合わせて、安心して動ける送迎環境ををつくっていきましょう。
【生活支援員のための送迎ガイド】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


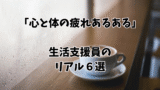
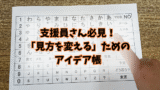
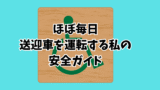


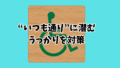
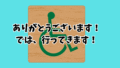
コメント