📌【まなレクについて知りたい人はこちら】
生活支援員として働いていて、「自分の強みってなんだろう?」と悩んだことはありませんか?
トイレ介助や食事介助のスキルだけでなく、
「車に詳しい」「ピアノが弾ける」「趣味で演劇をやっている」など、あなたならではの強みがあるなら、まなレクで大きく活かせるチャンスかもしれません。
- レクに学びの要素って本当に必要?
- ご利用者さんにとって難しすぎない?
- 専門知識がないとできない?
そんな不安を持っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
私自身の経験から、「まなレクが支援員の強みを活かす場になる」理由をお伝えしていきます。
【📌小学校の教員免許を活かして”まなレク”を実践している私のプロフィールはこちら】
まなレクとは?
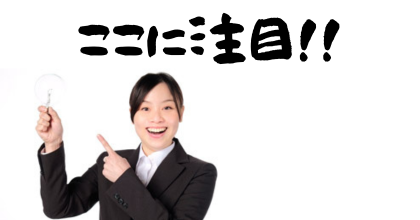
まなレクは、「学び × レクリエーション」という意味の造語です。
「学び」と聞くと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、実はとても柔軟な考え方。
私は、以下の3つの感覚を大切にしています。
W・I・Nの法則
- W(わかった!)…理解する喜び
- I(いいね!)…共感する楽しさ
- N(なぜ?)…疑問が生まれる面白さ
この3つがあれば、十分“学び”として成立します。難しく考えず、まずは「ちょっと知的な楽しみ時間」から始めてみませんか?
ご利用者さんの反応がこう変わった!
①引っ込み思案だったAさんが、「わかった!」という笑顔を返してくれるようになった
②いいね!をしっかり返していたら、意見がたくさん出るようになった
③Cさんが、まなレクの時間以外にも、「なぜ年賀状にはお年玉がついているんですか?」と話しかけてくれるようになった
まだまだたくさんありますが、W・I・Nポイントを意識するようになって、良い変化がたくさんありました。
まなレクのメリット・デメリット
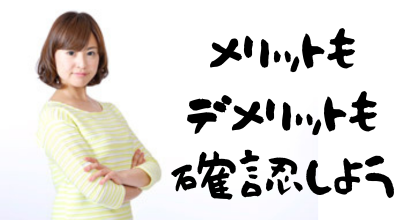
メリット
① ご利用者さんの経験値が増える
障害特性の関係で、経験が限定されがちな方もいます。
まなレクは、新しい「体験」や「興味の芽」を育てるチャンスになります。
② 『強み』の発見につながる
ご利用者さんの「好き」「得意」が見つかると、日中活動全体に良い循環が生まれます。
「え? 〇〇さん裁縫が得意だったの!?」という、意外な一面が見えることも!
③ 他の活動ともつながる
たとえば「絵画を体験するまなレク」から、創作活動や余暇活動へと発展させることも可能。
“個別支援”にもつなげやすくなります。
デメリット
心理的ハードルが高くなりがち
「学び」と聞くと、つい「きちんとやらなきゃ」と構えてしまうことも。
気軽に楽しめる雰囲気づくりを意識すると◎
場合によっては外部講師の力を借りてもOK!
継続しづらい
一回限りの企画で終わってしまうこともあります。
音楽や工芸など、継続しやすいテーマ選びがおすすめ。
思い切って「単発でもOK」と割り切るのも一つの方法です。
集団が苦手な方には不向きな場合も
全員参加が難しいケースもあります。
そんな時は、1対1の個別活動にアレンジして無理なく取り組みましょう。
アナタの『強み』が、まなレクになる
一番の魅力は、職員の「強み」がそのまままなレクになるということ。
たとえばあなたがピアノを弾けるなら——
- 「ドレミについて学ぼう」
- 「楽譜を読んでみよう」
- 「オリジナルソングを作ろう」
…というテーマでまなレクが展開できます。
例:「ドレミについて学ぼう」のW・I・N
- W(わかった!) 音の高さが鍵盤の位置で違う!
- I(いいね!) ピアノの音って気持ちいい!
- N(なぜ?) なぜ右に行くと音が高くなるの? 他の楽器と何が違う?
無理にすべての要素を詰め込む必要はありません。
大事なのは、ご利用者さんの理解度や反応に合わせながら、楽しみの中に「学びのタネ」をまくこと。
まとめ:強みは「支援スキル」だけじゃない!
- 介助スキル以外の「趣味」や「経験」も立派な武器
- W・I・Nで、学びのある時間に早変わり
- “自分らしさ”を活かすレクが、ご利用者さんの笑顔につながる
まなレクを導入している施設は、まだまだ少数派。
だからこそ、支援に一工夫を加えることで、あなたの魅力をもっと発揮できるはずです。
「学びってなんか難しそう…」という思い込みを手放して、
ご利用者さんと一緒に、新しい時間のカタチをつくってみませんか?
【まなレク:準備】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、小学校第1種教員免許を持っています。今でも月に10回ほど、まなレクを企画・実践しています。
私がまなレクで大事にしているのは、ご利用者さんの「わかった!(W)」「いいね!(I)」「なぜ?(N)」を引き出す『W・I・Nポイント』
ありがたいことに、ご利用者さんから「説明が上手」「言葉選びがうまい」と評判を頂いており、それが私の日々の励みになっています。





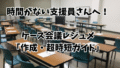

コメント