ある日の生活介護事業所。ぽつんと1人で座っているご利用者さんに、「一緒にレクリエーションに参加しますか?」と聞いたところ、
「レクをしたいけど、みんなでやるのは苦手」
という返事が返ってきました。これは生活支援員として15年ほど働いている私の実体験です。
そんなとき、どんな選択肢があるのでしょう?
この記事では、「集団がちょっと苦手」「にぎやかな空間が疲れる」という方にもフィットしやすい活動を5つご紹介します。
【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】
☑まずは、「苦手」の中身に目を向けよう
一口に「集団が苦手」といっても、その感じ方は人それぞれ。
以下のような背景があるかもしれません。
🌀 静かな空間のほうが落ち着く
感覚や聴覚に過敏がある方にとって、複数人でにぎやかに行う活動は刺激が強すぎる場合があります。
感覚過敏について詳しく知りたい人は、こちらの記事がとてもわかりやすかったです👇️
👉️感覚過敏の症状や原因、対処法、発達障害との関連性についてマンガで解説(BRAIN CLINIC)
🧩 人との関わりに不安がある
「うまく話せなかったらどうしよう」「失敗したら…」という不安から、集団での活動を避けてしまう方もいます。
💭 マイペースに過ごしたい
自分のペースで楽しみたいという気持ちが強く、相手のペースに合わせるのが苦手な方もいます。
特にASDのあるご利用者さんの場合、自分のルーティンが強くインプットされていて、集団での活動が苦手な場合があります。
ASDについては、こちらの記事が非常に参考になります👇️
👉️大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴は?(スマイルクリニック イムス東京)
「一人でも」「少人数でも」できる!おすすめアクティビティ5選
📚 読書タイム|静かな集中の時間を
本の世界にひたる時間は、気持ちを落ち着かせる力があります。
読み終わったあとに、希望する方だけで感想を共有してもOK。強制しない「ゆるやかなつながり」も生まれます。
読書がもたらすメリットについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください👇️
👉️読書が脳にもたらす効果とは?(STUDY HACKER)
🎸 音楽(演奏)|個別でも、セッションでも
音楽と聞くと集団での活動をイメージすることが多いですが、楽器の演奏を楽しむ“ひとり音楽タイム”もおすすめ。
音の出し方に正解がないので、自己表現としても◎。慣れてきたら少人数でのセッションに進んでも発展がありますよ。
🎬 映画鑑賞|“共有しなくても楽しめる”空間
音楽と同じく集団での活動、というイメージが強い映画ですが、じつは同じ空間で同じ映像を見ていても、「誰とも話さなくていい個別の活動」という側面もあるんです。
そんな「一体感と自由さ」が共存する活動。照明や座席の配置を工夫すれば、より安心できる時間になります。
🎤 一人カラオケ(ソロカラ)|マイペースに声を出す
カラオケ=みんなでワイワイ、だけじゃありません。
ひとりで歌う、職員とデュエットする、2〜3人で実施…など、形を工夫すればニーズに合わせて無理なく楽しめます。
🎲 ボードゲーム・カードゲーム|1対1からスタートできる交流
UNOやトランプなど、少人数でじっくり遊べるものは、距離の取り方がちょうどいいので、私が特におすすめしている活動です。
「勝っても負けても楽しいと思える雰囲気づくり」が続けやすさのポイントです。
私の実践例2選!
事例①:カラオケが好きだけど待つことが苦手なAさん
Aさんは、ASDの傾向が強く、「どれくらい待つのか」という見通しが持てないことに強い不安があります。反面、歌を歌っているときには笑顔が見られます。
実践:参加するご利用者さんに了解を得て、Aさんに1番最初に歌ってもらうことにした。歌った後は自分のしたいことをしてもらい、他の参加者でカラオケを続ける。(もしAさんが「歌を聞きたい」と思ったらそれももちろんOK)
⇒個別の活動と、集団での活動のハイブリッド作戦!
事例②:集団では本音が話せないBさん
Bさんは、人に見られていると思うと緊張が強くなってしまうタイプです。レクリエーションには参加するものの、自分から何かを話してくれることはありません。
実践:読書の時間を設定し、私も一緒に読むことにした。緊張しないよう、横並びに座ったことで、自分の思っていることを話してくれる機会が増えた。
⇒「同じ空間にいるけど、それぞれ別の時間を過ごしている」という安心感を持ってもらえた!
ご利用者さんに本音で話してもらえない、とお悩みのアナタには、こちらの記事もおすすめです👇️
まとめ|大切なのは、「やってみたい」に寄り添うこと
ご利用者さんが「何かやってみたい」という気持ちはとても尊いもの。それは、集団生活が得意であっても苦手であっても関係ありません。
無理に参加を勧めるのではなく、その気持ちを尊重して、「ひとりで」「少人数で」できる選択肢をそっと差し出す。
その積み重ねが、信頼にもつながっていきます。
もし、施設全体でできるイベントのネタにお困りでしたら、こちらの記事でネタの”ストックスキル”を身につけてはいかがでしょうか。
【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


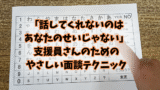
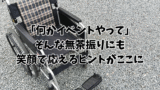



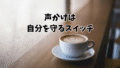
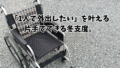
コメント