「一人前の生活支援員って、どこからなんだろう?」
これは、生活介護事業所で働きはじめて半年くらい経ったころの私の悩みです。
先輩に聞かずに動けたら? 1年経ったら? 自分の感覚で決めるの?
今回は、現場歴15年の実践経験から見つけた、私の「新人から一人前になる基準」についてお話しします。
【📌現場歴15年、このブログを書いている私のプロフィールはこちら】
結論:一人前の基準は「教えられるようになること」
私が新人職員さんの研修を担当する時、「人に教えられるようになったら一人前です」と伝えています。自分の中に支援の軸ができることが、新人から一歩進んだサインと考えているからです。
もし、あなたが新人さんを指導する立場になったときは、「新人さん自身の言葉で説明できるか」をチェックしてあげると良いですよ
なぜ「教えられる」ことが一人前?
人に説明しようとすると、わかっている部分だけでなく、曖昧な部分もはっきりします。言葉で伝えられるようになったということは、知識や技術が自分の中に定着している証拠です。
私の体験談:後輩に教えた日の気づき
私が今の生活介護事業所に勤め始めて、3年目のことです。その時後輩に「送迎車の車いすの固定ってどうやるんですか?」と聞かれました。
その時私は、車いすの固定方法だけでなく、「なぜ他の方法ではダメなのか」「どこにキケンな因子が潜んでいるか」を説明することができました。
その後も、砂利道での車いすの押し方や坂道での対応を聞かれて、見本を見せながら説明できたときに、「少しずつ一人前に近づいてる」と感じたのを覚えています。
砂利道での車いすの押し方に興味がある人はこちらの記事も読んでみてください👇️
「教える相手がいない場合は?」
自分自身が一番後輩で、教える相手がいないこともあるかもしれません。でも大丈夫、そんなときは”誰かを想像して説明してみる”方法がおすすめです。
私は、通勤中の車内で「1年目の後輩」を意識して、やり方を声に出しています。
実習生の受け入れも成長のチャンス
生活介護事業所に限らず、福祉施設では実習生を受け入れることがあります。もし、実習生を担当する機会があれば、自分の成長を実感できます。
現場に出るのが初めてという実習生さんの場合、特に”専門用語を分かりやすく言い換える力”が問われるので、普段から専門用語の言い換え方を練習しておくのもおすすめです。
「全部理解していないとダメ?」
ここまで読んでくださった人の中には、「結局全部知ってないと一人前じゃないのか」と思われた人もいるかも知れません。でも、すべてを完璧にできる必要はないんです
福祉の現場では、すべてを一人で完璧にできる人はいません。むしろ、自分の苦手なことやわからないことを知ったうえで対応するのも、立派なスキルの1つと言えます。
ちなみに私は、ご利用者さんの悩みを言語化するのが得意ですが、テンションをガンガン上げていくイベントの企画や進行が苦手です。
私の実践:その分野の「エース」を見つける
「むせにくい食事介助は○○さんを参考にすると良い」
「ボディメカニクスは△△さんの説明がわかりやすい」など、
生活支援員の仕事はチームで取り組むもの。だからこそ私は、その分野のエースを見つけるようにしています。
もし、あなた自信がどれか一つでも「これは私に任せて」と言える分野を持てたら、それはもうベテランの入り口です。
ちなみに、私の場合はレジュメの書き方を人に教えられるようになったとき、「自分の得意分野ができたな」と思えました。
まとめ:成長のサインは「伝えられることが増えた」とき
新人さんの多くは「一人で全部できるのが一人前」と思いがちですが、人に教えられることが増えることこそ、成長の証です。
焦らず、今日できたことを誰かに伝えられる日を楽しみに、一歩ずつ積み重ねていきましょう。
【新人さんのためのスタートブック(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
新人さんや実習生の受け入れを担当した際には、「わからない人の視点でアドバイスをしてくれるのが助かる」と高評価を頂いています。
スキルアップだけでなく、セルフケアにも関心があり、同じ現場で働く仲間が、少しでも長くこの仕事を続けられるようにという思いを込めてブログを運営しています。

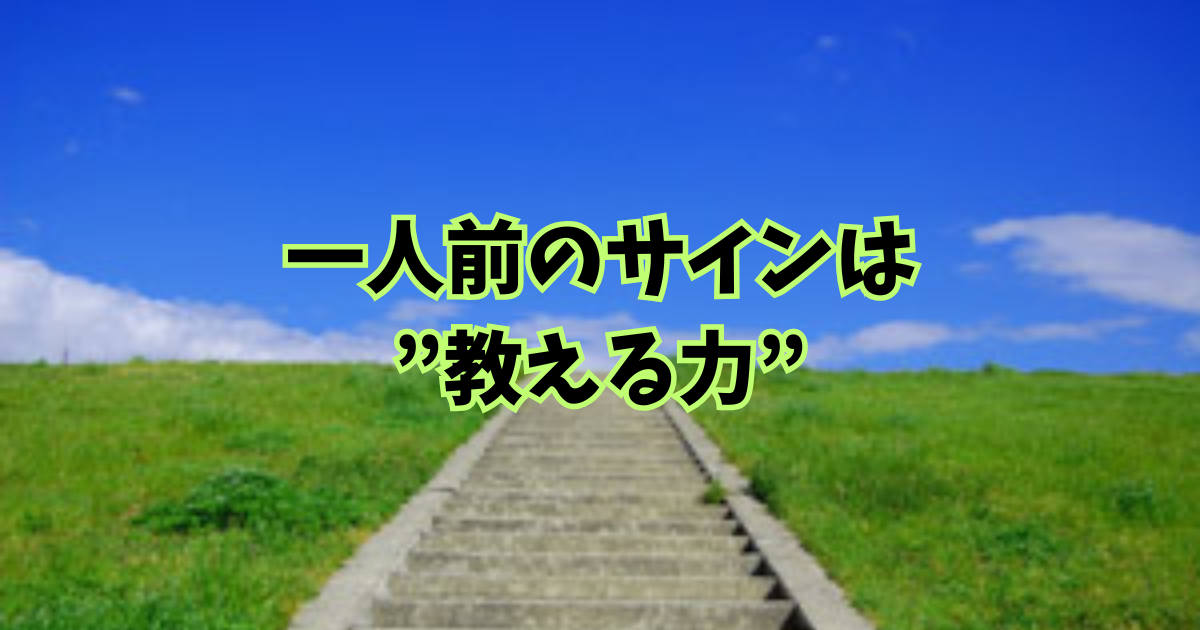
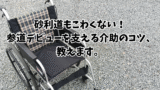

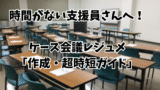
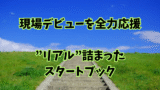


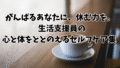
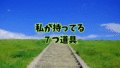
コメント