生活支援員の仕事は、トイレや着替えの介助など、直接的なケアだけではありません。
毎日のケース記録や個別支援計画など、「書く仕事」も実は多いですよね。
けれど…
- どう書いたらいいかわからない
- 言葉選びで不快にさせたくない
- 書類に時間がかかってしまい、支援に集中できない
こんな悩み、ありませんか?
特に多いのが「できないことばかり書かれてしまう」というお悩み。私も最初は「〇〇できない」ばかり書かれた書類を作っていた時期があります。
今回は、その経験を活かしてたどり着いた “できる”が伝わる言葉に変えるコツ をお伝えします。
【📌デスクワークの効率化も、現場の業務も大事にしている私のプロフィールはこちら】
🟠【まずは】書類の基本は“心構え”から

完璧を目指しすぎなくてOK。
書類は「正しく伝えること」が一番大事。
そして何より、ご利用者さんへのリスペクトがにじむ書き方がベストです。
「この人はサポートがないとできない」ではなく、
「サポートがあればできる人」と捉えるだけで、文章全体の雰囲気が変わります。
捉え方を変えるリフレーミングについて知りたい方は、こちらの記事をどうぞ👇️
🟠【次に】誰に読まれる?によって言葉を使い分けよう

書類は「読む相手」によって書き方を変えるのがコツ。この一手間で、あなたの書類の好感度がアップします。
| 書類の種類 | 想定読者 | 書き方のポイント |
|---|---|---|
| ケース会議資料、記録 | 関係者のみ | 専門用語で簡潔に |
| 支援計画など | ご本人・家族・関係者 | 専門用語+簡単な説明 |
| 連絡ノートなど | 家族のみ | わかりやすい表現を重視 |
🟠【注意】言葉づかいに気をつけたい表現たち
以下のような言葉、無意識に使っていませんか? これらを見直すだけで、印象がぐっと良くなります。
| NG表現 | こんな言い換えで印象UP! |
|---|---|
| 「~させる」「〜を促す」 | 「~を提案する」「~を勧める」 |
| 「〇〇できない」 | 「サポートがあれば〇〇できる」 |
| 「パニック」 | 「大きな声を出してしまう」「自分の頭を叩いてしまう」 ※どんな状況なのかを書く |
| 「完璧」 | 「時間内に作業を終えることができる」「不良品を出さない」 ※何に対する評価なのかを言葉にする |
大切なのは、支援者の主観ではなく事実ベースで書くこと。
ネガティブに見える言葉も、ちょっとした言い換えで印象が柔らかくなります。
ケース記録のNGワードについて詳しく知りたい人は、こちらの記事がとても参考になります。「介護記録」を「ケース記録」に置き換えながら読むとわかりやすいですよ👇️
👉️介護記録で使っていけない言葉とは?言い換え表現も解説(レバウェル介護)
🟠【実例あり】「できない」→『できる』に変えるには?
✅NG例
「ひとりではできない」
✅GOOD例
「職員の声かけにより、ご本人のペースで取り組むことができる」
“できない”で終わらせず、「支援によってどう変わるか」をセットで書くと、ご利用者さんをよりリアルにイメージすることができます。
実際にこの表現を使っていて、後輩から「こうやって書けば良いんですね」という気付きを持ってもらえた経験が、とても印象に残っています。
🟠【小ワザ】読みやすい構成を意識しよう
- サンドイッチ作戦
(①ポジティブ → ②改善点 → ③ポジティブ)で書くと印象◎
例:「ウォーキングに行きたい」と伝えてくれました。途中、「疲れた」と言って座り込んでしまいましたが、5分ほど休憩してから最後まで歩くことができました。
- 「できる」言葉を最初と最後に入れる
読み手の記憶に残るのは“最初と最後”。前後に良い印象をもってもらえる構成にしましょう。
言葉の選び方ひとつで、伝わる印象は大きく変わります。こうした表現力が身につくと、レジュメやおたよりなどの資料作成にも“自然なやさしさ”がにじみ出るようになります。
✔まとめ
「できないこと」をそのまま書くのではなく、
「どんな支援があれば、どう“できる”か」を書く。
それだけで、書類の印象もご本人の評価も、ガラッと変わります。
大切なのは、「どんな心で接するか」だと考えています。ご利用者さんへのリスペクトがあふれる書類が書けるようになれば、”区分認定調査に同席するとき”や、”施設見学の受け入れを担当するとき”などにも活かすことができます。
【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年の現役生活支援員で、ケアマネージャーの資格を持っています。
わかりやすい言い換えや、書類のやさしい言葉選びが得意で、ありがたいことに「今さら聞けない疑問なんですが」と、同僚や後輩だけでなく、先輩から声をかけてもらえることもあります。
デスクワークでは、毎日のケース記録の記入から個別支援計画の作成業務まで、幅広くこなしています。
ケース記録や個別支援計画などについて深堀りしたい人は、こちらの記事がわかりやすくておすすめです👇️

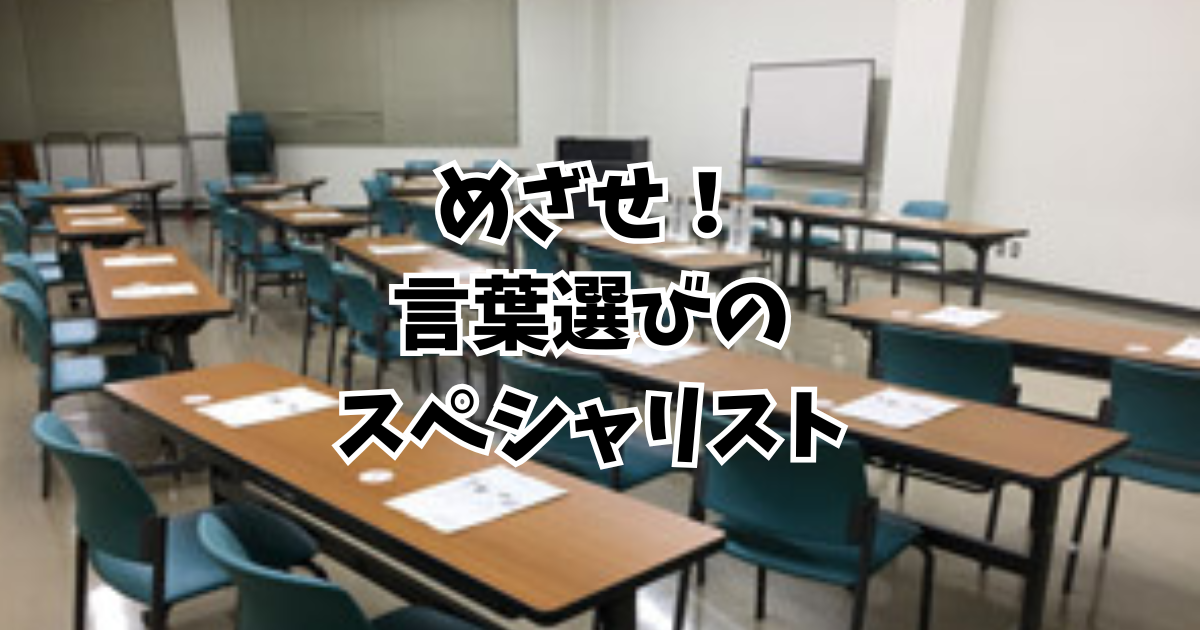
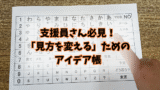
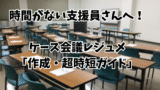
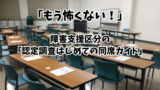
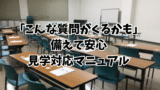
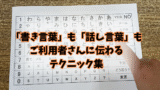


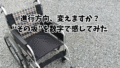

コメント