まなレクとは、“学び”の要素を取り入れたレクリエーションの造語です。
学びは生きる力になるをテーマに、ちょっと知的な時間づくりを目指しています。
生活介護事業所における日中活動は、年々その重要性を増しています。私自身も、現場で「学び」に対するご利用者さんの関心の高さを日々実感しています。
とはいえ…
- 新人職員でもできるテーマってある?
- ご利用者さんが楽しめるジャンルって何?
- メリット・デメリットも事前に知っておきたい…
そんな支援員さんの声にお応えして、今回は実際に私が担当している中でも「特に始めやすく、人気も高い」まなレクのジャンルをご紹介します。
【📌小学校の教員免許を活かして”まなレク”を実践している私のプロフィールはこちら】
「学び」は生きる力になる
長年、現場でまなレクを行ってきて思うのは、ご利用者さんが「わかった!」と笑顔を見せてくれる瞬間の尊さです。
行動範囲が限られたり、サポート情報が少なかったり。障害のある方が“経験”を積みにくい現実は確かにあります。でも、「知ることが楽しい」「学ぶことに自信がつく」――そんな積み重ねが、自分らしく生きる力になります。
皆さんの得意を活かすまなレクについての記事も書いていますので、興味がある人はぜひご覧下さい👇️
まなレクにおすすめの「〇〇系」講座2選
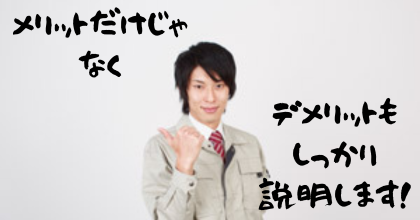
私はこれまで約10種類のまなレクを担当してきました。その中でも特におすすめしたいジャンルが、以下の2つです。
- 国語(ことば)系
- 算数系
どちらも「取り組みやすさ」と「応用のしやすさ」が魅力。それぞれの特徴を、メリットとデメリットを交えて紹介していきます。
国語(ことば)系講座
✅メリット
- 年中行事を題材にできる
例:七夕の由来、日本と世界の星祭りの比較など - 他ジャンルへの発展がしやすい
例:年賀状→手紙の歴史→日本史・世界史へ - 個別支援計画との連動がしやすい
例:語彙を増やすゲーム→「気持ちを言葉にする」支援へ
個別支援計画について知りたい方は、こちらの記事がわかりやすくて参考になります👇️
👉️個別支援計画とは?作成の流れやルールをわかりやすく解説(LITALICO)
⚠デメリット
- 学校っぽさが苦手な方にはハードルが高い
→「名前を変える」「まずは見学から」の工夫で対応可能 - ある程度の事前準備が必要
→「分からないことは一緒に調べる」もアリ - ホワイトボードがほぼ必須
→小さなボードを複数用意するなどで代用可能
算数系講座
✅メリット
- 日常生活に直結しやすい
例:時計の読み方、お金の使い方、「半分」や「3等分」の概念 - 「なぜ?」から入れる
例:「1×0=0なのはなぜ?」「奇数・偶数って何?」 - 結果を“見える化”しやすい
例:折り紙の重さを測る、素数を見つける、図形を切り分ける
※デメリットは国語系と共通のため省略
まとめ|「難しい」より「楽しい」から始めよう

国語・算数というと、どうしても「学校っぽさ」や「教える側の負担」が気になるかもしれません。でも、大切なのは「どうすれば楽しく学んでもらえるか」という視点です。
- 講座時間は15分程度でもOK
- 複数の職員でチームを組んでもOK
- 完璧じゃなくてOK、一緒に調べていけばいい
ご利用者さんが「わかった!」「もっと知りたい!」と目を輝かせる瞬間は、まなレクならではの喜びです。あなたの支援が、学びの第一歩になりますように。
【まなレク:準備】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、小学校第1種教員免許を持っています。今でも月に10回ほど、まなレクを企画・実践しています。
私がまなレクで大事にしているのは、ご利用者さんの「わかった!(W)」「いいね!(I)」「なぜ?(N)」を引き出す『W・I・Nポイント』
ありがたいことに、ご利用者さんから「説明が上手」「言葉選びがうまい」と評判を頂いており、それが私の日々の励みになっています。








コメント