掃除や整理整頓というと、「きれいに保つこと」「衛生的にすること」というイメージが強いのではないでしょうか。
でも、生活介護事業所の現場ではそれだけではありません。
私が勤めている生活介護事業所には、決められた場所に物がないと、落ち着かなくなってしまうタイプのご利用者さんがいます。
この記事では、生活支援員歴15年の私が、”整理整頓の持つ支援としての側面”をご紹介します。
【📌現場歴15年!掃除は”働きやすさにつながる”と思っている私のプロフィールはコチラ】
実は身近な”構造化”
構造化とは、簡単に言うと「パッと見て何をすればいいかわかりやすくすること」です。
スーパーのレジの前に、間隔をあけて並んでもらえるように、テープなどが貼られているのを見たことがある人も多いかもしれません。
あれは、「ここに並んで下さい」ということがパッと見てわかると思います。これが構造化です。思った以上に、私たちの身近にあるので、よければ探してみて下さい。
構造化については、こちらのサイトがとてもわかり易かったです。児童発達支援の視点でまとめられていますが、私は大人のご利用者さんに当てはめて読みました👇️
👉️「構造化」とは?方法や種類、メリットなどを分かりやすく解説します(そらまめキッズ)
例:気持ちが逸れてしまいやすいAさん
Aさんは、「今から何をするのか」をしっかりとインプットできれば、自分でその場所まで移動することができます。反面、気になるものが目に入ると、途中で気持ちが逸れてしまいます。
例えば、音楽の活動のために別棟に移動するとして、移動の途中で机の上に新聞がおいてあると、つい手にとって読み始めてしまい、移動することを忘れてしまいます。
もし、机の上が整理整頓されていれば、Aさんは気持ちが逸れることなく、次の活動に移ることができます。つまり、整理整頓はAさんにとって「次の活動に移るための支援」になります。
整理整頓がもたらす3つの構造化効果
① 見通しが立つ
「この棚にはタオル」「このカゴには洗濯ばさみ」と決まっていれば、どこに何があるか一目でわかります。
そして、それぞれどの順番で使うか、写真やイラストで示すことで、活動の流れもつかみやすくなります。その活動の流れを円滑にするのが整理整頓です。
② 刺激を減らす
視覚情報が多すぎると疲れてしまう人にとっては、整理整頓には、「情報量をコントロールする」という意味もあります。
必要なものだけが目に入るように整理することで、選択肢がシンプルになり、混乱してしまうことが少なくなる、という強みにアプローチすることができます。
③ やる気を引き出す
施設全体で整理整頓が習慣づくことで、ご利用者さん自身にも「どこに何があるか」がわかりやすくなります。
「自分でやってみたい」、「誰かの役に立ちたい」という希望があるご利用者さんにとっては、”自分で片付けてみよう”というやる気スイッチを押すきっかけになります。
掃除や整理整頓を“支援”として捉えるコツ
整理整頓を「支援」として見るためのコツは、「きれいにしたい」だけではなく、「わかりやすくしたい」と考えること。
ただ片付けるだけでなく、どこに何があるかを可視化するのも良い方法です。
- ラベルをつける(文字+イラストで)
- どうしても気になるものは布などで隠す
- 片づける流れを写真で掲示
こうした工夫は、どれも立派な構造化支援です。最大効率を求めるのではなく、時には「多少手間でも、ご利用者さんの手の届かない所に片付ける」といった、柔軟な対応がポイントです。
整理整頓からは少し離れてしまいますが、あるご利用者さんのために、送迎車に足型のシールを貼り、”足を置く場所”を伝える支援を実施しています。
送迎についてはコチラのカテゴリの記事をご覧ください。
無理なく続けるために
掃除や整理整頓は、少しの汚れや乱れがない状態を目指すと疲れてしまいます。大切なのは、”現場の状況”と”現実的にできる範囲”のベストバランス。
誰かひとりが気を張るのではなく、時にはご利用者さんと一緒に、みんなで少しずつ気を配り合っていくことが、長続きのポイントです。
それと同じくらい大切なのが、”仕事と暮らしのベストバランス”。ご利用者さんの笑顔のために、生活支援員であるあなた自身をいたわってあげて下さいね。
まとめ:正解は1つではない
掃除や整理整頓を、”単なる片付け”ではなく、”支援の一部”として捉える。このように、捉え方を変えることを「リフレーミング」と言います。
「見える化(構造化)支援」と一口に言っても、施設に通ってくれているご利用者さんの顔ぶれによって、必要な支援は変わります。
大切なことは「ただ片付ける」のではなく、「どうすればわかりやすくなるか」という視点をプラスすること。
できることから少しずつ、「見通しがつきやすい」整理整頓を始めてみませんか?
【生活支援員のための掃除テクニック】のカテゴリは現在準備中です。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利掃除はご利用者さんのためだけではなく、私達自身の働きやすさにもつながると考え、様々な掃除のアイデアを実践しています。
現場の業務と同じくらい大切なのが、自分自身をいたわるセルフケア。”目指せ福祉マスター”では、仕事と暮らしのベストバランスを応援しています。


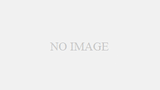
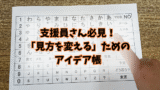


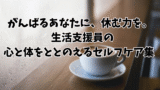
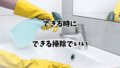
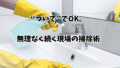
コメント