特別支援学校の卒業を間近に控えた保護者のみなさん、お子さんの卒業後の進路は決まりましたか? 今回は「生活介護事業所」の利用を検討されているアナタに向けての記事です。
- 難しい単語が多くて「理解しよう」という気持ちにブレーキがかかってしまう
- どの施設も名前が違うだけで中身は一緒なんじゃない?
- 利用できる対象が限られてるって聞いたけどホント?
今回は「実際に生活介護事業所で働いている中の人」という立場で、生活介護事業所とはどんな施設なのかについてご説明します。前半は「生活介護事業所とは何か」、後半は「生活介護事業所でできること」について書いていきます。
この記事は

・わかりやすい解説を聞きたい人
・生活介護事業所について知りたい人
・お子さんの卒業後の進路を決めかねている保護者さん
におすすめです。
生活介護事業所とは
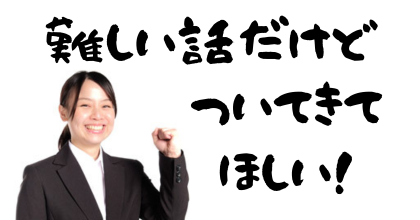
まずは、制度面で生活介護事業所について見ていきましょう。厚生労働省のサイトから必要な項目を引用させて頂きます。
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
引用:厚生労働省、「障害福祉サービスについて」
引用しておいて失礼かもしれませんが、「…難しっ!」ってなるの私だけですかね?
3つのポイントに分け、わかりやすい言葉に置き換えながら確認していきましょう
ポイント① 「常時介護を要するものにつき」
「常時介護」と聞くと、寝たきりの状態をイメージされるかもしれませんが、そうとは限りません。
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要するとありますので、
お風呂やトイレ、ご飯を食べる事への手助けの他に、絵を描いたり文章を書くといった活動や、仕事について常に手助けが必要な人、と考えることができます。
ポイント② 「主として昼間において」
生活介護事業所は、「通うタイプの施設」です。「通所」「通所系サービス」という言葉が使われます。
後述しますが、「どこから通うのか」については書かれていないのがポイントです。
ポイント③ 「入浴、排せつ及び(以下略)
後半部分は、「生活介護事業所として出来ること」が書いてあります。
お風呂やトイレ、ご飯を食べる事への手助けや、家事なども含めた生活上必要なアドバイス、絵を描いたり文章を書くといった活動や、仕事の機会などを提供することで、身体の機能や生活する力を伸ばすための支援をします
と言った内容が書かれているわけです。つまり、「生活介護事業所」をものすごく簡単にいうと、
日常生活にサポートが必要な障害のある人が、生活面での支援を受けながら日中過ごす場所
ということになります。
Q&A形式で疑問にお答えします
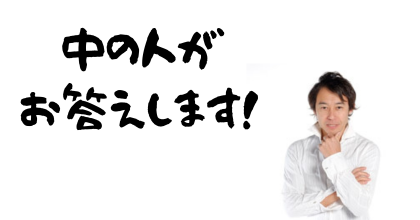
さあ、この記事もいよいよ後半です。ここからはQ&A形式で、アナタの疑問にお答えします。アナタの疑問、と書いていますが、私自身もわからなかったことや、実際に質問されたことをまとめています。
Q、誰でも利用できるの?
A、いいえ、生活介護事業所を利用できる対象者は以下のとおりです。厚生労働省のサイトより、必要な項目を引用させていただきます。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
引用:厚生労働省、「障害福祉サービスについて」
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
少し難しく感じるかもしれませんが、ご自分ですべて判断しなくても大丈夫です。
市町村の窓口で申請し、区分認定調査を受けるところからスタートします。お子さん(あるいはご本人さん)が生活介護事業所を利用できるかどうかは、その結果次第ということになります
Q、グループホームから生活介護に通えるの?
A、はい、通えます。実際に、私が勤めている生活介護事業所でも、日中は生活介護事業所で過ごし、夜はグループホーム(共同生活援助)で過ごしているご利用者さんがいます。
もちろん、家から通うこともできます。「ポイント②」で、どこから通うかについて書かれていなかったのはこのためです。
Q、どんなサポートをしてくれるの?
A、ご利用者さん1人ひとりに作られる「個別支援計画」に沿って、「いつ、どこで、誰が、どんな」支援をするのかが決まります。
支援と聞くと、「苦手なことを出来るように」というイメージを持たれるかもしれません。ですが、私が通っている生活介護事業所には、「得意なことをどんどん伸ばしたい」という要望を出してくれるご利用者さんが何人もいらっしゃいます。
Q、活動内容はどの施設でも同じなの?
A、いいえ。施設によって特色が全く異なります。
中の人として、生活介護事業所を選ぶポイントの1つが、施設の特色だと感じています。
あくまでも一例ですが、
- 絵を書くためのアトリエスペースがある
- 農作業に特化している
- 特殊浴槽を完備し、入浴支援に強い
- 調理場が広く、料理に関する支援が得意
など、ご利用者さんに満足してもらうためのアクティビティが充実していたり、設備面で他の施設にはない特色を備えた施設がたくさんあります。
自宅からの通いやすさももちろんですが、日中活動の充実という視点で、相性の合う施設を探すことも重要です。
Q、高等部在籍中に施設見学はできる?
A、可能です。日程調整等の必要はありますが、できるだけ多くの施設を見学することで、相性の良い施設と出会える確率が上がります。
見学時にチェックしていただきたいポイントをまとめた記事も是非読んでください。
⇒【関連記事】『「中の人」が語る:生活介護事業所の施設見学でチェックするべきポイント5つ』
まとめ
今回は、生活介護事業所とは何か? というテーマで、「制度の説明」や、「生活介護事業所で出来ること」などについて書いてきました。
- 生活介護事業所は、ご利用者さんにとっての「日中の居場所」
- 生活介護事業所は、誰でも利用できるわけではない
- 施設見学で相性の良い施設を探そう
卒業後の進路について、不安に思うことがたくさんあるかもしれません。日々の介護の合間に大変かと思いますが、卒業後の施設選びをしっかりと行うことで、「こんな施設だとは思わなかった」というギャップを感じることを軽減できます。
卒業されるお子さんが、素敵な施設と出会えますように。

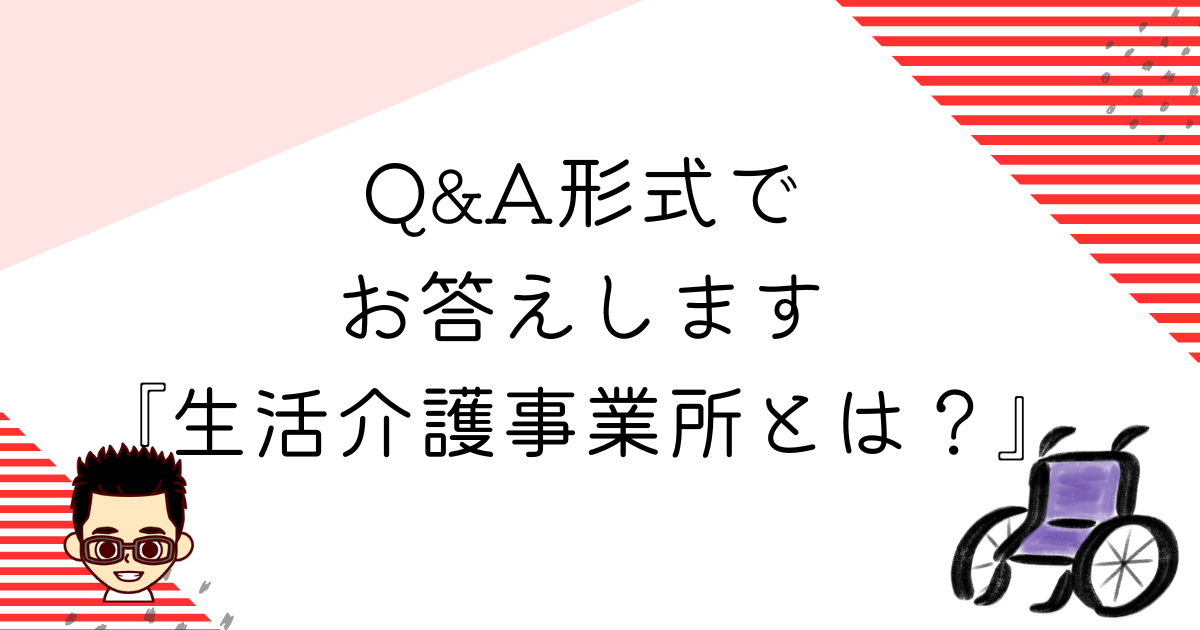


コメント