生活介護事業所の日中活動。ご利用者さんの満足度を高めるためにも、その施設にしかない『強み』を押し出していきたい。めざせ!福祉マスターでは、特色ある日中活動として生涯学習講座がおすすめをしています。
- 講座の流れがわからない
- 学校の授業みたいにやらなければいけないの?
- 最低限おさえておくべきポイントを知りたい
今回は、生活介護事業所で、障害のあるご利用者さんを対象とした生涯学習講座を10年以上実施している私が、生涯学習講座の流れを5つのステップでバッチリ説明します。
この記事は、

・講座の流れを知りたい生活支援員さん
・生涯学習講座に興味がある人
・人前で話すのが苦手な生活支援員さん
におすすめです。
想定する講座

今回は、国語系の講座で「年賀状について学ぶ」という状況を想定します。私が担当している生涯学習講座でも、バリエーションをいろいろ用意しながら、毎年実施している人気のテーマです。
時間は45分間、小学校の授業1コマ分をイメージしていきます。
その他のおすすめテーマについてはこちらをご覧下さい。
⇒【関連記事】『生活介護事業所で生涯学習講座を実施するなら「〇〇系」がおすすめ』
ステップ① 【準備】なぜ?を探す
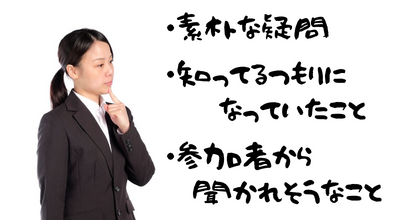
最初のステップは、そのテーマに関する「なぜ?」を探すことです。多ければ多いほど良いので、5個くらい考えてみましょう。
あなた自身がすでに知っていることでもOKです。「ご利用者さんなら、こんな疑問を持ってくれそうというものをピックアップして下さい。
- 年賀状はいつ頃から始まったの?
- めでたい四字熟語とはどんな物がある?
- 年賀状に「おめでとう」と書くのはなぜ?
- 年賀状を送る時のマナーはある?
- 書き損じた年賀状は捨てなければだめなの?
そして、その中から1つメインとなる「なぜ?」を決めて下さい。これが、講座を進めていく軸になります。
今回は「年賀状を送る時のマナーはある?」という「なぜ?」をメインテーマにします。インターネトなどを活用し、年賀状を送る時のマナーや、一般的なハガキとの違い、書き方に関するマナーなどを調べておきます。
ちなみに、その他の「なぜ?」も出番があるかもしれません。最初に決めたテーマが思ったよりも広がらなかった時に使ったり、予定よりも講座が早く終わった時の「残り10分」をつなぐ時に役立ちます。
事前準備がしっかりできていれば、講座は7割成功したと言っても言い過ぎではありません。普段からネタ帳を用意し、知識をストックしておくのがおすすめです。
ステップ② 【導入】「なぜ?」でご利用者さんをつかむ
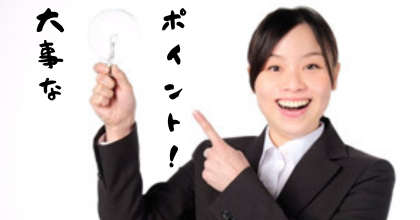
テーマが決まって、ある程度準備ができたら、いざ講座の始まりです。導入部分では、先ほど決めた「なぜ?」を使って、ご利用者さんの気持ちを「学びモード」に持っていきます。
全体の時間を45分と設定する場合、最初の5分くらいを使うイメージです。
慣れないうちは「〇〇について不思議に思いますよね?」と、こちらから「なぜ?」を振ってしまいがちです。最短距離でメインテーマにいけるメリットはあるものの、この方法はご利用者さんの自由な発想を妨げてしまう恐れがあります。
理想はご利用者さんから「なぜ?」が出ることです。あまり時間は意識せず、「今日は◯◯についてやります」と切り出し、「〇〇について知りたいことや、知っていることはありますか?」と問いかける方法がおすすめです。
年賀状についてであれば、
- お正月に届く
- あけましておめでとうを書く
- お年玉がついている
などの意見が出るかもしれません。もし、年賀状を送る時のマナーに関する意見が出なければ、無理に引き出す必要はありません。事前に用意しておいたサブテーマに切り替えてもいいですし、「どうやればお正月に届くか考えてみましょう」という感じで
ステップ③【発展】「わかった!」「いいね!」でやる気アップ
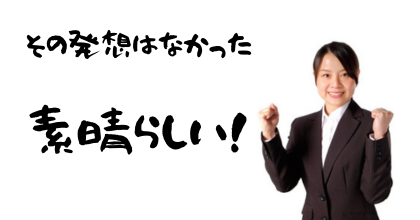
導入が終わったらメインテーマに入っていきます。ここは、担当者がメインで喋るパターンでもいいですし、クイズ形式で進行するパターンもアリです。
導入で5分くらい使うとすると、まとめの時間に5〜10分ほど使いたいので、30分から35分くらいがメインテーマで使える時間です。
例えば、クイズ形式で答えてもらいながら進行するとして、出題⇒回答⇒答え合わせで、1問あたり3分使うとするなら、10問くらい出題できることになります。
意識してほしいのは、流れの中に「わかった!(理解)」「いいね!(共感)」をできるだけたくさん作ることです。
- 縁起が悪い表現があることがわかった!
- 「新年あけましておめでとうございます」は意味が2重になってしまう
- 送る人によって、挨拶の表現を変える場合がある
ちょっとトンチ問答みたいなことを言いますが、正解だけが正しいとは限りません。正解/不正解の2択なら不正解になってしまう答えでも、
「その発想はなかったです。素晴らしい!」
と返すことが多いです。
ステップ④【まとめ1】ゴールは決めるけどこだわらない
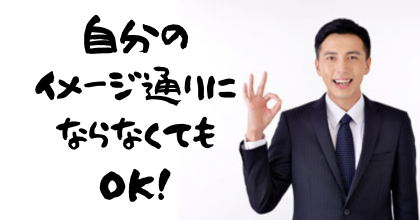
「生涯学習講座」という部分だけで考えれば、ある程度「このテーマはこうやってまとめよう」というゴールを設定しておくほうが良いと思います。
良いとは思いますが、「自分が設定したゴール」がそのまま実現するかと言えば話は違います。
例えば、年賀状のマナーというテーマで、
【導入】年賀状について知っていることを挙げてもらう
【発展】「年賀状を出す時期」「めでたい意味の四字熟語」「縁起が悪い表現」を学ぶ
【まとめ】自分が年賀状を書く時に、意識して書いてみよう
という流れをイメージしたとします。これを実際にご利用者さんの前でやっても、この通りになることは多分10回に2〜3回です。
途中から「年賀状の歴史」というテーマになる
「お正月は、なぜめでたいのか」という流れが出る
参加者の興味が「四字熟語」にうつる
ということもあるでしょう。そんな時は、その流れに沿ってもOKだと考えています。無理に自分の決めたゴールに合わせようとせず、柔軟に軌道修正するのは少し抵抗があるかもしれませんが、「思い切って軌道修正しましょう!」と言って、講座を仕切り直したって構いません。
大切なのは、学ぶ楽しさを提供することです。
ステップ⑤【まとめ2】新しい「なぜ?」が出れば最高!

残り時間が10分を切ったあたりで、講座のまとめに入ります。ホワイトボードを使っていた場合は、出た意見を見ながら、たくさんの意見が出たことをしっかりと肯定します。
経験上、意見の正誤よりも「自分の意見を出せたこと」を全力でリスペクトすることで、「けんの講座ではどんどん発言して良いんだ」という空気が作られていき、結果的に良い意見が出やすくなります。
もしその中に、新しい「なぜ?」につながるものがあれば大収穫です。「次は〇〇についてやりましょう」とまとめて、講座終了です。お疲れ様でした。
まとめ
今回は、生活介護事業所の「生涯学習講座の流れ」を5ステップで説明しました。
- 「わかった!」「いいね!」「なぜ?」を意識したテーマ設定や進行を心がける
- 事前の準備ができれば7割できたと言っても言い過ぎではない
- 新しい「なぜ?」が次の講座のテーマになる
私は、生涯学習講座に「わかった!」「いいね!」「なぜ?」が必要だと考えています。頭文字を取って『W・I・N』です。
実施のためのハードルは決して低くはありませんが、学びはご利用者さんの生きる力になります。最初は上手くいかなくても、繰り返すうちに自分なりの流れが見えてきますので、この記事を参考に自分流の講座の流れを作ってみて下さい。

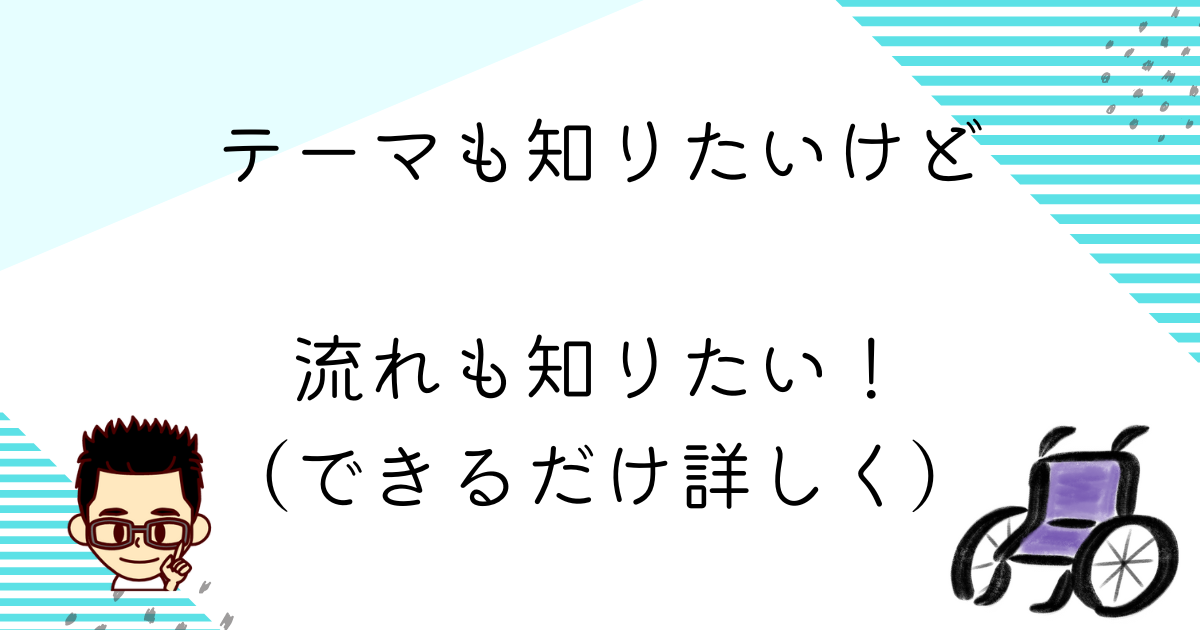


コメント