福祉施設職員のみなさん、今日もお仕事お疲れさまです。
今回は、こんなお悩みに寄り添います。
- 認定調査に同席することになったけど、何をどう答えたらいいの?
- 自分の答え方でご利用者さんの区分が決まってしまうの?
- 初めての同席で、不安しかない…
大丈夫です。
障害者福祉の現場歴15年の私が、「職員の目線」で、安心して臨めるコツをお伝えしていきます。
※この記事では、タイトルでは「障害支援区分認定調査」、本文中では「認定調査」と表記を統一して進めますね。
【📌デスクワークの効率化も、現場の業務も大事にしている私のプロフィールはこちら】
障害支援区分認定調査とは?
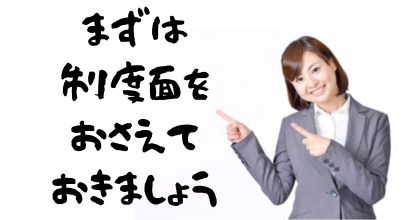
一言で言えば、障害支援区分を決めるための調査です。
障害支援区分は、障害福祉サービスの必要度を明確に判断するために使われます。
例えば、私が働いている「生活介護事業所」では、年齢や施設入所をしているかなどで、利用できる区分が変わります。(詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください)
認定調査では、市町村から委託を受けた認定調査員がご本人やご家族と面談し、80項目について聞き取りを行います(2023年10月現在)。
なぜ施設職員が同席するの?
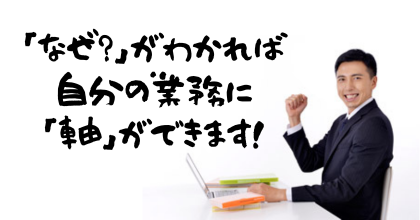
認定調査は、「普段の様子が分かる場所」で行われるのが基本です。
施設に調査員さんが来るということは、ご利用者さんの普段の様子を把握している場所だと認められているということ。
職員が同席する理由は、より正確な情報を集めるためです。
ここからは、私の経験も交えながら説明しますね。
1. 物事を順序立てて話すのが苦手な場合
障害特性によっては、気持ちが逸れやすかったり、質問の意図を見失ってしまうことがあります。
認定調査は基本1回きりなので、必要に応じて職員が話題を軌道修正することもあります。
2. 判断力に苦手がある場合
すべてのご利用者さんに意思はあります。
ただ、質問の意味を理解したり、状況を正しく判断することが難しい場合には、職員が補足したり、代わりに答える場面もあります。
3. 「できる」と答えてしまう場合
「できない」と答えることに抵抗を感じて、「できる」と答えてしまう方もいます。
ご本人が「できる」と思っていても、実際にはサポートが必要な場合もあるので、職員が客観的に情報を補うことで、より正確な情報に近づけます。
▶ 認定調査員マニュアルでは、「迷ったら『できない』で判定」とされています👇️
職員として、どう答えればいい?
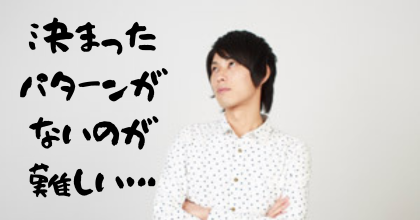
認定調査の項目は決まっていますが、質問の順番や進め方は調査員さんによって異なります。
- 普段の会話に質問を自然に織り交ぜる調査員さん
- マニュアル通り順番に進める調査員さん
いろいろなパターンがありますが、共通する答え方の基準はこれです。
▶ 「ご利用者さんがひとり暮らしをするとしたら、できるか/できないか」で判断する
この基準を持っていれば大丈夫です。
私の工夫
私は同席する時、できるだけ具体的な数字や頻度を伝えるよう心がけています。
例)食事介助について
- A:「基本的に自分で食べられますが、ごくまれに最後のひとくちを手伝っています」
- B:「基本的に自分で食べられますが、2週間に1回くらい、最後のひとくちを手伝っています」
→ Bのほうが、より具体的にイメージしやすいですよね。
また、
「〇〇している時は、見守りが必要」
「磨き残しチェックが必要」
など、支援者だからこそわかる視点も積極的に伝えています。
「これを言っても意味ないかも」なんて思わず、小さな事実も大切にしていきましょう。
まとめ
今回のポイントをまとめると…
- 認定調査は、障害支援区分を正しく判定するためのもの
- 職員が同席するのは、より正確な情報を集めるため
- 答えるときは「ひとり暮らしを想定」して判断する
認定調査員さんも、支援者も、ご本人やご家族も、
みんな「より良い支援につなげたい」という思いは同じです。
施設職員として同席することは、少し緊張するかもしれませんが、
この記事を読んで、少しでも前向きな気持ちで臨んでもらえたら嬉しいです。
また、認定調査だけでなく、ケース会議でも「伝わる書類」を作ることは大切です。スムーズに話し合いを進めるための【ケース会議のレジュメの書き方】もぜひ参考にしてください。
【生活支援員のデスクワークスキル】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
ありがたいことに、ご利用者さんだけでなく、ご家族さんからも「説明が丁寧でわかりやすい」とご高評を頂いています。
実はココだけの話、デスクワークはちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線でのお助けアイデア」をぜひご覧下さい。

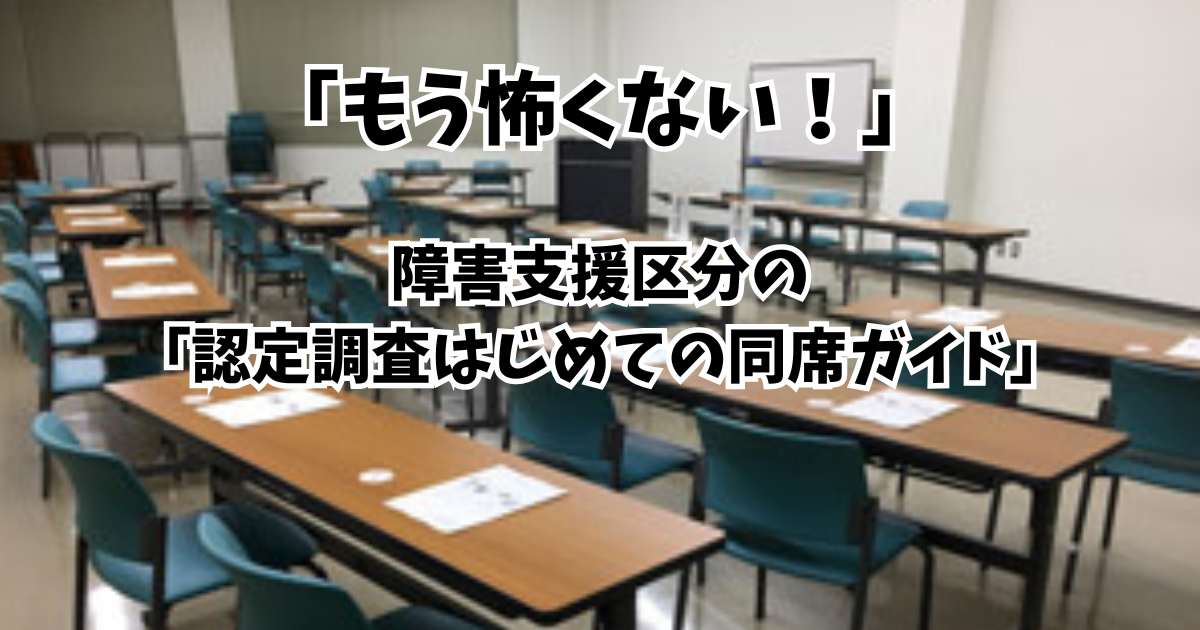
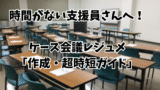
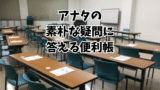


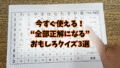

コメント