生活介護事業所に限らず、福祉の世界で働く人って「腰が痛い」っていうイメージはありませんか。平成22年のデータですが、厚生労働省の資料でも”業務上疾病のうち、腰痛が占める割合が増加傾向にある”と指摘されています。
👉️介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(厚生労働省:PDF)
介助にともなう「腰痛」は、現場でよくある悩み。だからこそ、生活支援員歴15年の私が実践している“技術としての声かけ”を軸にした腰痛予防をご紹介します。
【📌仕事と暮らしのベストバランスを大事にしている私のプロフィールはこちら】
腰に負担がかかりやすいシーン4選
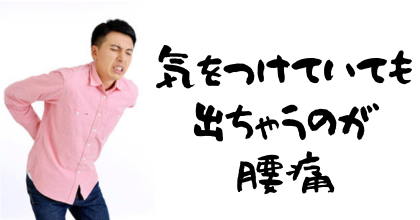
① トイレ介助のとき
⇒どうしても前傾姿勢になりがち。1日何度も対応することも。
② 移乗介助のとき
⇒持ち上げる動作が負担。補助具を使っても、力は使う
③ 送迎車のフックをかけるとき
⇒不自然な格好になってしまいがち。
④ 入浴介助のとき
⇒体をひねったり中腰になる。浴室が濡れていると滑りやすい。
私の実践、3つの理由
私が声かけによる腰痛予防を実践し始めたきっかけは、「自分が介助しようとしている時に、ご利用者さんの意識が別のところに向いていたらやりにくいな」と感じたことです。
例えばトイレ介助なら、介助する側もされる側も「トイレ介助」に意識が向いていること。これ、調べてみたら「共同注視」と言うそうです。詳しくはこちらのサイトがとてもわかりやすかったです。
👉️共同注視とは何か、そしてそれが障害されるとどうなるか(外部リンク)
① 自分自身への「介助モード」スイッチ
「1、2の3でいきますね」と声に出すことで、
自分自身の体も「よし、構えよう」と準備できます。
② ご利用者さんにも心の準備を
不意な動作は、利用者さんもびっくり&力が入ります。
結果として介助がしにくくなり、腰への負担が増大。
声かけは、両者の安全を守るバリアでもあるのです。
③ 介助に必要な「力」が軽くなる
力の入っていない脱力状態の体は、予想以上に重たいもの。
「いきますね」「一緒に立ちましょう」などの声かけで、
利用者さんが少しでも力を入れてくれれば、介助もスムーズに。
体の負担がグッと軽くなります。
実はこれ、「重心」が大きく関わってきます。こちらの資料がとてもわかりやすかったので、是非参考にしてみて下さい。
声かけレベルを上げる!「気持ちのいい数字」の活用法

「同じ方法で介助しているのに、Aさんはタイミングが合うけどBさんは合わない」と感じた経験はありませんか?
タイミングが合わない介助の多くは、
声かけの「リズム」がズレていることが原因かもしれません。
例えば──
- Aさんは「せーの、ハイ(2拍)」がしっくり
- Bさんは「イチ、ニのサン(3拍)」でスムーズに動作
- Cさんは「イチ、ニ、サン、ハイ(4拍)」が合う
こんなふうに、利用者さんによって「心地よいカウント」は違います。
日々の観察や他の支援者との情報共有で、そのリズムを見つけてみましょう。
【実例】カウント別の声かけパターン
▼椅子から立ち上がる支援の場面を想定
●「2カウント」が合う人へ
「せ〜の(1)、ハイ!(2)」
●「3カウント」がしっくりくる人へ
「イチ(1)、ニ〜の(2)、ハイ!(3)」
●「4カウント」が必要な人へ
「イチ(1)、ニの(2)、サン(3)、ハイ!(4)」
こういった声かけの工夫で、
驚くほどスムーズに動いてくれるようになるご利用者さんもいます。
私の実践例:ちょっと特殊な3カウント

私がかつて担当していたご利用者さんに、ちょっと特殊なカウント方法でタイミングを合わせていた人がいました。
Aさん:3カウントがしっくりくるタイプ
「いきますよ〜(1)しっかり息を吸って(2)どっこいしょ〜(3)」
Aさんは、数字を理解することが苦手だったので、毎回この方法でタイミングを合わせていました。
ご利用者さんの特性に合わせて柔軟に言い換えていくことも大事です。
まとめ:声かけはセルフケア
- 腰痛を引き起こしやすい場面を知る
- 声かけで「自分と利用者さん」両方の心と体を準備
- 「気持ちのいいカウント」で、リズムよく介助
「腰を痛めてしまうかも」という不安を抱えながらの業務は、心理的にも負担がかかります。
でも、技術や視点の工夫で、確実に負担は減らせます。
こちらの記事でも、日常の様々な場面で起こるストレスと上手く向き合っていくことの大切さについて書かれています👇️
つまり、声かけは立派なセルフケアなんです。「自分なりの腰痛対策」に、声かけという選択肢を――。
【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
生活介護事業所で15年働く、現役の生活支援員です。小学校第1種教員免許や、介護福祉士、ケアマネージャーの資格を持っています。
でも実は、常に第一線で働いてきたわけではありません。調子を崩して、専門家の力を借りながら立て直した時期もあります。
その経験から、「セルフケアって大事だな」と実感するようになりました。
このカテゴリでは、あの時の経験が誰かの役に立てればという願いを込めて、“体をいたわる支援のしかた”や、“ちょっとした整え方”を、私なりの言葉でまとめています。

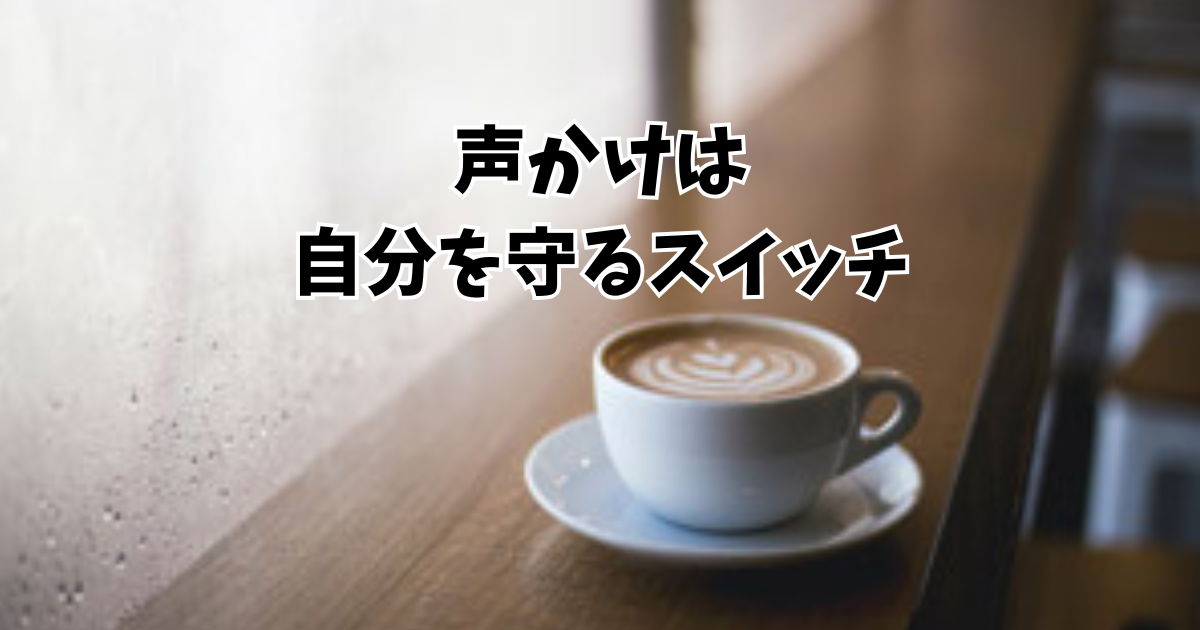

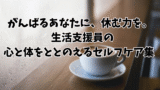



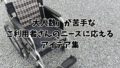
コメント