今日は、「生活支援員の仕事に興味があるけど、仕事内容がイメージしにくい」という人のために、就活サイトでは教えてくれない、細かすぎる1日の流れをご紹介します。(※あくまでも「私の職場では」という記事であることを前提に読んでください)
- トイレ介助と食事介助に追われている?
- 常にせわしなく動き回っている?
- ご利用者さんの突発的な行動に振り回されている?
「障害がある人の施設で働く」と聞くと、ネガティブなイメージを持ってしまっている人もいるかもしれません。実際、時間に追われる事があることも事実ですが、この記事では、実際に働いている私の視点で、生活支援員の1日の流れを可能な限り詳しく書いていきます。
この記事は、
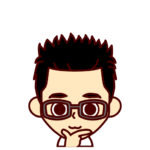
・生活支援員の仕事に興味がある人
・施設見学を考えている当事者さん
・生活介護事業所に転職を考えている人
におすすめです。
出勤〜朝の送迎
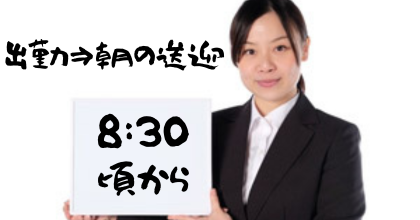
生活介護事業所は、通うタイプの施設です。私の職場では、出勤後に朝礼を行い、送迎車でご利用者さんをお迎えに行きます。
8時半頃に出発して、9時半頃から徐々に皆さんが到着し始めます。車の大きさによりますが、運転手と介助員の2名で送迎に出ることもあります。
送迎は、あらかじめ決められた場所を回って、ご利用者さんの自宅に伺うこともあれば、事前に決められた集合場所で乗ってもらうこともあります。
ご本人さんのみで乗り込まれる場合や、ご家族さんが出てきてもらえる場合、ヘルパーさんから引き継ぐ場合など、様々なパターンがあります。
送迎がないときは?

日によりますが、送迎車に乗らない事があります。そんな時は、お出迎えのための掃除をしています。玄関とトイレ、洗面所は特に汚れが目立ちやすいので、こまめに掃除するのがポイントです。
他にも、普段やらない施設整備をすることもあります。立地条件にもよりますが、草刈り機が使えると重宝されますよ。
⇒【関連記事】『気配り上手な生活支援員になるための「ついで掃除」のテクニックとは?』
⇒【外部リンク】『意外に多い!? 「介護以外の介護の仕事」』:別館・めざせ!福祉マスター
送迎車の到着
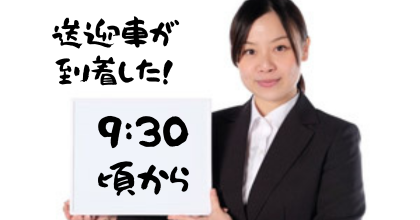
ご利用者さんを乗せた車が到着次第、検温と簡単な健康チェックを行います。送迎担当者はご利用者さんの乗り降りを、送迎がない職員は検温と健康チェックをメインで行います。
ここが「1日で最もトイレ介助が集中しやすいタイミング」です。
「乗車時間が長い」、「施設についたらトイレに行くルーティーンがある」というご利用者さんサイドの状況と、「大半の職員が送迎に出ていて、トイレ介助に入れる職員が一時的に少なくなる」という状況が、悪い方向に噛み合ってしまうことがあるからです
【関連記事】⇒『「生活介護事業所の生活支援員」の仕事はココが大変』
午前の日中活動
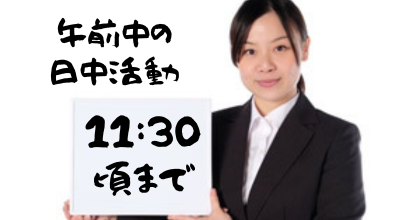
送迎とトイレ介助が一段落したら、午前中の活動に移ります。ここは施設によりますが、ご利用者さん全員で簡単な朝礼などがある場合もあります。私の職場では、ご利用者さんが到着し、ご自分の好きなタイミングで日中活動に入ります。
「運動」や「音楽」、「創作活動」や「生涯学習講座」の時間があり、1日のスケジュールが決まっています。私の職場では、午前/午後で分かれていて、担当する活動がある場合は、それを実施します。
【関連記事】⇒『日中の充実をサポート! 生活介護事業所で人気のアクティビティまとめ』
担当する日中活動がない時は?

担当する日中活動がない時にする主な業務は次の4つです。
①トイレ介助や、定時の水分補給など
⇒日中活動の担当者が活動に集中できるよう、トイレ介助や水分補給などに対応します。ご利用者さんの到着時よりも、介助の頻度は少ないという印象です。
②見守り支援
⇒日中活動に参加するご利用者さんの付き添いだけでなく、参加しないご利用者さんの見守り支援なども行います。
③洗濯や昼食の準備
⇒洗濯や昼食の準備も大切な業務です。特に昼食の準備は、刻み食の用意のためにおかずを刻んだり、アレルギーの確認をして、対象の食材が使われている料理を除去するなど、気が抜けないことに加えて、時間と手間がかかる仕事です。
【関連記事】⇒『生活介護事業所で、「やわらか食が必要な人」ってどんな人?』
昼食準備〜食事介助
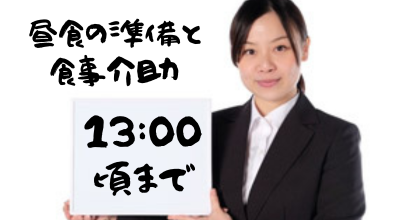
私の職場には食堂がないので、皆さんが過ごすスペースがそのまま食事スペースになります。そこで、昼食の時間の10分ほど前から、片付けと配膳の時間になります。
配膳が終わったら、昼食の時間です。サポートが必要なご利用者さんへの食事介助をします。よほど職員数が不足している場合を除き、原則として1対1での介助を実施します。
ご利用者さんの食事介助が終わったら、職員も交代で昼食休憩です。その間も、ご利用者さんのトイレ介助などは待ったなしなので、休憩していない職員で対応します。
食事介助がない時は?

先に休憩を取ったり、洗い物やハミガキの介助を行います。先に昼食を済ませ、まだ食べていない職員と食事介助を交代することもあります。
午後の活動
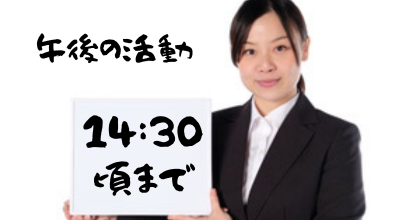
午後からも、スケジュールに沿って日中活動をします。先ほど、「ご利用者さんが到着されたタイミングでトイレ介助に入ることが多くなる」と書きました。
午後の活動に入るタイミングも、送迎車の到着時程ではありませんが、トイレ介助が集中しやすい時間です。休憩に出ている職員が多いことや、活動の前にトイレに行きたいご利用者さんがいることが理由だと考えています。
担当する日中活動がない時は?

午前中同様、ご利用者さんの見守り支援などを行います。その他に、自分が担当している日中活動の準備をしたり、介護記録を記入することもあります。
現場を他の職員に任せ、個別支援計画の作成に関する聞き取りや、ケース会議への参加をすることもあります。
帰りの送迎
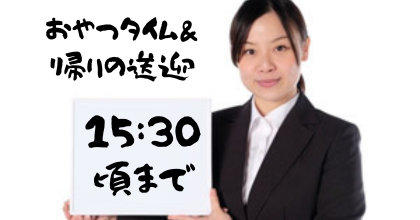
私の職場では、14時半頃におやつタイムがあります。そして15時半ごろから、随時ご利用者さんの帰りの送迎がスタートします。
身支度のお手伝いや、帰る前のトイレ介助などを適宜行います。
送迎がない時は?

ご利用者さんをお出迎えするため、翌日の準備をします。掃除をしたり、消毒をするのが主な業務です。
皆さんが帰ってから、就業時間までは貴重な「自分のペースで仕事ができる時間」です。個別支援計の作成や、研修用の資料の作成など、集中したい仕事がある場合はこの時間を使うことが多いです。
まとめ
今回は、「就活サイトでは教えてくれない、細かすぎる1日の流れ」というテーマで、私の職場を例にしてご紹介しました。
- 送迎は重要な業務の1つ
- 担当する日中活動がない時は、他の職員をサポート
- 帰りの送迎後は貴重な「自分のペースで仕事ができる時間」
ご紹介したのは私の職場の場合であり、あくまでも参考程度に考えていただきたいのですが、常にトイレ介助に追われていたり、突発的な事態に対応しっぱなしということはありません。ご利用者さんと一緒に、ゆったりとした時間が流れていくことも多いです。

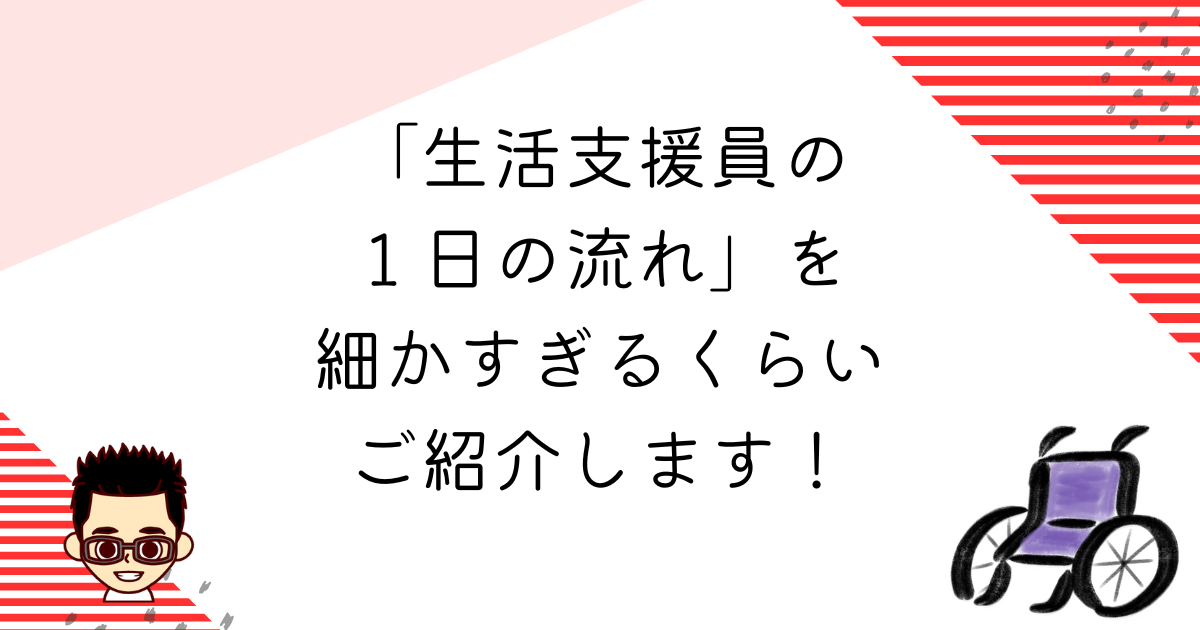

コメント