「点字、勉強しなきゃダメ?」と焦るあなたへ
エレベーターのボタンや缶ビールのフタなど、身の回りで見かける点字。
何が書いてあるかは分からないけれど、「あ、これが点字か」と気づく場面は意外と多いですよね。
私が点字に触れるようになったのは、あるご利用者さんとの日常的な関わりがきっかけでした。
「勉強しなきゃ」と意気込んだというよりも、「必要になった」という方が近いかもしれません。
この記事では、
- 利用者さんとの出会いから自然に点字を知った実体験
- 点字に関するちょっとした知識
- 実際に支援の中で感じた「点字の魅力」
を紹介していきます。
利用者さんとの日常から始まった点字との出会い
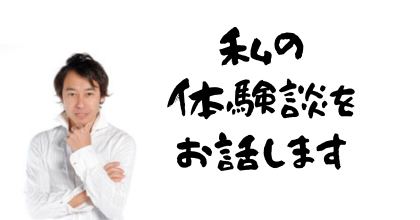
私に点字を教えてくれたのは、ご利用者さんであるマユコさん(仮名)です。
マユコさんは、全盲で左半身に麻痺があります。
施設での活動を通じて少しずつ関係を深めていた私ですが、ある時、正式に彼女の支援を担当することになりました。
これまでのやりとりは主に「会話」と「ご家族さんを通した連絡」でしたが、
「本人ともっと深く、やりとりしてみたい」と思うようになったのです。
正直に言うと、最初は「点字なんて全然知らない」「難しそう」と思っていました。
でも、”点字について知りたいです”と伝えた私。そして、マユコさんは快く教えてくれました。
私の足音を聞き分けるくらい感覚に優れた彼女は、
教え方もとても的確でわかりやすく、私は少しずつ点字に親しむようになりました。
まずはこれだけ知っておこう!点字のミニ知識
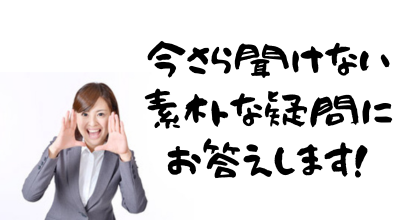
- 「点字じゃない文字」は「墨字(すみじ)」
→ 目で読む文字のことです。 - 点字は誰が作ったの?
→ 発祥はフランス、ルイ・ブライユという人が考案。日本では石川倉次が体系化し、1890年に正式採用されました。 - 点字の日ってあるの?
→ あります。日本の「点字の日」は11月1日、世界ではルイ・ブライユの誕生日である1月4日が「世界点字デー」です。
5つの「点字の魅力」
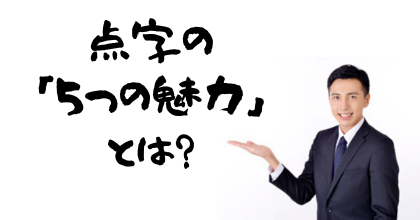
1.読むためのルールが明確で、迷いにくい
点字はすべて「左から右へ」「横書き」読むというルールで統一されています。
文字の形も一種類しかなく、フォントや大きさで迷うことがありません。
視覚に頼らず「触って読む」からこそ、シンプルなルールが設定されています。
2.ひらがな・カタカナの区別がない
「バナナ」と「ばなな」は、点字では同じ表記になります。
「音」だけで表す表音文字だから、書き方も音の通り。
例えば「お母さん」⇒「おかーさん」、「学校へ行く」⇒「がっこーえいく」と書くのが基本です。
3.仕組みはローマ字に似ていて覚えやすい
点字は6つの点の組み合わせで構成されていて、「母音+子音」のルールはローマ字と近い感覚。
私もこの仕組みに気づいたとき、「なんだか英語の授業みたい!」とちょっと楽しくなりました。
4.濁音や拗音のルールが奥深くて面白い
たとえば「が」は、「か」の前に「濁点の記号」をつけた形で表します。「次の文字を濁点を付けて読む + か」で「が」になる、という具合です。
1文字で完結せず、「2ブロックで1音」を表すこの仕組みが、私にはとても面白く感じました。
5.スペースの使い方が優しい
点字には「分かち書き」のルールがあります。
「点字に関する記事をたくさん書きました」
→「点字に 関する 記事を たくさん 書きました」
改行や空白を使って“読み手にやさしい形”にする姿勢は、私たちが墨字で配慮する「文字の大きさ」や「ふりがな」と同じ発想なんです。
点字=特別なもの?それとも日常の一部?
支援者としての立場でいうと、「点訳できるかどうか」が大切なのではなく、
「この利用者さんと、どんな方法で思いを通わせられるか」に重きを置きたいと感じています。
マユコさんは以前こんなふうに話してくれました。
「プリントを全部点訳されると、かえって読みにくいときがある」
読みやすさは人それぞれ。
点字も、墨字も、「相手のことを思って工夫する」という姿勢は同じだと思うのです。
まとめ:無理に学ばなくても大丈夫!
「いきなり点字を完璧に覚える」必要なんて、ありません。
支援の中で、「必要になったとき」に「少しずつ知っていく」ことでも十分です。
私自身、「学ぼう」と思ったわけではなく、気づいたら身近なものになっていたので、この記事はあえて「まなレク」のカテゴリには入れませんでした。
「この人は〇〇だから、この活動はできないかも」と考えるのではなく、「この活動、どうやったら一緒に楽しめるだろう」という優しい気持ちで向き合ってもらえたら嬉しいです。
【日中活動のアイデア】の記事をもっと読みたい人は?
こちらの「まとめページ」から、記事一覧をご覧ください。他のカテゴリも気になるあなたのために、まとめ記事一覧へのリンクも用意しています。

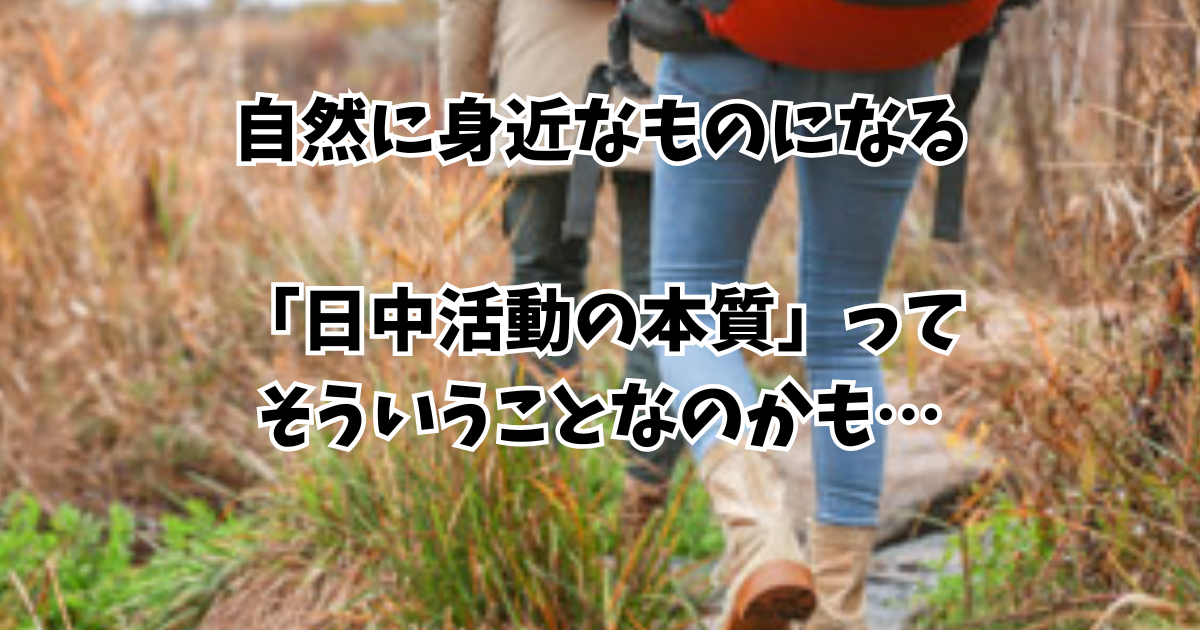
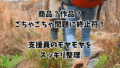
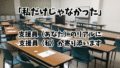
コメント