こんにちは!今回は、生活介護事業所で働く支援員さんに向けて、「掃除」をテーマにお話しします。
「掃除って後回しになりがち…」
「目の前の業務で精一杯で、つい手が回らない」
「支援のスキルを磨いた方が大事なのでは?」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
実は私もそうでした。でも、掃除って「ただの片づけ」じゃないんです。
“気配り”の力を発揮できる、大事な支援のひとつなんです。
この記事では、現場歴15年の私が実践している、「ついで掃除」というテクニックをご紹介します。
この記事はこんな方におすすめ!
- 支援の仕事を始めたばかりの新人さん
- 後輩に掃除を教える立場の研修担当さん
- 掃除は苦手だけど、やるべきだと感じている支援員さん
掃除で差がつく!気配りのポイント3つ
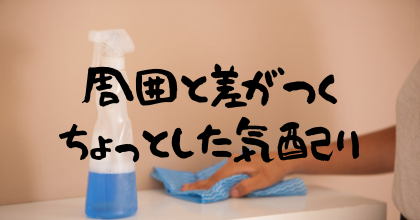
ご利用者さんの“目線”で見る
ただ「きれいにする」のではなく、ご利用者さんからどう見えているかを意識するのがポイントです。
- 車椅子に座った高さ
- 床に座っている目線
- 洗面所など、立っていても視線が低くなる場面
この視点で施設を見ると、今まで気づかなかったホコリや汚れが見えてきます。
危険を“予測”する
掃除中に「これ、危ないかも」と思ったことはありませんか?
たとえば──
・いつもと違う場所に雑巾が置いてある
・落ち葉や紙くずが通路にある
・備品がズレて置かれている
ASD、特に自閉的傾向の強いご利用者さんは、こういった「いつもと違う」状況に不安を感じやすく、混乱につながることもあります。
「〇〇さんはこれが気になるかもしれないな」と先回りする視点が、安心できる環境づくりにつながります。
ご利用者さんの“変化”に気づく
こんな経験、ありませんか?
「同じ場所に髪の毛が何日も落ちている」
→ 実は、あるご利用者さんがストレスで髪を抜いていた…!
掃除中だからこそ気づける小さな変化。
それが、不調のサインをキャッチするきっかけになることもあるんです。
「ついで掃除」の実践例
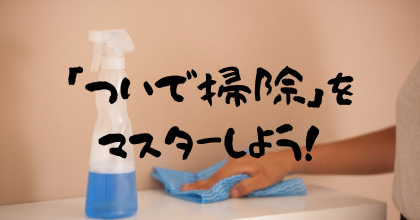
「掃除しよう!」と構えるのではなく、“何かのついで”にサッとやるのが「ついで掃除」のコツ。ここでは、私が日常で実践している例を紹介します。
出勤したついでに
- 押しピンやガラス片が落ちていないか
- 廊下に落ち葉や掲示物が落ちていないか
朝一番にサッと拾っておくだけで、事故防止につながります。
ハミガキ介助のついでに
- 洗面所の蛇口まわりに食べかすはないか
- 床が濡れていないか
- 歯ブラシが所定の位置にあるか
次に使う人の気持ちを考えて、ほんのひと手間が喜ばれます。
トイレに行ったついでに
- トイレットペーパーが切れていないか
- 床が濡れていないか(滑りや感染リスク防止)
トイレ介助中はバタバタしがちなので、自分のトイレタイムがチャンスです。
「そうは言っても…」な現実に寄り添う
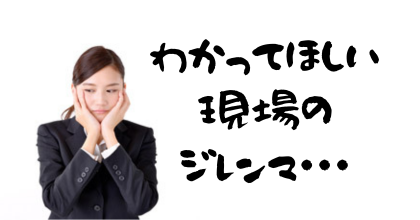
もちろん、理想通りにいかない日もありますよね。
- 掃除中に呼び出しがかかった
- ご利用者さんの対応で手が離せなかった
- 宅配便が届いたタイミングだった
そんなときは、職員同士で「できなかったこと」をサラッとカバーし合える空気が大切です。
「掃除してくれてありがとう」
「ここ、きれいにしておいたよ」
そんな一言が、チーム全体を気持ちよく回します。
まとめ:掃除は立派な支援のひとつです
「ついで掃除」は、支援の手を止めずに環境を整える、無理のない工夫です。
- ご利用者さんが過ごしやすい空間をつくる
- 危険を予防し、安心できる環境を守る
- ご利用者さんの変化に気づくきっかけにもなる
掃除にまとまった時間を割けない時こそ、「ついで掃除」が頼れる存在になります。
小さな気配りが積み重なることで、“支援の質”がぐっと高まるんです。
「掃除が苦手…」「忙しくて後回しにしがち…」そんなあなたこそ、ぜひ一歩だけ踏み出してみてくださいね。
【便利グッズとお助けアイデア】の記事をもっと読みたい人は?
こちらの「まとめページ」から、記事一覧をご覧ください。他のカテゴリも気になるあなたのために、まとめ記事一覧へのリンクも用意しています。

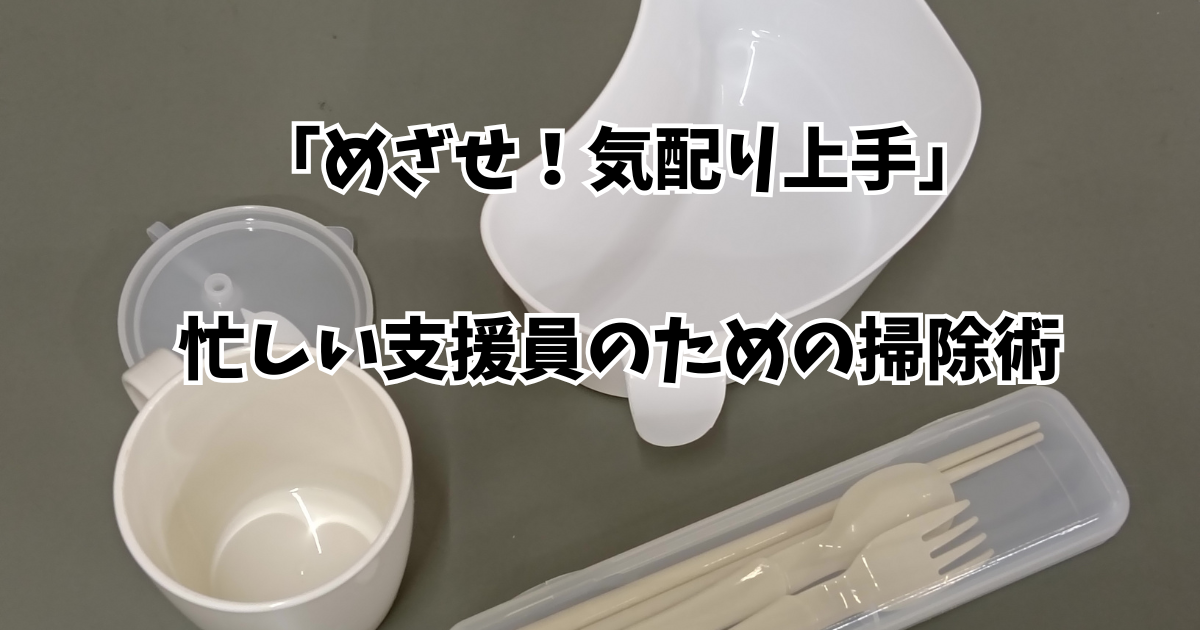
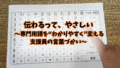
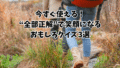
コメント