「来週はケース検討会をやりましょう」
…え、ケース会議?事例検討会?それとも別のなにか???
これ、新人時代の私の体験です。制度も技術も、とにかく覚えることがいっぱいで、「ケース会議」と「事例検討会」の違いがあやふやなまま、とある研修会に参加しました。
そんな中、「ケース検討会」という新たな言葉が登場!もう脳内は大混乱です。
メモをとりながらも、「これってどの会議のこと…?」とモヤモヤしていたのを今でも覚えています。
この体験から学んだのは、「名前」よりも「目的」が大事!ということ。
今回は、そんな私の体験をもとに「ケース会議」と「事例検討会」の違いを整理しつつ、目的から逆算してレジュメを作る、デスクワークスキルの実践方法も紹介します。
【📌デスクワークの効率化も、現場の業務も大事にしている私のプロフィールはこちら】
まずは「目的」を確認!

ケース会議とは?
- 目的:支援の方向性確認・課題共有
- 参加者:担当支援員+関係職種
- 特徴:他機関連携も含まれる
事例検討会とは?
- 目的:参加者のスキルアップ
- 参加者:全体、もしくは数名のグループ
- 特徴:課題に対して「自分ならこうする」という視点で話し合う
生活支援員として、医療や教育の関係者と関わることもあるため、名称ではなく目的を意識していきましょう。
と、新人時代の私に言ってあげたい!
「ケース検討会」ってなに?私が混乱した理由

「ケース検討会」という言葉、じつは正式な定義があるわけではありません。多くの現場では「ケース会議」や「事例検討会」のどちらかをそう呼んでいる、という場合がほとんどです。
つまり、名前は違っても“中身は同じ”ことがよくあるんです。
現場によって呼び名はさまざま
- ケース会議=ケース検討会と呼ぶ事業所も
- 事例検討会=ケース検討会として扱われることも
- 「ケースカンファレンス」や「ミーティング」と呼ばれることも
【実践例】目的から逆算するレジュメの作りかた

新人時代の大混乱は今、私のデスクワークに活かされています。レジュメを作る時に「会議の目的」を最初に確認するようになりました。
私が新人職員さんの研修をする時に、よく出す例がこちらです。
例①:ケース会議のレジュメ構成
- 会議の目的:ご利用者さんの〇〇を解決する
- 基本情報
- ご本人の希望
- 現在の支援内容と課題
- 今後の支援方向についての提案
例②:事例検討会のレジュメ構成
- 会議の目的:「自分ならどうするか」を話し合う
- 基本情報
- ご本人の希望
- 現在の支援内容と課題
- 今後の支援方向についての提案
目的をはっきりさせるだけで、会議の方向性がバッチリ決まるのがわかりますね◎
会議の違いがひと目でわかる!早見表
| 会議名 | 主な目的 | 参加者 | 特徴 |
| ケース会議 | 個別支援の確認・課題共有 | 担当+関係者 | 関係者のみで集まる |
| 事例検討会 | 振り返り・スキルアップ | チーム全体もしくは数名のグループ | 事例の人を知らなくても参加できる |
| ケース検討会もしくは他の呼び方 | 上記のいずれか | – | 呼び名に注意!中身で判断 |
まとめ|名前より「目的」から考える視点を
新人の頃は、「会議の名称が違えば、全て別の会議ではないか」と考えていました。 でも今では「目的」を意識することで、迷うことはほとんどなくなりました。
さらに、会議の目的を大切にすることで、準備する内容やレジュメの作り方が明確になり、自分と同じような悩みを持つ人への気配りもできるようになったと思っています。
会議名にふりまわされそうになったら、ぜひ一度「この会議の目的は何だろう?」と立ち止まってみてくださいね。
より実践的に、ケース会議を想定したレジュメの書き方について知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。テンプレートもありますので、ぜひ活用してみて下さい。
【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
ありがたいことに、ご利用者さんだけでなく、ご家族さんからも「説明が丁寧でわかりやすい」とご高評を頂いています。
実はココだけの話、デスクワークはちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線でのお助けアイデア」をぜひご覧下さい。

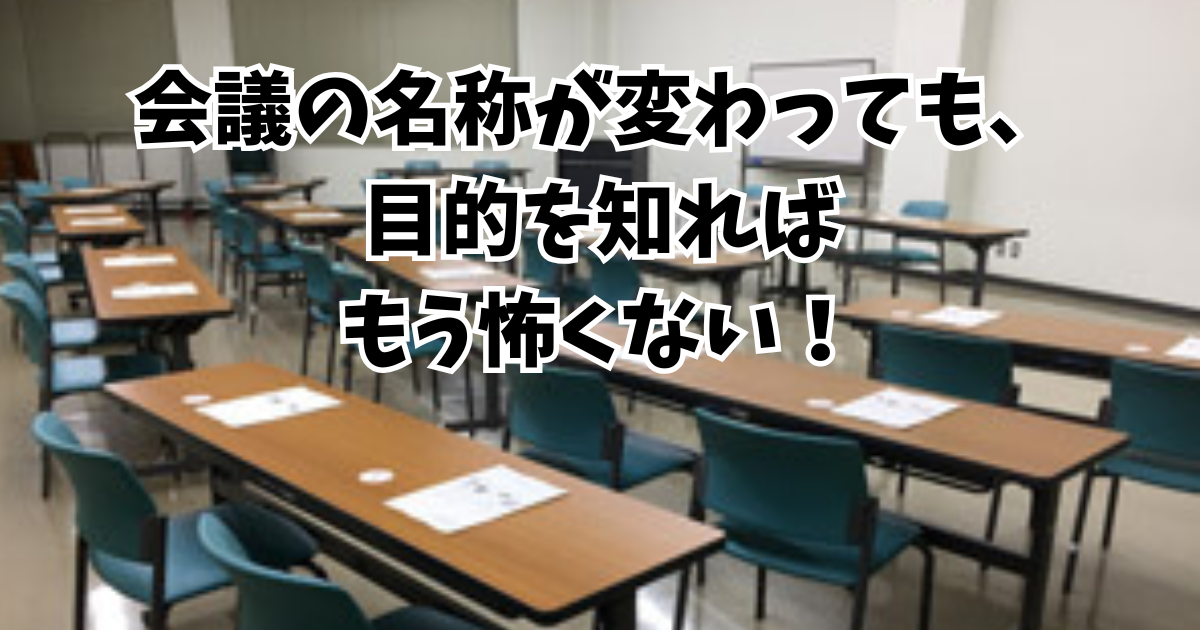
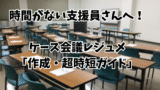
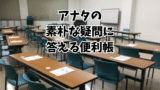


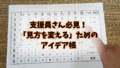
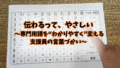
コメント