生活支援員の皆さん、ご利用者さんと一緒に神社やお寺へ出かけた経験はありますか?
施設みんなで初詣、観光地のお寺への日帰り外出など、ちょっと特別な行き先は日中活動の楽しみを広げてくれます。
でも、こんな不安を感じたことはありませんか?
「砂利道があるから無理かも…」
「参道って車いすで行けるのかな?」
確かに、風情ある玉砂利の参道は魅力的ですが、車いすの操作となると難しさもあります。
今回は、現場歴15年の支援員が「ベーシックな車いす」で砂利道を走行する介助のコツをお伝えします。
また、こちらの記事では、片麻痺のある方が、自分で健側に手袋をはめる方法を写真付きでご紹介しています。「一人で参拝に行きたい」という気持ちを応援したい生活支援員さんにオススメの内容なので、ぜひ、外出支援の参考にしてみてください。
【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】
なぜ砂利道はむずかしいのか?

砂利道は、車いすの「前輪(キャスター)」が砂利に取られやすく、思うように進めません。
また、タイヤ幅が狭いため、砂利に沈み込んでしまいバランスを崩すリスクも。
特に前輪が沈みすぎると、車いす全体が前に傾いてしまい、転倒の危険が高まります。
石畳や踏切も同様に注意が必要です。
悪路対応の車いすもあるけれど
砂利道向けの補助器具や車いす(例:「快適AQURO」「ジャリスター」など)もありますが、今回は…「普通の車いす」でもできる押し方の工夫 を紹介します!
悪路対応の車いすに興味がある!という人は、こちらもページを覗いてみて下さい👇️
👉️快適AQURO:雪道、砂利道もスイスイ。アウトドアも楽しめる車椅子パーツ(COM泉屋)
基本の押し方:ポイントは「前輪を浮かせる」

悪路を進むときは、「ティッピングレバー」を使い、前輪を浮かせた状態で後輪だけで走行する方法が有効です。
やり方のイメージはこうです:
- グリップをやや下方向に押しながら
- ゆっくりと前に押し出すように進む


前輪を15cmほど浮かせることで、砂利にキャスターが取られるのを防げます。
注意点:支援者とご利用者さん、両方に大切なこと
支援者が気をつけたいこと
✔️ 力が必要!無理は禁物
前輪を浮かせたまま進むには、押す力+支える力が必要です。
腕や腰に負担がかかるため、無理をせず、こまめに休憩をとりましょう。
✔️ 声かけがカギ!
ご利用者さんにとっては、普段と違う感覚で不安を感じやすい場面。
以下のようなタイミングで普段よりワンテンポ早い声かけを意識しましょう:
- 前輪を浮かせるとき
- 動き始めるとき
- 止まるとき
- 前輪を下ろすとき
できれば、支援者同士で浮かせた状態を体験してみると、乗り心地の違いを理解できます。
また、声かけはお互いの意識を共通のものに向ける「共同注視」の効果があります。私はこれを、腰痛予防法の1つとしても活用しています。詳しく知りたい方のために、それぞれおすすめの記事を置いておきますので、よろしければご覧ください👇️
👉️共同注視とは何か、そしてそれが障害されるとどうなるか(きもとメンタルクリニック)
ご利用者さんが気をつけたいこと
✔️ 背もたれにしっかり体を預ける
前輪が浮くと車いすがやや後ろに傾きます。安心して乗るためにも、背中を背もたれに預けてください。
✔️ アームサポート(肘置き)を持つ
急な段差などに備え、肘置きをしっかり握ってもらいましょう。
ベルト類の装着も確認しておくと、より安心です。
前輪を浮かせられない時は?
体格差や体力的な問題で浮かせるのが難しい場合は、「後ろ向き」で進む方法もあります。
坂道を降りる要領で進めば、前輪の引っかかりをある程度防げます。
ただし、進行方向が見えづらいため、できるだけ他の支援者と交代できると安心です。
車いすで坂道を下る時、どれくらいの勾配で後ろを向いたら良いか、判断するスキルに関する記事もありますので、興味がある人はぜひご覧下さい👇️
現地の工夫や貸出サービスも活用しよう
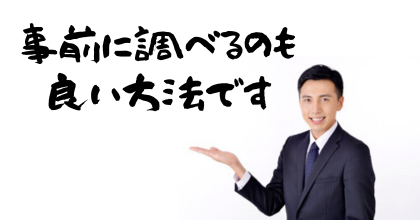
例えば、伊勢神宮では数に限りはありますが、砂利道でも走行しやすい車いすの貸出サービスがあります。
また、「バリアフリー対応の神社・お寺」を事前に調べるのも一つの手です。
複数の工夫を組み合わせて、無理のない計画を立てていきましょう。
私が外出支援の時に活用しているサイトはこちらです👇️
まとめ:支援員の工夫で、参道が笑顔に変わる
- 砂利道では「前輪を浮かせて後輪だけで進む」方法が有効
- ご利用者さんには背もたれに体を預け、肘置きを持ってもらう
- 事前の下調べや貸出サービスも活用しよう
支援員のちょっとした工夫で、「行けないかも…」を「楽しかった!」に変えることができます。
あきらめる前に、一緒にできる方法を考えていきましょう。
「砂利道の移動ができないからお参りに行けない」ということは、見方を変えれば「砂利道の移動ができればお参りに行ける」ということです。こういったリフレーミングの考え方に関する記事もありますので、気になる人は覗いてみて下さい👇️
【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。
一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えることに自信があります。
ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。
介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️


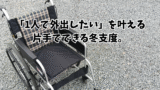
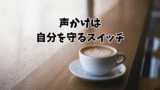

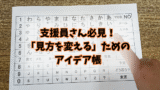



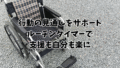

コメント