生活支援員として働いていると、ケース会議に参加する機会は多くあります。
時には、会議を主催する立場になることも…。
そんなとき、「レジュメを作らなきゃいけないけど、どう書けばいいかわからない!」と悩む方も少なくありません。実は私も、15年生活支援員を続けていますが、デスクワークは得意ではありません。
「そもそもケース会議と事例検討会って何が違うの?」と疑問に思うこともあるかもしれません。また、レジュメや議事録などの書類を「相手に伝わりやすく書くコツ」を知りたい人は、こちらの記事をご覧下さい👇️
【📌デスクワークの効率化も、現場の業務も大事にしている私のプロフィールはこちら】
レジュメとは?

レジュメとは、会議全体の流れを大まかにまとめたものです。
つまり、「これを読めば全部わかる!」という完璧な資料を作る必要はないということ。
福祉の現場は日々忙しく、じっくり資料作りに時間を割くのはなかなか難しいですよね。
だからこそ、「大まかな流れが伝わればOK!」と割り切って、シンプルにまとめるのがポイントです。
ステップ1:会議の目的を決める

まず大切なのは、会議の目的をはっきりさせることです。
ケース会議には、大きく分けて2つのタイプがあります。
情報を共有するタイプ
- 支援内容や役割がすでに決まっている場合に多い
- 比較的短時間でまとまるが、新しいアイデアは生まれにくい
例
「Aさんの支援方法を全体で共有する」
「歩行訓練の担当者を決める」
問題について意見を出し合うタイプ
- 支援方法がまだ決まっていない場合に多い
- 斬新なアイデアが生まれる反面、収拾が難しくなることも
例
「Aさんに必要な支援方法を考える」
「歩行訓練について意見を出し合う」
ステップ2:参加メンバーを決める

目的が決まったら、誰に参加してもらうかを考えます。
例
- 現在関わっている支援員
- これから関わってほしい職員
- サービス管理責任者
- 相談支援専門員
- 施設外の支援関係者(必要があれば)
「支援に必要な人」をイメージしながらリストアップしましょう。
ステップ3:会議の日時を決める

続いて、会議の日程調整です。
声かけの優先順位は、
- 外部関係者
- 相談支援専門員
- サービス管理責任者
- 関わり始める予定の職員
- 現在関わっている職員
この順番にすると、日程がスムーズに決まりやすいです。
また、「いつがいいですか?」ではなく、候補日を3〜4つ提示するのがコツ。
無理に全員を揃えようとせず、必要に応じて事前に意見を集めておきましょう。
ステップ4:テンプレートを作る

ここから実際にレジュメ作成に入ります。
あなた自身の負担をできるだけ減らすため、テンプレート化しておくのがおすすめ!
レジュメに必要な項目
- 資料のタイトル
- 日時
- 場所
- 目的
- 参加者
- 対象者
- 検討内容(タイムテーブルもあるとベター)
これらが書かれていれば、参加する人が「これはこういう方向性の会議なんだな」とわかりやすくなります。
情報共有タイプのテンプレ例
ケース会議資料
作成者:生活介護事業所『△△』 生活支援員〇〇
1. 日時:2024年〇月✕日 15:00〜
2. 場所:生活介護事業所『△△』会議室
3. 目的:「急な予定変更時の役割分担を決める」
4. 参加者:〇〇、〇〇(敬称略)
5. 対象者:Aさん
6. 検討内容:
①情報共有(5分)
②役割確認(15分)
③評価方法確認(10分)
④その他
意見出しタイプのテンプレ例
ケース会議資料
作成者:生活介護事業所『△△』 生活支援員〇〇
1. 日時:2024年〇月✕日 15:00〜
2. 場所:生活介護事業所『△△』会議室
3. 目的:「急な予定変更時の対応策を話し合う」
4. 参加者:〇〇、〇〇(敬称略)
5. 対象者:Aさん
6. 検討内容:
①情報共有(5分)
②アイデア出し(30分)
③検討結果まとめ(10分)
④その他
ステップ5:まとめ資料(議事録)を作る

会議が終わったら、できるだけ早く議事録を作成しましょう。
こちらもテンプレを用意しておくと楽です!
議事録に必要な項目
- 日時
- 場所
- 参加者
- 対象者
- 議題と結果
ポイントは、内容を1枚にまとめること。
似た意見はまとめて、シンプルに仕上げましょう!
番外編:会議を円滑に進める2つのテクニック
① グランドルールを書く
会議の最初に、話し方や態度のルールを伝えておくとスムーズです。
- 発言は短く、わかりやすく
- 専門用語には簡単な説明を添える
- 他人の意見を否定しない
② 知りたいことを書く
レジュメに、「この会議で明らかにしたいこと」を明記すると、
参加者の意識が揃いやすくなります。
テンプレで書いたAさんのレジュメを例にすると、
- Aさんにとって「急」とはどれくらいか知りたい
- 言葉以外の伝達方法について意見がほしい
などの意見を書き添えることで、参加者が事前に意見をまとめやすくなります。
実践してみよう
初めてのケース会議主催でも、
この5ステップとテンプレートがあれば、
レジュメ作成も怖くありません。
焦らず、丁寧に。
「流れが伝われば大丈夫!」という気持ちで進めてみてくださいね。
まとめ
ケース会議のレジュメ作成は、
慣れれば意外とシンプルです!
- 目的を決める
- メンバーを決める
- 日時を決める
- テンプレでレジュメを作る
- 議事録をまとめる
この流れを押さえて、支援の質をさらに高めていきましょう!
【生活支援員のデスクワークスキル】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
ありがたいことに、ご利用者さんだけでなく、ご家族さんからも「説明が丁寧でわかりやすい」とご高評を頂いています。
実はココだけの話、デスクワークはちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線でのお助けアイデア」をぜひご覧下さい。

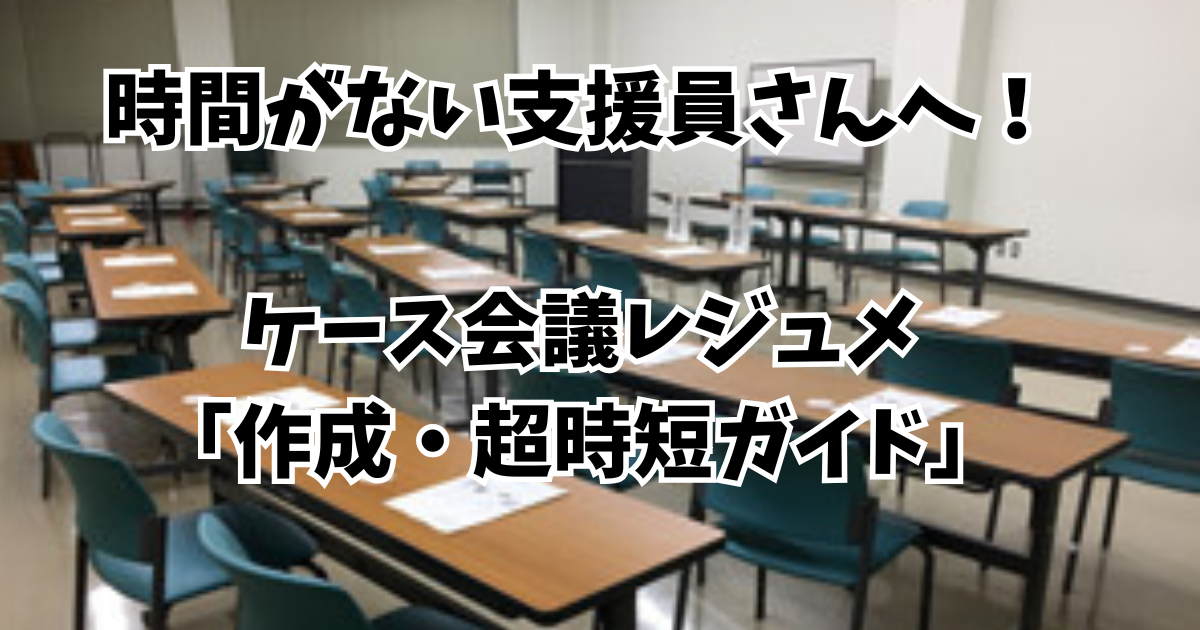
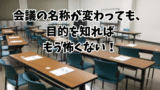

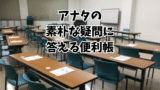


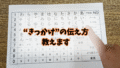

コメント