「まなレク」は、「学び×レクリエーション」という意味の造語です。
生活支援員として、10年以上まなレクに関わってきた私。「学びは生きる力になる」をテーマに、ただ楽しいだけじゃない、ちょっと知的な時間づくりを目指しています。
私の担当する方の中に、「文章の理解は難しいけれど、知らないことを知ると嬉しくなる」というご利用者さんがいます。今回のまなレクは、そのご利用者さんに向けて用意したものです。
今回は、「本」を使うけれど、読書はしない!
知っているようで知らなかった豆知識が満載の、ひと味違う”まなレク”をご紹介します。
学びながら、「誰かに話したくなる!」を引き出す活動の流れをまとめました。
【📌小学校の教員免許を活かして”まなレク”を実践している私のプロフィールはこちら】
用意するもの
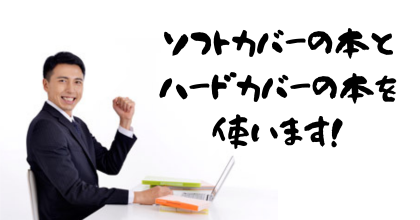
目安時間は30〜45分ほど。
用意するのはこの2つだけ。
- ソフトカバーの本
- ハードカバーの本
本の内容はなんでもOK。
ただし、少なくとも1冊は「スピン(しおり紐)」がついているものを選びましょう。
※ホワイトボードがあると、さらに盛り上がります!
今回は、「本の中身」ではなく「本のパーツ」に注目した豆知識まなレクです。
導入(ここが最大の山場)
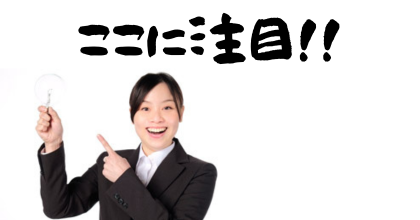
導入がこのレクの成否を分けます。
おすすめの切り出し方:
「今日は『本』についての豆知識がテーマです!」
そして、
「車にハンドルやシートベルトがあるように、本にもいろいろな“パーツ”があります」
と、わかりやすい例えを使いましょう。
出てきた言葉(「表紙」「ページ」「タイトル」など)はすべてホワイトボードに書き出します。
正解・不正解に関係なく拾うことで、場が温まります。
場の温め方に不安がある人は、アイスブレイクにもおすすめのこちらの記事をぜひご覧下さい👇️
👉️アイスブレイクとは?その目的・メリット・注意点・活用例を解説(slack)
発展(知的好奇心をくすぐろう)
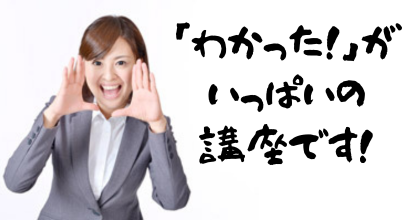
ここからは、本の各部名称を紹介していきます。
進め方はお好みで:
- クイズ形式(三択にするとメリハリUP)
- ミニ講義形式
たとえばこんな問いかけをしてみましょう。
- しおり代わりの紐の名前は? → スピン
- カバーの内側に折り込む部分は? → 袖(そで)
- 本の上と下の名前は? → 天と地
「なるほど!」や「知ってた?」という反応を引き出しやすく、知的好奇心を刺激できます。この知的好奇心を刺激するのが、このまなレクの最大のポイント。
冒頭でお話したご利用者さんが、他の支援員に「本の紐はスピンです!」と話しかけている様子を見たときには、心の中でガッツポーズでした。
本の各部名称について知りたい場合は、こちらのページがとても参考になります👇️
終わり方(感想シェアがおすすめ)
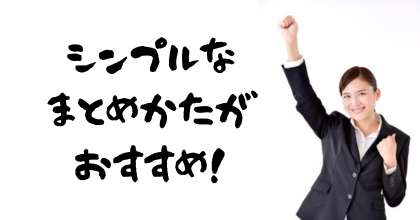
締めはシンプルに、
「今日わかったことを教えてください!」
「他にも知りたい名前はありますか?」
と、ご利用者さんの声を聞きましょう。
もし「もっといろんな物の名前も知りたい!」という反応が出れば、大成功!
次回に「日用品クイズ」などへ展開するヒントになりますよ。
まなレクが、次のまなレクにつながる。まさに「ネタの好循環」です。
もし、ネタ探しに不安がある人は、こちらの記事がおすすめです👇️
まとめ
- 知っているようで知らなかったことを楽しく学べる
- 「本=読書」という固定概念をくずす、新しい体験になる
- 豆知識や雑学が好きなご利用者さんにぴったり!
活動を考えるときは、「わかった!(W)」「いいね!(I)」「なぜ?(N)」を意識して。
ご利用者さんに「W・I・N」を届けるまなレク、ぜひ取り入れてみてください!
【まなレク:実践】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。
現場歴15年の現役生活支援員です。小学校第1種教員免許を持っていて、現在も月に10回ほどまなレクを企画・実践しています。
ご利用者さんからは、「ちょっと賢くなった気がする!」「答えるのが楽しい!」とご高評を頂いております。
私が大切にしているのは、ご利用者さんの「W:わかった!」「I:いいね!」「N:なぜ?」⇒『W・I・Nポイント』を引き出すこと。W・I・Nについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください👇️










コメント