「来週の施設見学の対応お願い」
当時の主任から初めてそう言われた時、私はテンパってしまいました。何をどう対応したら良いかわからなかったからです。
結果は散々…。質問されていないことまで答えてしまい、想定されていた時間を30分近くオーバーしてしまいました。
でも、何度も施設案内を担当する中で、”見学対応でよくある質問”をある程度パターン化することができた今では、時間的にも余裕を持てるようになりました。
この記事では、生活支援員として押さえておきたい質問を5つに絞って解説。事前準備とデスクワークもスムーズに進められるコツをお届けします。
【📌デスクワークの効率化も、現場の業務も大事にしている私のプロフィールはこちら】
見学対応前の準備

見学前にチェックしておきたいポイントは以下の通りです:
- 見学予定者の人数や構成(ご本人、ご家族、相談支援専門員など)
- 施設の落ち着いた時間帯の把握(案内がスムーズに進む時間)
- よく聞かれる質問の確認
施設の規模によっては、ユニット同士の連携も必要になりますので、時間に余裕を持ってチェックしておきましょう。
①生活介護事業所とは?
意外に多いのが「生活介護事業所とは何ですか?」という質問。ここでは、専門用語を使うのではなく、わかりやすい言葉で説明するのが◎。
生活介護事業所は、障害のある方が日中のサポートを受ける施設です。
施設ごとに得意・不得意があって、支援の内容も幅広いので、ご本人さんやご家族さんにとって相性の良い施設を選ぶことが大切なんです。
生活介護事業所について再確認したい人はこちら👇️
②施設の特色を教えてください
生活介護事業所は、施設ごとに特色があります。自分自身の施設の強みや、逆に「こういうサポートは難しいかも」という点を改めて確認しておくとスムーズです。
私たちの施設は、皆さんが大部屋でのびのび過ごせるのが強みです。創作活動に力を入れているので、「絵画や音楽で自分を表現したい」というご利用者さんが多く通っています。
逆に、個室がほとんどないので、自分だけの空間が必要、という場合には対応しにくいかもしれません。
特に、感覚過敏があるご利用者さんにとっては、カームダウンスペースが必要になる場合がありますので、対応できるかチェックしておきましょう。
👉️空港で広がるカームダウン・クールダウンスペース|2025年5月版(感覚過敏研究所)
③ご利用者さんの人数や男女比は?
これは、毎回答えているのではないかと思うほど、よく聞かれます。大まかで構いませんので、「施設の定員」「ご利用者さんの総数」「1日平均の利用人数」などを把握しておくと、スムーズに対応できます。
私たちの施設は、定員が20名、25名のご利用者さんと契約していて、1日あたり19名が通っています。男女比は、男性のほうが5名ほど多いです。
④スタッフ数と男女比
施設によっては、スタッフの男女比にも差がある場合があります。③の質問と一緒に聞かれることもあるので、事前に把握しておくのが◎。
スタッフの人数は15人で、常時12名が支援に入っています。スタッフの男女比は、だいたい6割が女性で、特にトイレと入浴は同性介助を徹底しています。
令和6年度の報酬改定で、虐待の防止・権利擁護の観点から、本人の意志に反する異性介助がなされないような取り組みが義務化されています。
👉️令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚生労働省)
⑤トイレを見てもいいですか?
え?と思われるかもしれませんが、この質問をされるご家族さんが一定数いらっしゃいます。身体的な介助が必要な場合、トイレの広さや便器の配置などを気にされる人が多い印象です。
車椅子が1台、余裕で転回できるスペースがあります。呼び出しボタンがあるので、万が一の時にも対応しやすい体制が整っています。
見学に適した時間帯について
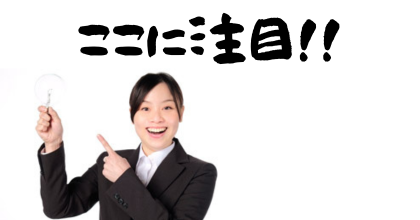
もし、見学の時間を調整する場合には、自分たちができるだけ落ち着いている時間帯を選ぶのがポイントです。
- 朝や夕方の送迎時間は、忙しいので避けるのが無難
- 設備面だけを見たい場合は、ご利用者さんが帰ってからの時間帯を設定するのもあり
まとめ
施設見学対応は、ご利用者さんとご家族が安心して選べるようサポートする大切な時間です。 事前に準備しておくことで、業務が効率化できるだけでなく、いざという時に自分自身が慌てずにすみます。
実際にご利用されることになった場合、担当者を集めて会議をする必要があるかもしれません。”ケース会議のレジュメの書き方”もチェックしておきたい人は、こちらの記事も是非読んでみてください。
【生活支援員のデスクワークスキル】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください👇️
勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。
ケアマネージャー、介護福祉士、小学校第1種教員免許の資格を持っていて、特に専門用語を使わずにわかりやすく説明することが得意です。
ありがたいことに、ご利用者さんだけでなく、ご家族さんからも「説明が丁寧でわかりやすい」とご高評を頂いています。
実はココだけの話、デスクワークはちょっと苦手。そんな私だからこそ書ける、「苦手な人目線でのお助けアイデア」をぜひご覧下さい。

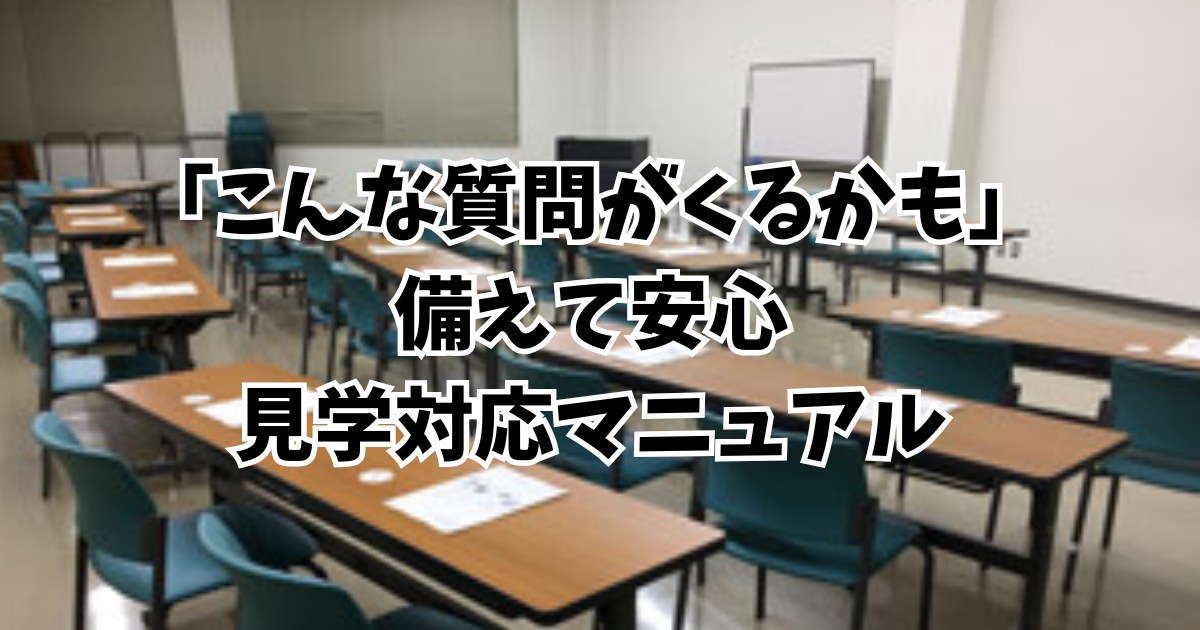
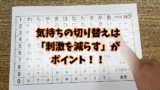
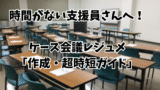
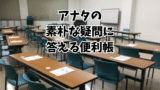


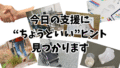

コメント