生活介護事業所の創作活動を活かすアイデア
生活介護事業所で働く皆さん、今日もお疲れさまです。
あなたの施設では、ご利用者さんの「創作活動」の時間はありますか?
そして、その活動で生まれた創作物を「販売」する場面はありますか?
- 作品と商品の違いって、よくわからない…
- 施設の備品を使った場合、著作権ってどうなるの?
- 作ったもの、どう活かしたらいいんだろう?
今回は、私が実際に働く現場で感じた疑問と工夫をもとに、
「創作活動を支援にどう活かすか?」を一緒に整理していきます。
この記事はこんな方におすすめ!
- 作品と商品の違いを整理したい支援員さん
- 創作活動をどう扱えばいいか悩んでいる職員さん
- ご利用者さんの表現をもっと大事にしたい方
「作品」と「商品」のちがいって?
まず、オンライン辞書(Weblio)を使って、意味を調べてみました。
作品
製作したもの。特に、芸術活動による製作物。
(例)文芸作品・工芸作品
商品
売るための品物。販売を目的とする財やサービス。
(例)キャラクター商品・目玉商品
つまり…
- 作品 → 芸術性や表現が重視される「つくりたいもの」
- 商品 → 売ることが前提の「買ってもらうもの」
支援現場で気になる3つのポイント
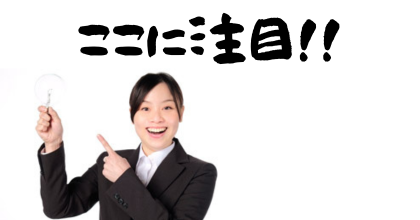
① 大量生産できるかどうか
- 商品 → 買ってくれる人に安定供給できることが求められます。
- 作品 → 一点もの・唯一無二。手間や偶然性が価値になります。
② 目的の違い
- 商品 → 買ってもらうための工夫(見た目・価格・実用性)
- 作品 → 「表現したい想い」が込められていることが大事
③ 著作権は誰のもの?
活動時間中に作ったものであっても、
著作権は基本的にご利用者さんのものです。
商品化や展示などの際には、ご本人の同意(またはご家族・後見人の同意)が必要になることを忘れないようにしましょう。
ご利用者さんの「創作活動」ってどんな意味がある?

私が働いているの生活介護事業所では、絵画・工芸・音楽などの創作活動を日中活動に取り入れています。「今日は〇〇の時間です」と決めず、ご利用者さんが「今日は絵を描きたい」「作詞をしたい」という気持ちになった時に支援しています。
「リハビリ」や「作業」ではなく、表現することそのものが目的です。
でも、これはあくまで一例。施設が違えば、活動の内容や目的はさまざま。
中には外部講師を呼んだり、音楽に特化していたりと、施設の特色が色濃く出る部分でもあります。
創作物の“活かし方”3つのアイデア
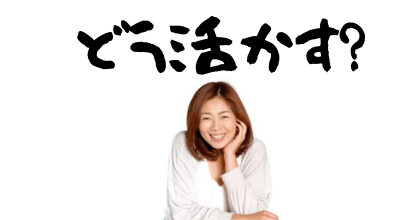
① 展覧会に出品する
地域や全国で開催される障害者アート展などに出品する方法です。
- 目標ができると、日々の創作にも張り合いが生まれやすい
- 「見てもらう」体験が、自己肯定感のアップにもつながります
※ 出品料や審査、搬入・搬出などの事前チェックは忘れずに。
② 施設内でギャラリーを開く
自分たちで「見てもらう場」をつくるのも、立派な発表の機会です。
- 玄関や廊下にギャラリースペースを設置
- テーマを月替りで決めたり、アーティストをピックアップするなど工夫も自由
「外に出さない発表」も、十分価値があります。
③ 原画として商品化する
支援の工夫として人気なのが、作品を商品の原画に使う方法。
- ポストカードやマグカップ、Tシャツなどへ展開
- 商品制作が難しい方も「原画提供」で参加できる
- 売上の一部を還元する仕組みを作れば、自己収入にもつながる
まとめ:創作活動は「心を動かす支援」につながる
- 商品は「売るもの」、作品は「表現したもの」
- 創作活動は施設の特色や支援方針を映す鏡
- 著作権は原則ご本人にあることに注意
作品が誰かに見てもらえた。褒めてもらえた。
それだけで、「もっとやってみたい」「次はこんなことがしたい」と、
やる気に火が灯ることがあります。
この小さな喜びが、やがて支援の好循環を生み出していく。
だからこそ、私たち支援員は、その最初の“気づきの場”を丁寧に作っていきたいですね。
【日中活動のアイデア】の記事をもっと読みたい人は?
こちらの「まとめページ」から、記事一覧をご覧ください。他のカテゴリも気になるあなたのために、まとめ記事一覧へのリンクも用意しています。

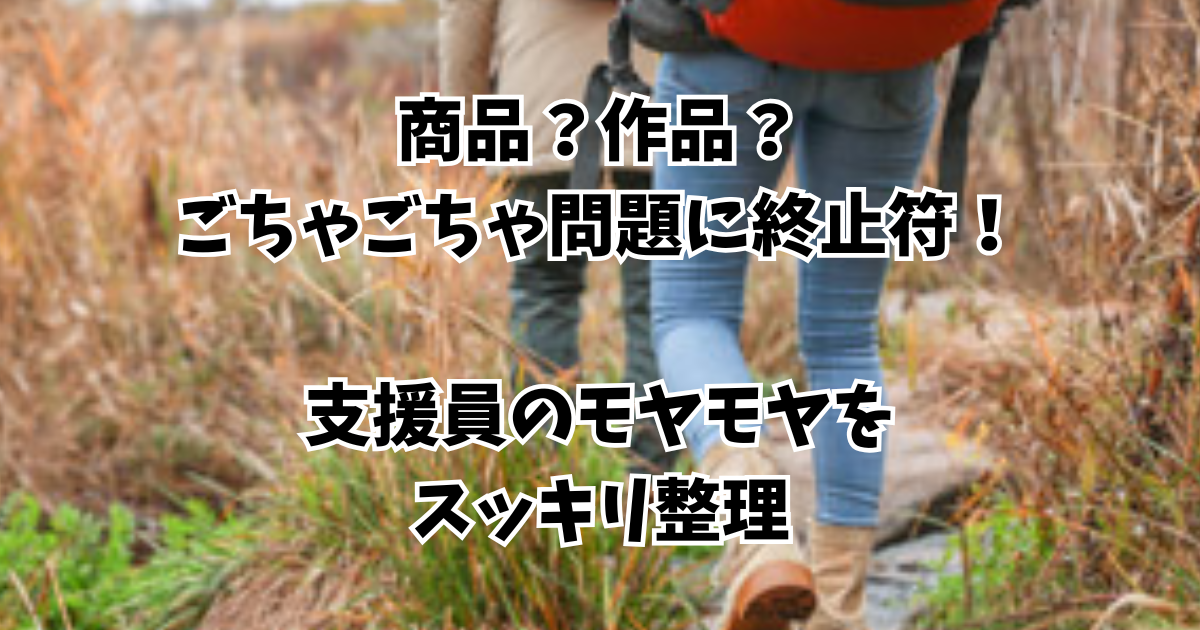
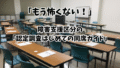
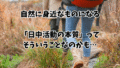
コメント