生活支援員の仕事、それはご利用者さんの日常を支えること――
誰かのために自分の力を使える素敵な仕事です。
でも! それと「疲れる」は別問題。私たち生活支援員も人間なんですから、疲れるものは疲れるんです。誰かに仕事の愚痴を話したくなるのは当たり前のこと。
そんな“わかってほしい”気持ち、私もずっと抱えてきました。
今回は、生活支援員の「心と体の疲れあるある」を6つ紹介します。しんどいと感じる私が悪いんじゃないか、と自分を責めてしまう前に、「あるある!」と共感してもらえることで、少しでもあなたの心が軽くなれば嬉しいです。
【📌仕事と暮らしのベストバランスを大事にしている私のプロフィールはこちら】
【心の疲れ1】伝わらないことに、心が折れがち
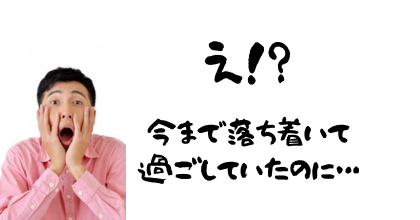
伝えたはずのことが全然違って伝わり、ご家族からクレームの電話。
さっきまで笑顔だった方が、突然怒り出して物を壊しだしてしまう。
「えっ、なんで!?」という予想外の連続に、気持ちがついていかなくなることも。
原因を探して分析する力は必要だけど、それでも全部は予測できない。そもそも、原因がわかったところで、壊れた備品がもとに戻るわけでもない。
「どうすればよかったの?」と自分を責めてしまうことも、少なくありません。
その行動を別な方向から捉えなおしてみる(=リフレーミング)と、見えてくるものもあるんですが、突発的な行動はどうしても精神的に堪えるものがあります。
【心の疲れ2】職員間の「価値観のズレ」で消耗しがち
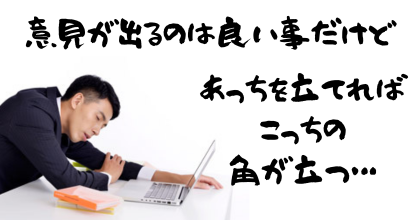
生活支援員同士で介護観や支援スタイルが違うと、それだけでモヤモヤの種に。上下関係などが絡んでくると、それだけで神経をゴリゴリとすり減らしてしまいます。
◆私はじっくり待つタイプだけど、上司は気づいたらすぐに手を出すタイプ
◆A支援員は業務の効率を優先したいけど、私は個別対応を重視したい
どちらが正しいというより、1つのチームとして価値観のズレをすり合わせる難しさに、気疲れしてしまいます。特に、より統一感のある支援が必要なケースでは、しんどさも倍増です。
また、支援の方向性だけでなく、会議の目的そのものがズレてしまっていた場合には、気疲れも倍増してしまいます。
【心の疲れ3】アンテナを貼りっぱなしになりがち
「言葉にならない言葉」に耳を傾けること。
それが、支援でいちばん大切で、いちばん大変なこと。
常に「気づこう」とアンテナを張っている私たちの脳内は、いつもフル稼働。
その“考え続ける疲れ”が、じわじわ心にたまっていくんです。
たとえば――
汗ばむ陽気の日に、厚着をしているご利用者さんがいたとします。
つい「暑かったら脱ぐはず」と思ってしまいがちですが、実際には、
- 暑いと言いだせない
- 暑さ寒さの感覚がわかりにくい
- 決まった服を着ないと不安になる
- 「暑い」→「脱ぐ」がつながらない
- 脱ぎ方がわからない
――そんな背景が隠れていることもあります。「もしかしたら本音を話してくれていないかも」という不安を抱きながら、常にアンテナを貼りっぱなしになることも少なくありません。
【体の疲れ1】常に腰痛リスクを抱えがち
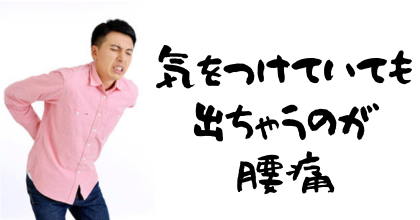
トイレ介助、移乗介助、入浴支援…。
現場の業務はどれも腰に負担がかかる作業ばかり。
一度腰を痛めると完全復帰は難しいため、日々のケアや声かけで予防するしかないんですが、どれだけ気をつけていても、疲れは溜まっていきます。
急な外出支援、慣れない坂道で車椅子を押した日には、身体だけでなく心もどっと疲れてしまいます。
【体の疲れ2】研修・会議で“座ってばかり”の疲れもある
生活支援員の仕事は体力勝負…と思われがちですが、実は「座りっぱなし」の時間も多いんです。
・ケース会議や事例検討会への参加
・対面研修やオンライン研修
・記録業務や報告書作成
これらが重なると、1日中ほとんど立ち上がれない日も。特に対面形式での研修は、内容によっては時間が長いこともあり、硬めの椅子だった日には辛さ倍増。
動きっぱなしでの疲れとは違って、腰や肩のコリがジワジワと溜まるのがこの疲れ。
「座ってるだけでしょ」と思われやすいけれど、じつは地味にしんどいんです。
ご利用者さんの区分認定調査に同席したときには、緊張感も相まって余計に疲れてしまいます。
【体の疲れ3】イベントやレクで、から元気になりがち
お花見、ハロウィン、クリスマス会――
季節のイベントやレクリエーションは、ご利用者さんにとって大切な楽しみのひとつ。
だからこそ、「笑顔になってもらいたい!」「楽しい時間にしたい!」と、
生活支援員の私たちは、ついテンション高めになりがちです。
でも実はこれ、心も体もごっそり削られてる。
- 普段より多めの準備と片づけ
- 慣れない司会進行やゲーム進行
- その場を盛り上げ続ける気疲れ
終わったあと、どっと疲れが押し寄せてくるのは当然です。
「楽しんでもらいたい」という気持ちは本物。でも、無理して笑顔になっている自分もいるんです。対応できるスキルをみにつけても、「何かやってほしい」という無茶振りはしんどいものです。
☕だからこそ、セルフケアが大切です
今回は、生活支援員として感じるリアルな「心と体の疲れあるある」をお伝えしました。そして、私が一番伝えたいのは”セルフケアの大切さ”です。
厚生労働省のこちらの記事でも、自分自身の小さなSOSに気づくことの大切さについて書かれています。「気持ちを紙に書く」「腹式呼吸を繰り返す」など、わかりやすい対処方法も載っているのでおすすめです👇️
無理して「がんばらなきゃ」と思わないでください。
「わかるよ」と言ってくれる人が、ここにいますから。
【生活支援員のためのセルフケア】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。
生活介護事業所で15年働く、現役の生活支援員です。小学校第1種教員免許や、介護福祉士、ケアマネージャーの資格を持っています。
でも実は、常に第一線で働いてきたわけではありません。調子を崩して、専門家の力を借りながら立て直した時期もあります。
その経験から、「セルフケアって大事だな」と実感するようになりました。
このカテゴリでは、あの時の経験が誰かの役に立てればという願いを込めて、“体をいたわる支援のしかた”や、“ちょっとした整え方”を、私なりの言葉でまとめています。

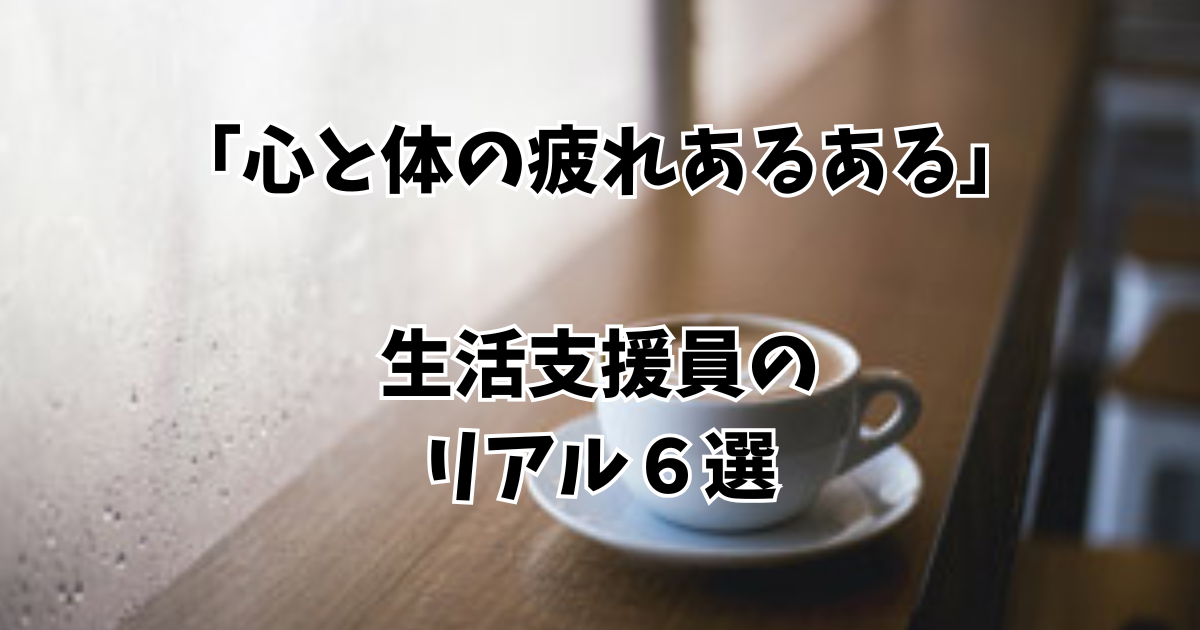
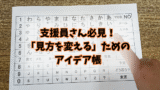
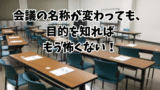
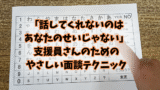
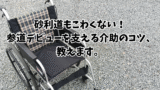
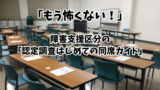
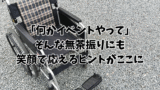
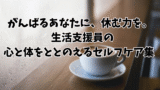


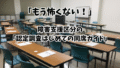
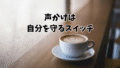
コメント