生活介護事業所の日中活動、生涯学習講座は私がおすすめしている活動の1つです。実は、生涯学習講座のやり方を工夫すれば、知識や教養が身につくだけでなく、ご利用者さんの支援のニーズに応えることができるんです。
この記事は、

・「言葉を増やしたい」と考えているご本人さん
・支援と学びを組み合わせたい生活支援員さん
・サービス管理責任者さん
におすすめです。
自分の気持ちを自分の言葉で伝えるために
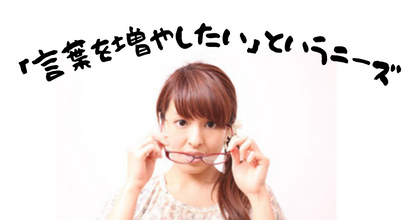
「言葉を増やしたい」
自分の気持ちをより的確に伝えるため、持っている言葉を増やしたいと希望される利用者さんやご家族さんが一定数います。
また、個別支援計画(その人がどんなことをしたいかをまとめた資料)を作成するうえで、言葉を増やすことを目標にすることもあるのではないでしょうか。
「学び」は生きる力になる!をテーマに、生涯学習講座を10年以上担当してきた私が、楽しく学びながら言葉を増やせるテーマをご紹介します。
⇒【関連記事】『生活介護事業所で生涯学習講座を実施するなら「〇〇系」がおすすめ』
「ぎなた読み」

今回ご紹介するテーマは「ぎなた読み」です。
「ここではきものをぬいでください」
という文章は、区切り方を変えると
- ここで、履き物を脱いでください
- ここでは、着物を脱いでください
という2つの読み方ができます。
「弁慶は、なぎなたを持って」を「弁慶はな、ぎなたを持って」と誤読した事が由来になっている言葉遊びです。
区切りを変えると読み方が変わるということを知ることで、自分では気づかなかった表現に気づくことができ、楽しみながら言葉を増やすことにつなげるのが狙いです。
⇒【関連記事】『福祉の現場でのリフレーミングとは?ポジティブシンキングとの違いを解説』
講座の流れ

「これは何と読むでしょう?」という問いかけから、ホワイトボードに例題を書いていきます。
すべてひらがなで書くのがポイントです。
「ここではきものをぬいでください」
もし、「ここで、履き物を脱いでください」しか出なかった場合は、「私は服を脱いでという意味かと思ったんですが…」と返すことで、もう1つの意味に気づいてもらえるかもしれません。
私の経験上、言葉を増やすための勉強というよりも、「区切りを変えると意味が変わる事を楽しむ」というスタンスで、気づいたら使える言葉が増えていたという感じのほうが、ご利用者さんの取っ掛かりが良いです。
ご利用者さんのセンスが光る回答例
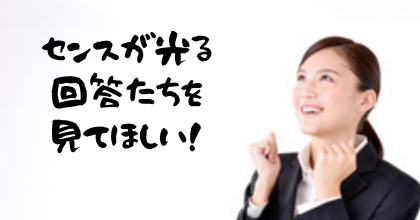
ここからは例題をいくつか挙げていきます。最初は、私が講座をしている中で、実際に出た『予想外の回答』をご紹介します。
くるまでまとう
⇒「車で、待とう」「来るまで、待とう」
※「車で纏う」という読み方をしたご利用者さんがいました。私も考えていなかった回答です。アッパレ!
とうさんのかいしゃ
⇒「倒産の会社」「父さんの会社」
※「とうさんのか、医者」と区切って読んでくれたご利用者さん。「通さんのか(とおさんのか)」が正しいんですが、思わず唸ってしまう回答でした。
こいものがたり
⇒「恋物語」「濃い物語」
※「来い、物語」という回答が出たことがあります。意味が通るかどうかではなく、決意が素晴らしいです。
なんかいがいい
⇒「何階がいい?」「南海がいい」
※「難解がいい」「何か、胃が良い」という名回答をいただきました。
例題:難易度【低】
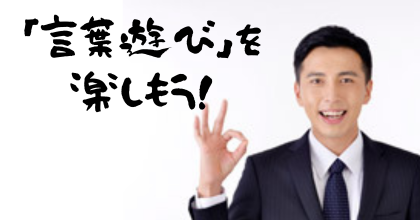
続いては、「は」を「わ」と読み替えたりせず、区切りを変えるだけで意味が変わる言葉を集めました。難しく感じてしまうかもしれませんが、正解することだけを目的にせず、気楽に回答してもらいましょう。
だれかいたの
⇒「誰か、いたの?」「誰? 書いたの」
かがみにきた
⇒「加賀、見に来た」「蚊が、見に来た」「鏡に来た」
おれにくいや
⇒「俺、肉イヤ」「折れにくい、矢」
にらみつけた
⇒「睨みつけた」「ニラ、見つけた」
きょうふのみそしる
⇒「今日、麩の味噌汁」「恐怖の味噌汁」
うみにいるかのたいぐん
⇒「海に、イルカの大群」「海にいる、蚊の大群」
おそらくもっています
⇒「おそらく、持っています」「お空、くもっています」
きょうならいきます
⇒「今日、奈良行きます」「今日なら、行きます」
きょうとかならいきます
⇒「京都か、奈良行きます」「今日とかなら、行きます」
さとうさんじゅうはっさい
⇒「佐藤さん、18歳」「佐藤、38歳」
たなかさんにひゃくえんかして
⇒「田中さん、二百円貸して」「田中さんに、百円貸して」
さかなのにおいついた
⇒「魚の匂い、ついた」「坂なのに、追いついた」
例題:難易度【やや高】
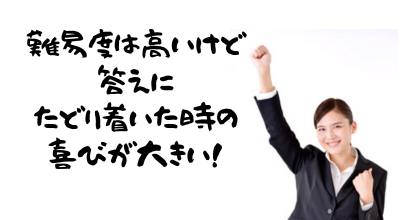
続いては、区切りだけでなく、音の読み方も変わるものです。難易度は上がりますが、難しいことをやってみるというのも大切な経験です。
ふろにはいるか
⇒「風呂に、入るか」「風呂には、イルカ」「風呂には、居るか」
のろいのはかばだ
⇒「呪いの、墓場だ」「ノロいのは、カバだ」
ここではねよう
⇒「ここでは、寝よう」「ここで、跳ねよう」
きみはしらないでいいよ
⇒「君は、知らないでいいよ」「君、走らないでいいよ」
あくのじゅうじか
⇒「悪の十字架」「開くの、10時か」
きょうはいしゃにいくよ
⇒「今日は、医者に行くよ」「今日、歯医者に行くよ」
講座中のポイント
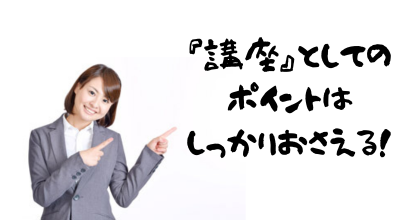
この講座に限らずですが、ご利用者さんから「正解ではない回答」が出ることがあります。それを肯定的に受け止めることが何よりも大切です。
中には、間違ってしまうことを極端に嫌ったり、正解ではない回答をした人を笑ってしまう人がいますが、それでは意見が出にくくなってしまいます。
「〇〇さん(講座の担当者)は、どんな意見でも『いいね!』と言ってくれる」という流れが浸透すれば、たくさんの意見が出る講座になります。
そしてもう1つ、言葉遊びとしては面白いのかもしれませんが、『講座』であることを意識した出題を心がけることも大切です。
ウケ狙いで「うんこのけーきおいしい」というのは出さないほうがいいと思いますし、「ゆでたまごたべる」など、不適切な表現になりかねないものは出題しない工夫が『講座』としての質を保つのに必要です。
⇒【関連記事】『生涯学習:ご利用者さんをググっと惹きつける「私の鉄板ネタ」』
まとめ
今回は「言葉を増やしたい」を叶える生涯学習講座のテーマということで、『ぎなた読み』を取り上げました。
- 言葉遊びを楽しみながら、言葉が増えていくことが目的
- 他の人の意見を聞くことも大切
- 講師は肯定的な受け答えを意識しよう
最後にお伝えしたいのは、一瞬で結果が出る魔法のような支援は存在しないということです。(あるのかもしれませんが、私は出会ったことがありません。)
言葉を増やすための支援を実施しても、100%上手くいくことが保証されているわけではありませんが、「結果が出なかった」ということも1つの結果です。
まずは、「学び」を通じてご利用者さんに楽しい時間を過ごしてもらうことを意識して、スモールステップで取り組んでいきましょう。

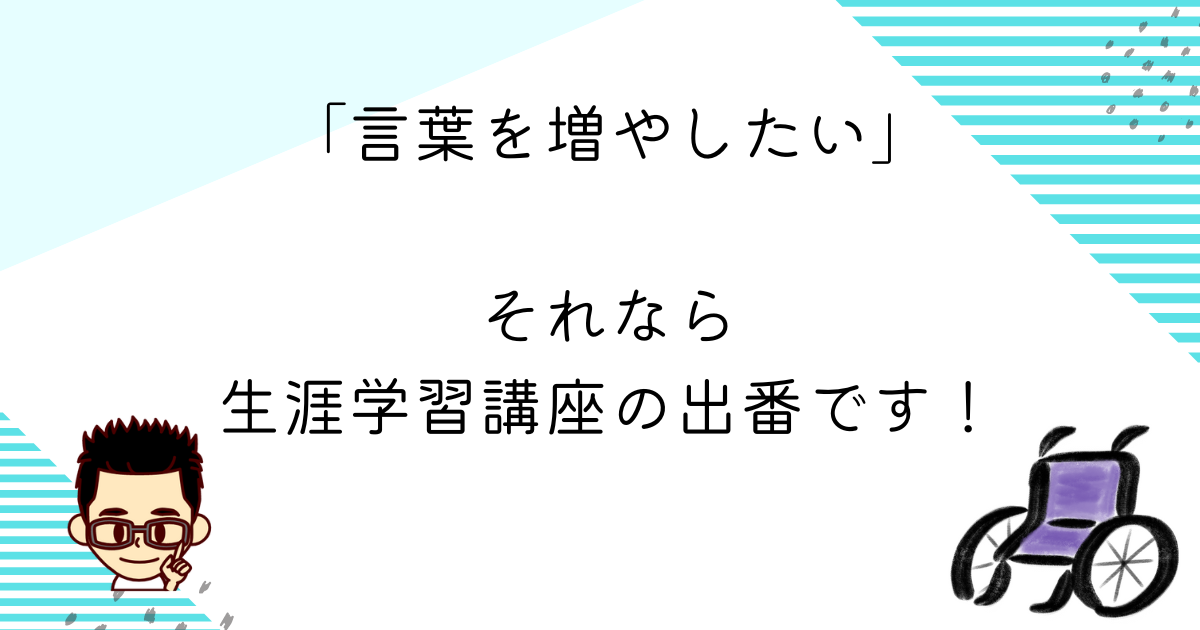


コメント