ご利用者さんのニーズの多様化に伴い、生活介護事業所の日中活動の重要性は日々高まっていると実感しています。私がおすすめしている「生涯学習講座」は、工夫次第でご利用者さんの興味や関心に広くアプローチできる可能性を秘めています。
- 新人職員でも実施しやすいジャンルはあるの?
- ご利用者さんにウケの良いテーマを知りたい
- メリット、デメリットの両方を教えて
「生涯学習講座をやってみたいけど、具体的にどんな講座をすればいいか全くイメージできない。」そう思っている生活支援員さんのために、今日は私が実際に担当している講座の中から、おすすめのジャンルをご紹介します。
この記事は
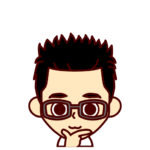
・日中活動を担当している職員さん
・1対複数の関わりが得意な生活支援員さん
・特色ある施設運営に興味がある管理者さん
におすすめです。
実施のためのハードルは、決して低くないのが現実です。ですが、少しでも多くの人に生涯学習の魅力を知ってもらい、ご利用者さんに「学ぶ楽しさ」「分かる喜び」を味わってもらうため、ぜひ最後まで読んでほしいです。
「学び」は生きる力になる

生活支援員として働いていると、行きたい場所がバリアフリーに対応していない「アクセスの問題」や、必要なサポート方法がわからない「サポートの不足」など、障害のある人の経験値がどうしても少なくなってしまいがちだなと思うことがたくさんあります。
そして、今の職場で10年以上生涯学習講座に携わってきて感じるのは、「わかった!」というご利用者さんの笑顔が何よりも素晴らしいということです。
学ぶことが楽しい、と思えることは「生きる力」になります。
私が生活介護事業所の日中活動で生涯学習講座をおすすめする理由については、こちらをぜひご覧ください。
⇒【関連記事】『生活介護事業所の特色を出すなら、「生涯学習講座」が超おすすめです』
おすすめの「〇〇系」講座
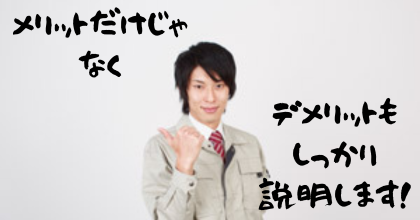
現在、私は5種類の生涯学習講座を担当しています。現在は実施していないものも含めると、10種類近くの講座を担当してきた事になります。その中から、おすすめのジャンルを2つご紹介します。
メリットはもちろん、デメリットについても書いていくので、現場人間のリアルな意見を是非参考にしてみてください。
国語(ことば)系
最初におすすめするのは「国語」、特に「ことば」に関するテーマを扱う講座です。非常に広いテーマですが、それゆえに汎用性が高く、ご利用者さんのニーズに合わせやすいという特徴があります。
メリット①年中行事からヒントが得られる
お正月や節分いった日本の伝統的な年中行事は、その由来を調べるだけで立派な講座として成立します。
七夕飾りを作って飾る施設はたくさんあるかもしれませんが、「七夕飾りの由来を調べたり、世界の星に関するお祭りについて学ぶ」という講座をやっているのは、かなり特別感があると思います。
メリット②別テーマの講座に発展させやすい
国語系、特に「ことば」をテーマにした生涯学習講座は、ご利用者さんの興味の広がりに応じて、他の種類の講座に発展させやすいというメリットがあります。
例えば、「年賀状について学ぶ」というテーマから、「手紙の歴史」⇒「いろいろな物の歴史」という風に発展させていくことが可能です。
日本史や世界史を学ぶ社会科の講座を作るのも面白いですね。
メリット③個別支援計画と連動させやすい
「ことば」をテーマにした生涯学習講座は、ご利用者さんの個別支援計画と連動させやすいというメリットがあります。
例えば、「自分の気持ちを言葉で伝えられるようになりたい」という目標があったとして、生涯学習講座で語彙を増やせるゲームなどを実施すると行った具合です。
生涯学習講座単体で実施するのではなく、工夫次第で途切れることのない支援の循環を作っていくことが可能です。
デメリット①「学校感」が苦手な人には参加のハードルが上がりがち
ご利用者さんによっては、学校に良い思い出を持っていなかったり、「学ぶ」ことに対して抵抗感のある場合があります。
国語系の講座は、どうしても「学校感」が出るので、苦手なご利用者さんにとっては参加のハードルが上がってしまいがちです。
「楽しい」と感じてもらうことができれば、継続的に参加してもらえるチャンスなので、まずは見学してもらうところからスタートするなどの方法で対応できるかもしれません。
思い切って講座の名前を変更するのも、学校っぽさを出しにくくする1つの方法です。
デメリット②ある程度先を予想した準備が必要
国語系の講座に限ったことではありませんが、学びを前提としているので、ある程度先を予想した事前の準備が必要です。
具体的には、そのテーマについてどんな質問が来るかを予想し、それに対する答えを調べておきます。参加してくれるご利用者さんを思い浮かべながらやってみて下さい。
決してすべての質問を先回りして調べなければならないわけではありません。わからないことは保留して、次回までに調べておいたり、「ご利用者さんと一緒に調べる」というのも1つの方法です。
デメリット③ホワイトボードがほぼ必須アイテム
講座の要点を書いたり、ご利用者さんから出た意見を書く時に、ホワイトボードが必要になります。あると便利というレベルではなく、ほぼ必須です。
施設内のスペースの問題がありますが、会議室においてあるくらいのサイズが理想です。どうしても用意できない場合は、100円ショップで購入できるサイズのものを複数個用意しておく方法をおすすめします。
算数系
続いておすすめするのは算数系の講座です。デメリットに関しては国語系とほぼ共通しているので、実施のメリットを3つ挙げます。
メリット①日常生活のスキルに結びつけやすい
- 時計が読めるようになりたい
- お金の計算ができるようになりたい
- 「半分」「三等分」といった「分ける概念」を覚えたい
など、ご利用者さんの日常生活で身につけたいニーズと結びつけやすいのが最大のメリットです。
算数系の講座は、学ぶことを楽しみ、さらに日常生活のスキル獲得にもつながる可能性を秘めています。
メリット②「なぜ?」からスタートさせやすい
関連記事でも触れていますが、生涯学習講座には『W・I・N =(わかった!・いいね!・なぜ?)』という3つの要素が大切だと考えています。
- なぜ「イチかけるゼロ」はゼロなの?
- 1年は何秒?
- 奇数と偶数って何?
など、算数系の講座は、特に「なぜ?」からスタートさせやすいので、講座の導入部分でご利用者さんの気持ちをつかみやすいです。
メリット③結果を目に見える形で示しやすい
障害特性によっては、目に見えないものを理解することが苦手なご利用者さんがいます。
- 正方形の紙を、正方形のまま半分のサイズにする
- 1〜100までの数字の中から「素数」を探す
- 折り紙1枚の重さを測る
など、算数系の講座は、結果を目に見える形で示しやすいテーマを扱えるのが強みです。
まとめ
今回は、「生活介護事業所で生涯学習講座をするなら」というテーマで、おすすめのジャンルを2つご紹介しました。
- 国語系・算数系がおすすめ
- もちろんデメリットもある
- 学ぶことは「生きる力になる」
最後にお伝えしたいのは、「難しそう」「できない」と思い込むのではなく、『どうやったら学ぶことを楽しんでもらえるか』というマインドを持ってほしいということです。
難しく考える必要はありません。学校の先生をお手本にする必要もありません。ご利用者さんたちが、長時間の講座に参加するのが苦手な場合は、15分くらいの短い時間で実施しても構いません。
もし、一人で担当することが負担に感じるようであれば、複数名で実施するなど、チームでの連携を意識しながら取り組んでみてほしいです。ご利用者さんの「わかった!」という笑顔に出会える素敵な時間、それが生活介護事業所の生涯学習講座です。

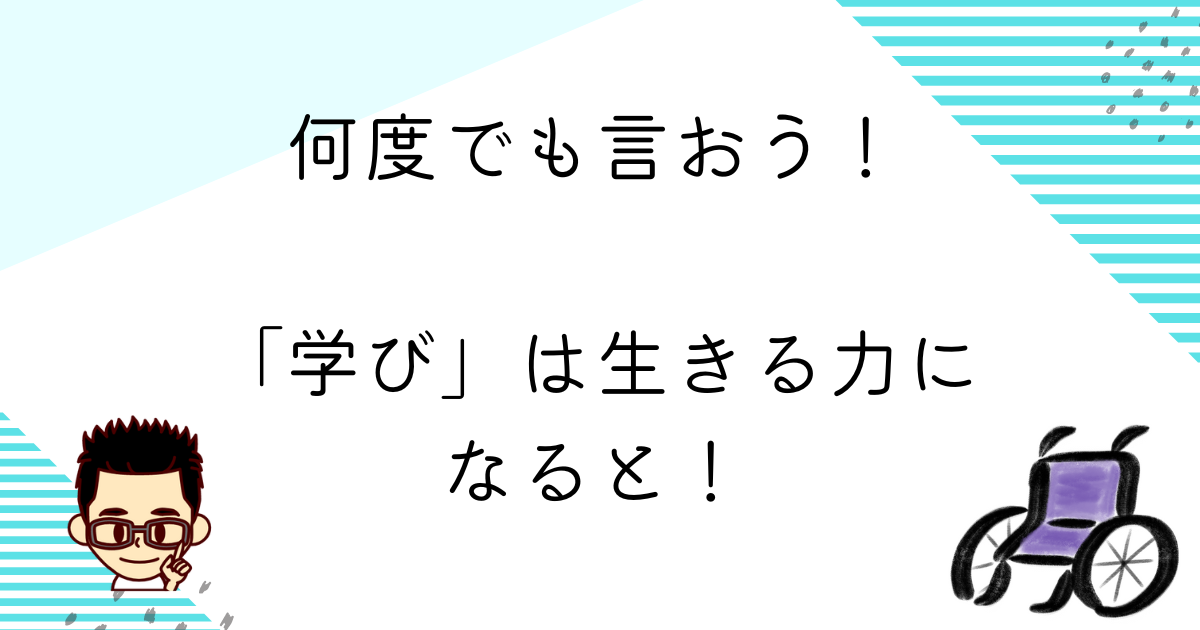


コメント