生活介護事業所での日中活動において、読書は驚くほどの魅力があるアクティビティです。ですが、ご利用者さんが心おきなく読書を楽しむためには、本の扉を開く前に立ちはだかる「バリア」を『クリア』にする必要があります。
- 両手に力が入らず、ページを開いて持つことができない
- 視覚に障害があり、墨字の本が読みたくても読めない
- 車いすに身体を固定しているので、視界が狭い
今回は、生活介護事業所で15年間、読書の日中活動に関わってきた私が、「バリア」を『クリア』にする鍵を余すところなくご紹介します。私が経験してきた事例をもとに、現役の生活支援員(介護士)だからこそ書ける具体的なアイデア満載でお届けします。
この記事は、
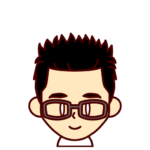
・読書の活動を提供したい生活支援員さん
・事例を探している職員さん
・生活介護事業所の読書事情が知りたい人
におすすめです。
日中活動としての読書の魅力

生活介護事業所では、ご利用者さんの特性に合わせて様々な日中活動を提供しています。内容は施設によって特色がありますが、読書の時間もそのうちの1つです。
⇒【関連記事】『日中の充実をサポート! 生活介護事業所で人気のアクティビティまとめ』
私も、職場でご利用者さんへの日中活動として、読書の時間を担当しています。「自分の人生を『読書に使う』というプレミアムな時間を味わう」をコンセプトに、参加を希望するご利用者さんが、それぞれ読みたい本を読んでいます。
生活介護事業所の日中活動としての読書の魅力は、次のようなものが挙げられます。
- 色々な考えに触れることができる
- 知識や教養が身につく
- 読みたい本を買いに行く「外出活動」に繋がる
私が生活支援員として働いていて感じるのは、ご利用者さんの経験がどうしても少なくなってしまいがちということです。読書を通じて、様々な人の考えに触れることができたり、「本を買いに行く」という経験に繋がることは、本当に大切なことだと考えています。
事例1 両手に力を入れることが苦手なAさん

Aさんは、60代の女性です。麻痺があるわけではありませんが、力が入りづらいため、両手足を自由に動かせません。普段から車いすを利用して生活しています。
Aさんの「バリア」
車いすを利用した状態でテーブルに付いた場合、右手は自分の力で机の上に乗せることができますが、左手は、右手で支えるようにして、ようやく乗せることができます。
写真のように、本を手で持ったまま読むことはできず、机の上に本を広げておいても、ページを開いたまま持っておくことは極めて難しい状況です。
こうやって『クリア』にした
ダイソーで、「ワイヤーブックスタンド」という商品を買ってきました。メイクをする時に使う卓上ミラーくらいの角度で、本を開いた状態で立てかけることができます。
ページをめくるときは、近くにいる支援者に声をかければOKなので、周囲に気を遣うことなく自分のペースで本を楽しむことができるようになりました。
ちなみにAさんは幅広いジャンルの本を読みますが、中でも小説がお好きです。「ワイヤーブックスタンド」は、ソフトカバーの文庫本などにも対応できるので重宝しています。
唯一弱点をあげるとしたら、本を置く部分のワイヤーの幅の関係で、500ページを超えるハードカバーの本が固定しにくいことでしょうか。
⇒【関連記事】『福祉施設の行事と、100円ショップが相性抜群の理由』
事例2 視覚に障害があるBさん

Bさんは50代の女性です。2歳の頃に全盲になり、左半身に麻痺があります。点字を読むことができ、使い方を覚えれば、テレビやラジオの視聴や、携帯電話の操作なども可能です。
Bさんの「バリア」
点字を読むことができますが、点訳された本の種類が限られています。私がある程度点字を覚えているので、Bさんが読みたい本を点訳することが可能でしたが、技術面と時間的な関係で「Bさんの読みたいペースでの実施」が困難な状況でした。
⇒【関連記事】『生活介護事業所の職員が語る、5つの「点字の魅力」とは?』
こうやって『クリア』にした
点訳には時間がかかるので、文学作品を朗読したCDを聞いてもらうことにしました。CDプレーヤーの操作をBさんに覚えてもらい、イヤホンを付けてもらうことで、自分の好きなペースと音量で聞くことができるようになりました。
CDはBさん自身が購入し、ネットショップなどで商品を一緒に探す支援を実施しました。
Bさんは児童文学が好きで、ラジオやテレビで仕入れた情報をもとに、読みたい本を選んでいました。現在は施設の利用をやめ、自宅でゆっくり過ごしています。
その後、別なきっかけで「オーディオブック配信サービス」を知り、視覚に障害のある人の読書の可能性に大きな広がりを感じています。
事例3 視界が狭いCさん

Cさんは30代の男性です。筋ジストロフィーという難病で、ストレッチャー式の車いすを利用しています。ストレッチャー式の車椅子とは、「背もたれを大きく倒して、ベッドのようにできる車椅子」をイメージしてもらえれば大丈夫です。
Cさんのバリア
Cさんは自分で自分の姿勢を保つことができないため、車椅子を利用しているときは、身体と車椅子の背もたれ部分をベルトで固定しています。
拘縮(こうしゅく⇒関節が曲がらなくなる状態のこと)が進んでいるため、首を曲げることができず、背もたれを90度に起こしても、机の上の本を読むことはできません。
こうやって『クリア』にした
Cさんは2種類の方法で読書を楽しんでいます。
パターン1、顔の前に本を持ってくる
Cさんが本の読める位置に行くのではなく、本がCさんの読める位置に来るという状況を作ることにしました。
音楽の活動で使う譜面台があったので、それを利用することにしました。Cさんの顔の前に本を持ってくることで、自分のペースで本を読むことができるようになりました。
パターン2、横になって読む
Cさんの体調によっては、「本を読みたいけど座っているのが辛い」という状況になることがありました。
そこで、車椅子をベッドのような形状にし、Cさんには横を向いた状態で寝てもらうことにしました。その状態でパターン1の譜面台を使うことで、「座った状態でなくても本が読める」という状況を作ることができました。
Cさんは、ジャンルを問わず、1冊の本をじっくりと読んでいくタイプです。また、読んでいる本に関して意見交換をするのが好きで、よく私と一緒にお喋りしています。
まとめ
今回は、『生活介護事業所の「障害のある人の読書の楽しみ方」』というテーマで、実際の事例を元に「バリア」を『クリア』にする方法についてご紹介しました。
- 最小限の支援で「自分のペースで読む時間」を作る
- 「見る読書」だけでなく「聴く読書」もある
- 「座って読む」だけが読書の時間ではない
最後にお伝えしたいのは、「どうやったら楽しめるか」というマインドで考えてほしいということです。譜面台のような、工夫次第で本が読めるようになる便利なツールが、アナタの身の回りにあるかもしれません。
また、「サポートがなければ読めない」のではなく、『サポートがあれば読める』ととらえることで、より前向きな支援を考えるきっかけになるのではないでしょうか。

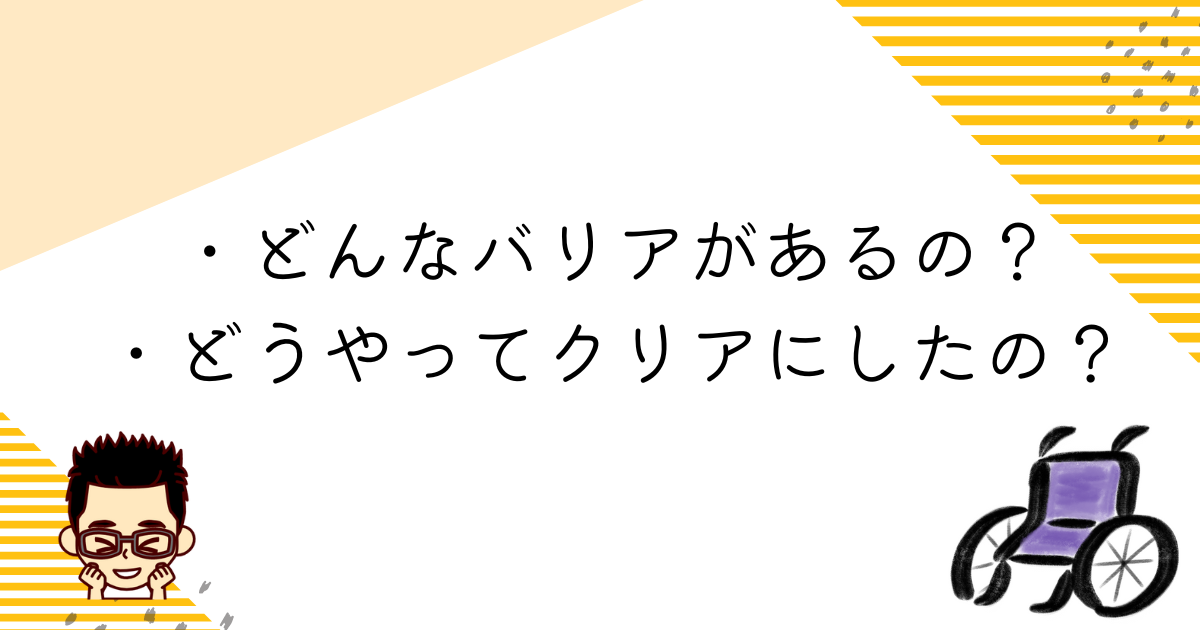


コメント