生活支援員として働いていて、「うちの施設の特色ってなんだろう?」と考えたことはありませんか? 「この施設だから利用したい」と思ってもらえるような魅力があることで、ご利用者さんの生活の満足度が向上するだけでなく、私たち生活支援員のより良いサービス提供にも繋がります。
- 生涯学習講座が何のことかよくわからない
- ご利用者さんにとって、難易度が高すぎない?
- 専門的な知識が必要なイメージがある
私自身、小学校の教員免許を持っていて、職場ではご利用者さんのための生涯学習講座を主催しています。今回は、特色ある施設運営のためのアイデアとして、生涯学習講座がおすすめの理由をご紹介していきます。
この記事は、

・生活介護事業所の管理者さん
・中堅〜ベテランの生活支援員さん
・生活介護事業所を利用したい当事者さん
生活介護事業所に特色は必要?
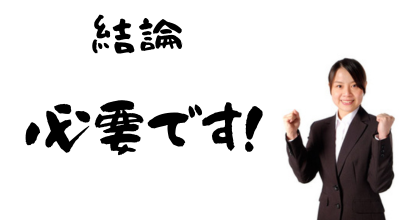
結論から言うと、生活介護事業所に特色は必要だと考えています。必ずしも「特別な日中活動」だけが特色というわけではなく、
・調理室があり、介護食の提供に強い
・年中無休で開所している
・入浴サービスに特化している
など、その施設の持ち味は様々です。ご利用者さん、職員さんの立場からそれぞれ必要な理由をご紹介します。
「施設を選ぶ基準になる」
ご利用者さんやご家族さんにとって、利用する施設を選ぶことは重要です。特に、ご利用者さんにとっては、立地条件や全体の雰囲気だけでなく、「自分がどんなことをしたいか」を実現する環境が整っているかというのがとても大切です。
「手先が器用なので、生産活動に参加したい」
「絵を描くことが好きなので、創作活動をたくさんしたい」
「体を動かすことが好きなので、運動のプログラムをやりたい」
など、施設の特色が明確であればあるほど、自分の可能性とのマッチングを考えやすくなります。
より良いサービス提供につながる
その生活介護事業所に、他の施設にはない魅力があれば、「ここで働いてみたい」という人が増える可能性があります。
また、職員1人1人が「自分たちの施設らしさ」を意識して働くことができるので、より良いサービスの提供につながります。
生涯学習とは
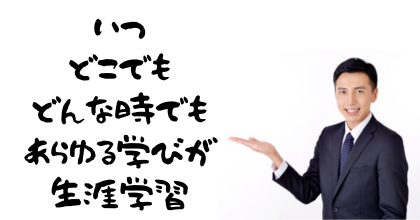
生涯学習とは、「人々が生涯に行うあらゆる学習」のことです。学校教育だけでなく、いつ・どこでも・どんな時でも学ぶことができるのが生涯学習です。
詳しくは文部可科学省のWebページを御覧ください。
⇒【参考】文部科学省:平成30年度文部科学白書『第3章 生涯学習社会の実現』
キーワードは『W・I・N』
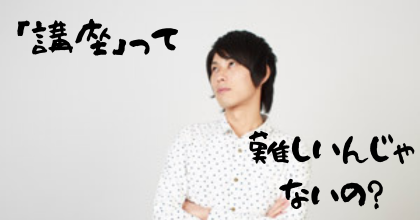
生活介護事業所の日中活動で生涯学習講座をする、と聞くと「難しい」というイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。私が生涯学習講座をする時に意識しているのは『W・I・N』です。
W ⇒ 「わかった!」(理解)
I ⇒ 「いいね!」(共感)
N ⇒ 「なぜ?」(疑問)
この「わかった!」「いいね!」「なぜ?」の要素があれば、立派な生涯学習講座として成立すると考えています。(あくまでも受け取り手の判断なので、押し付けにならないように注意してくださいね)
そしてそれが、他でもない「その施設でしか味わうことができない活動」=「施設の特色」になり得るのです。
生涯学習講座のメリット・デメリット
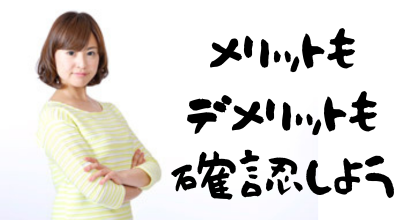
この章では、生活介護事業所の日中活動で生涯学習講座を実施するメリットとデメリットについてご紹介します。
メリット
経験値が増える
ご利用者さんによっては、障害特性の関係で、経験値がどうしても少なくなってしまう人がいます。生涯学習講座を通じて、経験する機会が増え、興味や感心の幅が広がります。
施設内で新しい経験ができる機会を増やすことができるのは、生活介護事業所で生涯学習講座を実施するメリットの1つです。
ご利用者さんの『強み』を発見するチャンスになる
生活介護事業所に限ったことではありませんが、ご利用者さんがどんな人かを知ることはとても重要です。中でも、「この人はどんな強みを持っているか」という部分が特に大切で、様々な角度からアプローチする必要があります。
生涯学習講座は、ご利用者さんの意外な『強み』を発見できる可能性を秘めています。
その他の日中活動とつなげることができる
これは生活介護事業所ならではのメリットです。例えば、「裁縫を学ぶ」という講座があったとして、講座の時間だけでなく、創作活動や余暇の時間にも取り入れることができます。
全体の活動から、個人の活動につなげることができ、それがご利用者さんの『強み』になる可能性を秘めているのは、生活介護事業所で生涯学習講座をするメリットであると言えます。
デメリット
主催者(講師)の心理的ハードルが高くなりがち
生涯学習「講座」なので、中心となって進める講師が必要になります。人前で何かをすることに抵抗がある人にとっては、心理的なハードルが高くなってしまいがちです。
人前で何かをするのが好きな人にやってもらったり、複数人でチームを組んでやるなどの方法が考えられます。
思い切って、外部講師を呼ぶというのも1つの方法です。
継続が難しい(単発の企画になりがち)
実際に生涯学習講座を主催していて、同じテーマで継続的に実施することに難しさを感じています。音楽や工芸など、継続的な実施に強いテーマを選ぶなどの方法で対策ができます。
「継続がむずかしいからやらない」という選択をするよりも、思い切って「単発の企画」として実施するのもアリですよ。
集団での活動が苦手なご利用者さんには不向き
決してご利用者さんが悪いわけではなく、システムと特性のマッチングの問題です。集団での活動が苦手なご利用者さんには、どうしても参加しにくいと感じてしまうかもしれません。
集団でやる形にこだわらず、1対1の活動として取り組むなどの方法でカバーが可能です。
職員の『強み』がそのまま講座になる
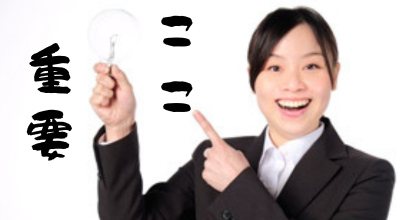
生活介護事業所の特色を打ち出せる可能性を秘めている生涯学習講座、最大のおすすめ理由が、職員の強みがそのまま講座になるということです。
もし、この記事を読んでいるアナタが、ピアノを弾くことができる人だったら、『ピアノの弾き方講座』や『合唱講座』などの時間を作るのはいかがでしょうか。
この章では、『ピアノの弾き方講座』先程のW・I・Nに当てはめながらアイデアを出してみましょう。
『ピアノの弾き方講座』
例①「音について学ぼう」
W(わかった!)⇒ 弾く場所によって音が違う!
I(いいね!)⇒ ピアノの音が好き!
N(なぜ?)⇒ どうして右に行くほど音が高くなるの? 他の楽器の仕組みと同じところや違うところは?
・「楽譜を読んでみよう」
W(わかった!)⇒ ドレミが読めた!
I(いいね!)⇒ もっと色々な曲を読んでみたい
N(なぜ?)⇒ なぜ音符の形が違うの?
・「オリジナルソングを作ってみよう」
W(わかった!)⇒ 曲が出来上がるまでのプロセスがわかった!
I(いいね!)⇒ 〇〇さんの歌詞が素敵!
N(なぜ?)⇒ 「楽しい感じ」と「悲しい感じ」があるのはなぜ?(長調と短調)
ピアノを弾くだけではなく、理解・共感・疑問の要素を取り入れることで、一気に生涯学習講座らしくなります。最初から無理にすべての要素を取り入れる必要はありません。
主催者の思いを押し付ける形になってはいけませんが、参加してくれるご利用者さんの理解度に合わせて、ある程度のガイドが必要になる場合も多いです。
何より大切なのは「自分の『強み』を活かして、ご利用者さんと楽しい時間を過ごすこと」です。
まとめ
今回は「生活介護事業所の特色を打ち出すなら、生涯学習講座がおすすめ」というテーマで、生涯学習講座に必要な3つの視点や、実施のメリット・デメリットについてご紹介しました。
- 施設の特色は、ご利用者さんにとって施設を選ぶ基準になる
- 理解・共感・疑問の3要素で、一気に生涯学習講座らしくなる
- 職員の『強み』がそのまま講座になる
あくまでも私自身の経験ですが、生涯学習講座をウリにしている施設は決して多くないという印象です。つまり、他の施設との差をつけやすいジャンルだということです。
「講座=勉強=硬い感じ」という思い込みにとらわれず、参加してくれているご利用者さんと楽しい時間を過ごすことが最初のステップです。施設の特色を全面に押し出して、ご利用者さんにとっても職員にとっても、良い循環を作っていきましょう。

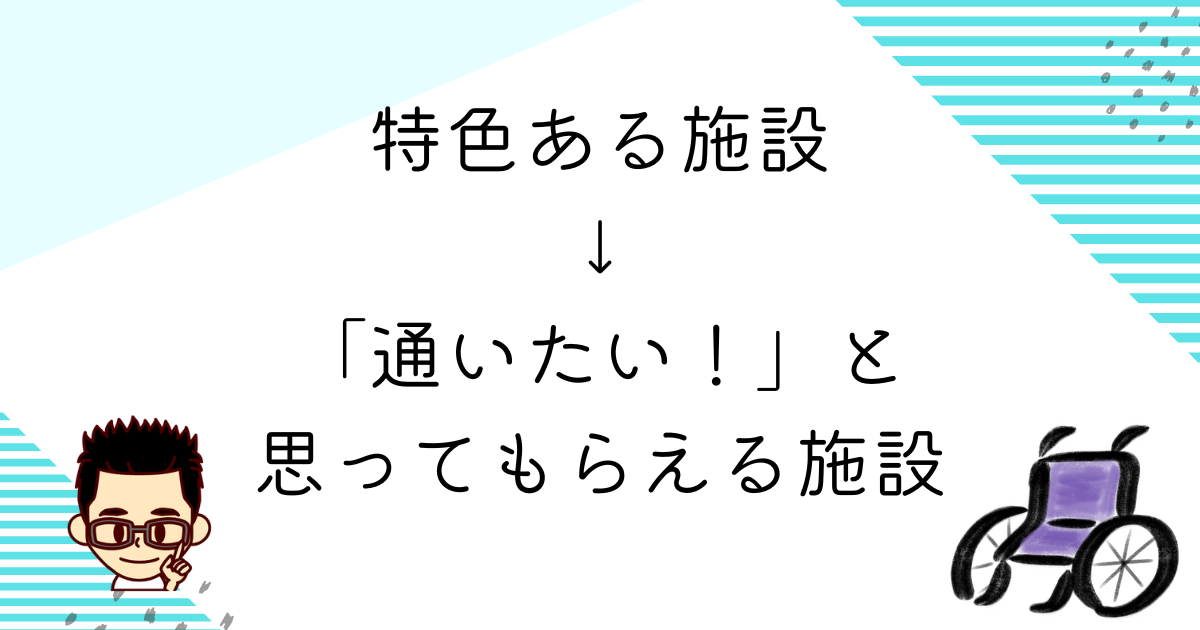


コメント