「明日は〇〇の研修か…気が重いな」そう感じているのは、きっとあなただけではないかもしれません。
この記事は、
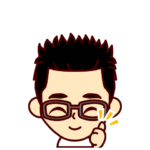
・研修が苦手な生活支援員さん
・参加したくなる研修を企画したい職員さん
におすすめです。
支援に必要な知識を獲得したり、その分野の最新情報を手に入れるために、研修は必要不可欠なものです。それはわかっているんですが…どうにも消えない苦手意識。
その最大の理由は「面白くないから」ではありませんか?
15年近くこの業界で働くなかで、様々な研修に参加してきました。その中で、私なりにたどり着いた「研修が面白くない理由」と、「こうすればもっと研修を受けたくなる!」というアイデアをたっぷりご紹介します。
「ここが面白くない」と感じてしまうポイント3つ
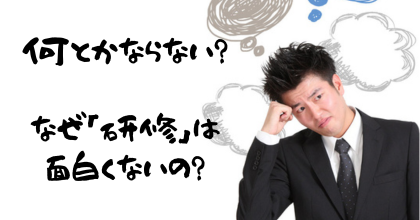
「研修」といっても、そのスタイルは様々です。講義形式、演習中心、最近ではオンラインで参加できる研修も増え、遠方で実施される研修にも参加しやすくなりました。
私は年間3〜4回(タイミングがあればもっと参加する年もあります)研修に参加する、職場でも自他ともに認める「研修マニア」です。
研修に行く頻度が少なくないからこそ、「ああ、今回もこのタイプの研修か」と思ってしまうことがあるんです。そんな私が感じてしまう「面白くない」ポイントを3つご紹介します。
配布資料を見たら「研修の中身」が100%わかってしまう

受付で、「スライドが全ページ印刷された配布資料」をもらった経験はありませんか? 一生懸命準備していただいた方には本当に申し訳ないんですが、これを参加者全員分用意する必要はないと思っています。
その資料を読めば、開始数分で「今日やる勉強の全体像」が見えてしまうんです。アニメで例えたら、予告で内容が100%わかってしまうみたいなものです。
これでは「今日は何を学ぶのだろう」というワクワク感がなくなってしまいます。先の展開がわかっているアニメが面白くないのと同じ理由で、結論が配布されている資料を見ながら受ける研修は、面白くないと感じてしまいます。
視覚にハンデがあって、スライドを見ることが苦手な人もいると思うので、「スライドを全ページ印刷した資料を作る」という仕組みそのものは必要です。
その仕組みを残しつつ、より良くできるアイデアについては次章でご紹介します。
「理解が追いついているか」の確認がないまま話が進んでしまいがち

講師の先生の話を聞いているけど、専門用語が多すぎて「あれ? もしかして自分は場違いな所にいる?」と感じてしまったことはありませんか?
「わからない」が『わかる』ようになることはとても素晴らしいことです。逆に言えば、「わからない」が『わかる』ようになるための研修なわけです。
わからない専門用語が出てきたまま研修が進行すると、理解が追いつかなくなってしまいます。そうかといって、その場で「今のはなんですか?」と手を挙げて聞ける雰囲気でもない。隣の人にこっそり聴くわけにもいかず、携帯を取り出すのはマナー違反…。
限られた時間でたくさんの情報を正確に伝えるためには、専門用語は不可欠です。この部分を補うアイデアは次章で扱います。
1回で伝えられる情報量が多すぎる

研修のカリキュラムを考えていただいている主催者さんには本当に申し訳ありませんが、1回あたりの研修で扱う情報量が多すぎませんか?
資格取得のための研修などについては、指定されたカリキュラムに沿って時間配分が決められている場合もあります。
やはり、1回あたりの研修時間が長く、扱う情報量が多すぎると、疲労が蓄積して集中力が低下してしまいます。その結果、「学びたい」という意欲が低下し、「面白くない」と感じてしまいます。
こうすればもっと受けたくなる!

「研修に面白さは必要なのか?」
「研修なんだから、多少の窮屈さはあるはずだ」
という意見をお持ちの方もいらしゃるでしょう。ごもっともだと思います。では、研修に面白さは不要なのでしょうか? 私は明確にNO!と答えます。
私自身「学び」は生きる力になる!をテーマに、障害のあるご利用者さんのための生涯学習講座を行っています。その根底には、「学び通じて楽しい時間を過ごしてもらいたい」という気持ちがあります。
この章では、こうすれば研修に参加したくなる!というアイデアを3つご紹介します。
①「講師の顔を見て話を聞く時間」を増やす

最初に提案したいのは、「講師の顔を見て話を聞ける時間」を増やすことです。配布資料があると、顔が下を向いてしまいます。
私自身、生涯学習講座を担当しているのでわかるんですが、ご利用者さんが自分の方を見て話を聞いてくれていると、とてもやる気が出ます。
研修でも、講師の顔を見て話を聞ける時間が増えれば、受講者だけでなく講師のやる気もアップして、研修全体のクオリティが上がる効果が期待できます。
そのためには、「スライドが全ページ印刷された資料の事前配布」ではなく、レジュメと記録用ノートを配布するのはどうでしょうか。
ただ、前章でも触れましたが、視覚にハンデがありスライドを見るのが苦手な人もいます。そのため、受付の段階から資料が必要かどうかを確認し、希望者のみに配布するなどの工夫があれば良いと思います。
もし、どうしてもスライドを印刷した配布資料が必要(ルールが決まっている等)であれば、研修の終わりに「振り返りの資料」として配布する方法でカバーできます。
②「理解の確認」=「対話」を増やす

これは①とも大きく関わってきます。「講師の顔を見て話を聞くことができる」ということは、講師から見て「受講者のリアクションを確認できる」ということです。
以前、ご利用者さんに協力してもらってある実験をしたことがあります。カメラとモニターを用意し、ご利用者さんの表情が見えない状況を作って、別室から生涯学習講座を行いました。
この時に痛感したのは、「講師と受講者が視線を合わせる」ことの大切さです。
表情や空気による「対話」が生まれることのメリットは計り知れません。受講者のリアクションで、講師は全体の理解度などを把握することができます。対話が増えれば、研修がより充実したものになります。
配布資料に目線を落としていては、講師の「人としての温度」を感じ取ることは出来ません。
③「1回1時間」でシリーズ化する

これに関しては「ルール上どうしてもそうせざるを得ない」という部分が大きいのかもしれませんが、そうでなければ「1回1時間」でシリーズ化するのはどうでしょうか?
1回4時間で4テーマ扱うのではなく、1回1時間で4回やるみたいな感じです。
1回の研修時間を短くする工夫と併せて、1回に伝える情報量を見直すことも大切です。「60分の講義で、スライドの枚数が70枚近くあった」という研修に参加したこともあります。計算するとスライド1枚あたり1分以内で話すことになります。
研修を主催する人の業務負担などの問題はありますが、「少ない回数で一気に」から「回数を増やして少しずつ」にシフトするのも1つの方法ではないでしょうか。
まとめ
今回は「なぜ福祉施設の研修が面白くないのか?」というテーマで、研修が面白くないと感じる理由や、こうすればもっと参加したくなるというアイデアをご紹介しました。
- わからないが『わかった!』になるのが研修の醍醐味
- 言葉のやり取りだけが「対話」ではない
- 研修の仕組みそのものを見直すことも大切
福祉の研修はどうしても「面白くない」と感じてしまいやすい要素が揃ってしまっているのが現状です。法令法規の確認や、心理学などの専門的な知識を要するテーマにも触れるため、難しいと感じてしまうことが多いです。
「だから面白くないままでいい」のではなく、『その中でどうすれば面白くなるか』を考えることが大切です。日々の業務に追われる中、時間を捻出して参加する研修が実りあるものになるよう、これからも学びの大切さを発信していきます。

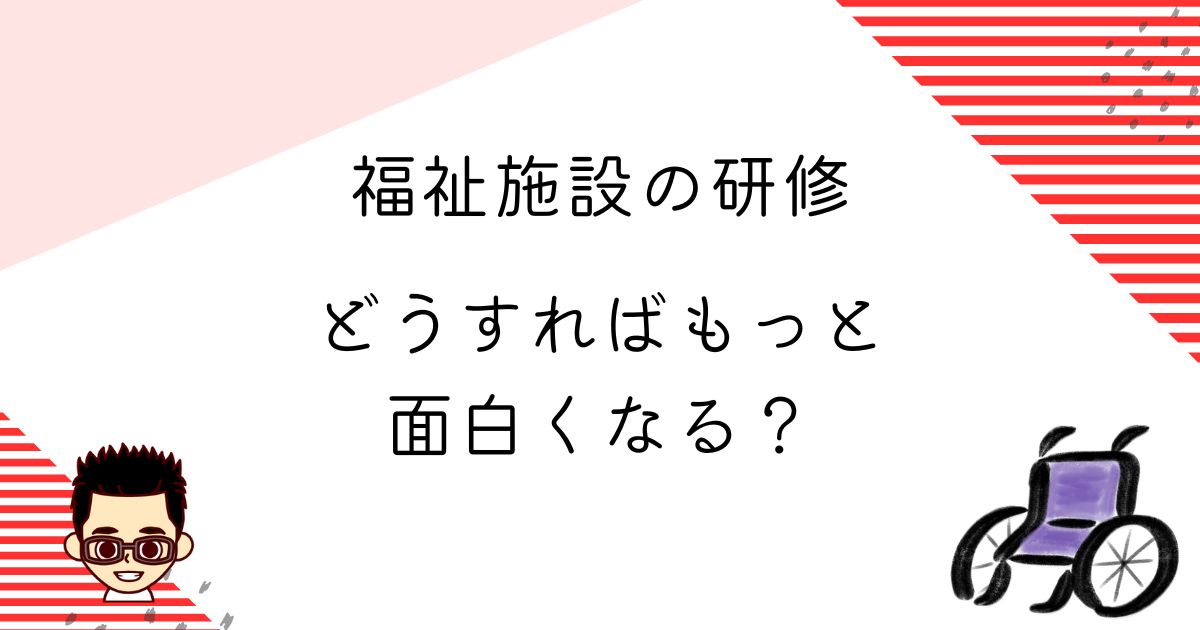


コメント